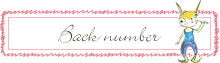村本 邦子
摂食障害をテーマにして一度考えてみたいと思いながら数年が過ぎた。これが興味深い現代の奇病で あると思うからではなく、これはまさに「私たちの病」であると感じているからである。本特集の執筆者たちは、皆、我が国にも摂食障害が顕著に増加した高度 経済成長期とともに大きくなり、痩せ礼賛の風潮が強まるなか、ダイエット本やダイエット食品、シェイプ・アップ器具に取り巻かれた環境を生きてきた。そう いう私たちにとって、「ダイエット中よ」という会話は日常茶飯事だし、拒食、過食、嘔吐、下剤を使っての浄化すら、異常と言うよりはむしろ馴染みのあるも のだった。FLCワークショップで体やセクシュアリティについて語り合うと、自分も若い時は摂食障害だったという女性が少なからずいる。医療機関の世話に なった女性もいれば、健康を害するほど極端な行動は年齢を重ねていつのまにか消えたという女性もいる。現在もなお、摂食をめぐって苦しんでいる女性もい る。執筆者のうち数名も、過去に何らかの形で摂食障害を経験している。大袈裟だと言われるだろうか?「かつて摂食障害だった」と語る女性たちを、何らかの 相談機関にかかった経歴を持っていなければ専門家は軽く見がちであるが、実際にDSM III-Rの診断基準を満たしている場合も多い。
美しくありたい、スタイル良くなりたいというありふれた願望から、健康を害し、生命を危険にさら すほどの病的な状態にいたるまで全般をテーマにしたが、私たちがこれらの背景にある原因がひとつだと考えているわけでは決してない。D.M.シュウォー ツ、M.G.トンプソン、C.L.ジョンソンは「神経性食思不振症は数ある病因の、最終的な共通経路である」と言っているが、これに賛成である。P.Y. アイゼンドラスは、本紙の論文を「もつれ」(Entanglements)と題しているが、まさに私たちの体こそ、数々の要因がもつれあう場所として選ば れるのである。それは何故か考えてみたかった。つまり、本特集は、摂食障害の背後にある個人の問題をさぐることが主眼ではなく(個々のケースにはさまざま な要因が絡んでいるだろう)、なぜそれらの問題が最終的に摂食障害という形を取るかという点に重点が置かれている。
大雑把ながら摂食障害に関する文献を集めてみて、とくに医療や心理の専門誌に取り上げられている ものには、社会文化的側面に関しての考察が乏しい(考察はあってもそれが必ずしも治療に反映しない)という印象をまず受けたが、アメリカではフェミニズム の理論をも含めて、社会文化的側面に関する目配りがきいており、翻訳されたもののなかにすぐれた文献をいくつか見いだした。また、我が国でも、生野らによ る患者と家族の会、斉藤らによるセルフヘルプ・グループの実績は注目に値する。勉強するにつれて、今さら若輩である私たちが摂食障害について何か言おうと することが恥ずかしくもなってきた。しかしながら、初めに述べたような理由で、私たち自身も自分たちの問題として、これについて一度考えてみたかったので ある。
数人の執筆者が触れているが、摂食障害の女性に治療者として関わりながらも、一方では「痩せてい る方が確かに美しい」と客観的に(と言うよりは現代文化の基準で)クライエントに価値判断を下している自分に気づいたり、私たち自身がふだん容貌にとらわ れていることに気づいてはっとする瞬間がある。女を容貌やスタイルで判断するのは、何も男に限ったことではない。この社会に生きる者として、私たち自身が 否応なく社会の価値観に取り込んでしまっていることを自覚することには、いつも痛みがつきまとう。私たちにとって、ひょっとすると、この特集の試み自体が セルフヘルプの意味を持っていたのかもしれない。
光栄なことに、本年度はフェミニストでありユング派の分析家であるP.Y.アイゼンドラスによる 寄稿論文を掲載することができた。彼女は現在、主に摂食障害に専門的に関わっている。我が国ではまだまだ、精神療法の専門家とフェミニスト・セラピストと が相入れない状況であるが、専門性とフェミニズムが必ずしも反目しあうものではないということを知ることで、おおいに勇気づけられる。執筆者たちは、伝統 的な理論からも、フェミニズムの理論からも学ぶべきところは貪欲に学びたいと考えている。
アイゼンドラス以外の執筆者たちは、この特集を書く準備として、何度か研究会を開き、また書いた ものについて互いにコメントしあった。家族療法を始め、馴染みのなかった治療法を学んだことはよい勉強になったが、身体摂食を伴うような治療法については 批判的である。アイゼンドラスやオーバックらのフェミニスト・セラピーについても勉強した。一回は、国立京都病院の臨床心理士で摂食障害を長年にわたって 経験してきた中村このゆさんのお話を聞いた。たくさんの症例を経験しておられること、とくに重症の摂食障害を扱ってこられたことから、外来では経験できな い事例について聞くことができた。中村さんたちは、近く摂食障害についての本を出版するそうである。
市川と河合は現場で摂食障害のクライエントを多く抱えており、医療チームのなかの臨床心理士とし て、主として一対一の面接による治療を行っている。市川は小児科で心理療法のケースをあげて、コントロールという視点から論じている。摂食障害の子どもた ちは感受性が強く、他者の欲求や気持ちに過敏に反応し、結果として自分の欲求を抑え込んでしまういわゆる「いい子」であると言われるが、症状を通じて家族 をコントロールし、新しいあり方を探るという指摘は興味深い。年齢が低ければ低いほど、子どもを取り巻く環境、カルチャーとしての家族は大きな意味を持っ てくる。家族療法が効果をあげているのもそれゆえだが、家族というサブカルチャーにある「女の子」の意味を書換え、その力動を変えることが治療的に働くと 考えられるだろう。この場合、入院がひとつの枠組みとして機能していることにも注目したい。
河合はそれよりも年齢がやや高めのケース、黒川内科で試みてきた「体重制限療法」を用いた外来治 療の症例を提示している。この場合の枠組みは、入院ではなく、入院を回避するための制限体重である。河合が「枠」を、この社会で女性に与えられた枠組みに 準えていることは興味深い。それが固定し融通性を失って問題が生じているわけだが、治療者とのギャングエイジ的なかかわりを通じて、与えられた枠組みを自 分なりに調整し修正していくことを学んでいく。あとは、社会のなかで自分に与えられた枠をどの程度受入れ、どの程度修正していくかという応用問題である。 この場合、ギャングエイジと言われているものは、P.Y.アイゼンドラスの言うところのピア・グループに等しいと思われるが、これもひとつのサブ・カル チャーと考えることができる。
以上は臨床の場から見た摂食障害であったが、次は、もう少し一般的に見た摂食障害の問題を論じて いる。私たちは基本的に摂食障害を文化の病と捉えているが、ここでは、その文化を支え、また支えられている女性たちの心理に焦点を当ててみる。西は、主に 食と母娘関係について考察する。歴史的に言って、「食」と「母」が密接に結びついてきたこと、家族が役割分業をするようになって、母と娘の関係が複雑な意 味と絡みを含んでいることから、母が「娘なるもの」に囚われ、娘が「母なるもの」(食)に囚われていくさまを記述し、またどうやってそこから解放され得る かを示唆している。
村本は主に女性と性について論じる。摂食障害は、自分の肉体や性を受け入れられないことと密接に 関係しているが、摂食障害の問題を抱えるか否かにかかわらず、一般的に言って、この社会では、女性たちが性を含む自分の体というものを受け入れることがど んなに困難であるか、一般の女性の声を拾いながら見ていく。とくに体の変化が著しく、摂食障害が起こりやすい思春期を中心に、その前後、女性たちが、現実 としてどのような心理的発達をしていくのかをたどりながら、摂食障害との関連を考えてみる。
ここではさらに視野を広げて、文化のコンテクストに目を向ける。石原はまず、摂食障害と特別な関 わりを持たない一般女性と男性に、女性の体型についてのインタビューを試みているが、そこには、女性、男性ともに取り込んでしまっている理想の体型と現実 が二重にくっきりと浮かび上がってくる。次に、「ダイエット」という言葉や「痩身=美」という等式が人々の意識に刻み込まれていく過程を出版物の流れとと もに追っていく。スタイルのコントロールが西洋化のひとつとして我が国に取り入れられ、初めは医者たち専門家によって健康法として広められたが、80年代 になるとダイエットがファッションと一体になって、さらに大衆化していく。このような価値観を広めることに一役買った専門家やマスコミの責任が大きいこと が改めてよくわかるが、裏返せば、この社会を変えていくために専門家やマスコミは大きな力を持っており、これを生かすも殺すもひとりひとりの「意識覚醒」 次第なのだということである。文化に対する無力感、消極的現状維持の姿勢を問いなおしたいものだ。
越智は摂食障害を文化の病として、とくに「倒錯と嗜癖」という観点から切り込む。現代文明の根底 には、一般的に「パワーへの限りない欲求」と無力無能な「内なる赤ん坊」が表裏一体となってあるが、とくに痩身がパワーと結びつく女性にあっては、これが 「受動的パワーによる完全な世界(他者)支配」という倒錯した形で表現されやすい。この場合、「保護する治療者」と「か弱い患者」という治療構造において は病理が強化されるばかりであり、むしろ患者その人こそが場を構成する重要な一員として機能する構造が必要である。摂食障害は従来の治療構造を超え、セル フヘルプ・グループ、あるいは治療者が治療者として機能しなくなるようなバラドクシカルな治療の場でこそ癒されるものであるという指摘は非常に重要であ る。市川・河合論文でも見るように、治療場面においても、治療者/クライエントという二者関係にではなく、治療者/クライエントを包む場、カルチャーとい う拡がりのある視点を持っていなければならないのである。
本特集では、このように、摂食障害を特殊な人々の病気としてではなく、正常な人々と「陸続きにある"行動の偏異"」(越智)として、その陸自体を調べてみようとする試みであり、同時にその地質を変えるエッセンスの一滴にでもなればと不遜にも願っている。
文献
R.アイケンバウム、S.オーバック(1988)『フェミニスト・セラピー』(長田妙子、長田光展訳)新水社。
R.S.W.エメット編(1991)『神経性食思不振症と過食症』(S.W.エメット編、篠木・根岸訳)星和書店。
S.オーバック(1992)『拒食症』(鈴木二郎他訳)新曜社。
生野照子、新野三四子(1993)『拒食症・過食症とは-その背景と治療』芽ばえ社。
伊藤比呂美、斉藤学(1992)『明るく拒食、ゲンキに過食』平凡社。
『女性ライフサイクル研究』第3号(1993)掲載
 「今時の子どもたちは...」という言い回しは、非難のニュアンスとともにいつの時代にもありましたが、子どもたちの心が見えないのは、それを見ようとしないからですし、子どもたちの声が聴こえないのは、それを聴こうとしないからではないでしょうか。
「今時の子どもたちは...」という言い回しは、非難のニュアンスとともにいつの時代にもありましたが、子どもたちの心が見えないのは、それを見ようとしないからですし、子どもたちの声が聴こえないのは、それを聴こうとしないからではないでしょうか。

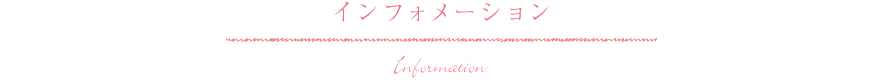
 中年期というのは、女性の一生の中でも、これまでの人生を振り返り、この先の人生の生き方を模索する、重要な転換期です。それにも関わらず、今までほとん ど取り上げられることのなかったこのテーマに、本書では、女性の視点から、女性の手で光を当ててみました。中年期女性の心・体・性・夫との関係、親子の問 題、介護、シングル女性など、さまざまな中年期女性のさまざまな側面に目を向けて、取り上げています。
中年期というのは、女性の一生の中でも、これまでの人生を振り返り、この先の人生の生き方を模索する、重要な転換期です。それにも関わらず、今までほとん ど取り上げられることのなかったこのテーマに、本書では、女性の視点から、女性の手で光を当ててみました。中年期女性の心・体・性・夫との関係、親子の問 題、介護、シングル女性など、さまざまな中年期女性のさまざまな側面に目を向けて、取り上げています。 セルフヘルプ・グループとは、生きづらさを抱えた者同士が支え合う自助グループのことです。ごく自然に人々が支え合っている社会ならば、あえてセルフヘル プ・グループの必要はないのでしょう。けれどそうではない現実の中で、互いに支えあうことで生きやすくしていく側面や、自然には支えてくれない社会に対し て、自分たちの生きにくさを訴えていく側面などがセルフヘルプ・グループにはあります。それぞれのグループの歴史、活動内容などセルフヘルプ・グループに ついての情報を満載しておりますので、必要に応じて連絡を取って参加してもらえますし、さまざまなグループのあり方を参考に、必要に応じて新しいグループ を作ってもらえたらと思います。ぜひ、ご一読ください。
セルフヘルプ・グループとは、生きづらさを抱えた者同士が支え合う自助グループのことです。ごく自然に人々が支え合っている社会ならば、あえてセルフヘル プ・グループの必要はないのでしょう。けれどそうではない現実の中で、互いに支えあうことで生きやすくしていく側面や、自然には支えてくれない社会に対し て、自分たちの生きにくさを訴えていく側面などがセルフヘルプ・グループにはあります。それぞれのグループの歴史、活動内容などセルフヘルプ・グループに ついての情報を満載しておりますので、必要に応じて連絡を取って参加してもらえますし、さまざまなグループのあり方を参考に、必要に応じて新しいグループ を作ってもらえたらと思います。ぜひ、ご一読ください。 1995年1月17日、戦争を体験していない世代にとっては、初めての歴史的大惨事の経験ともいえる阪神大震災が起きました。既に数年が経っており、建物 は修復され、表面的には復興が成し遂げられたかのように見え、世間の関心はだんだんと薄くなってきているかのように思われます。しかしながら、個々人の心 のなかでの復興、つまり、震災の経験をどう自分のものとして生き抜くかについては今なお、途上にあると言えます。本書は、あまり取り上げられることのな かった女性、子どもの視点から阪神大震災を捉え直したものであり、この震災を心に留めておくためにも、また援助する側にとっても貴重な1冊であると思いま すので、ぜひ、ご一読ください。
1995年1月17日、戦争を体験していない世代にとっては、初めての歴史的大惨事の経験ともいえる阪神大震災が起きました。既に数年が経っており、建物 は修復され、表面的には復興が成し遂げられたかのように見え、世間の関心はだんだんと薄くなってきているかのように思われます。しかしながら、個々人の心 のなかでの復興、つまり、震災の経験をどう自分のものとして生き抜くかについては今なお、途上にあると言えます。本書は、あまり取り上げられることのな かった女性、子どもの視点から阪神大震災を捉え直したものであり、この震災を心に留めておくためにも、また援助する側にとっても貴重な1冊であると思いま すので、ぜひ、ご一読ください。 昨今、犯罪報道をめぐって、表現の「自由」を優先するか、それとも「人権」を優先するかが人々の関心を集めています。何によらず誰かの手によって表現され たことは、その個人を越えて力を持つこととなります。すると、意図するしないにかかわらず、その力は誰かの脅威となり得るのです。本書では、このような力 を持つ「表現」を、様々な角度から再検討しています。例えば、抑圧されている立場の子どもや女性にとって「表現」がどのような意味を持つのか、また、何か を生み出すことと「表現」との関係やセクシャリティの問題などにも言及しています。自分にとっての「表現と自由」について再考するためにも、本書をお薦め します。
昨今、犯罪報道をめぐって、表現の「自由」を優先するか、それとも「人権」を優先するかが人々の関心を集めています。何によらず誰かの手によって表現され たことは、その個人を越えて力を持つこととなります。すると、意図するしないにかかわらず、その力は誰かの脅威となり得るのです。本書では、このような力 を持つ「表現」を、様々な角度から再検討しています。例えば、抑圧されている立場の子どもや女性にとって「表現」がどのような意味を持つのか、また、何か を生み出すことと「表現」との関係やセクシャリティの問題などにも言及しています。自分にとっての「表現と自由」について再考するためにも、本書をお薦め します。