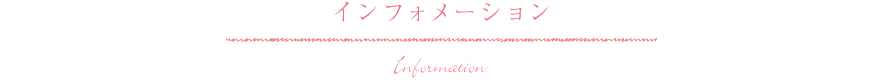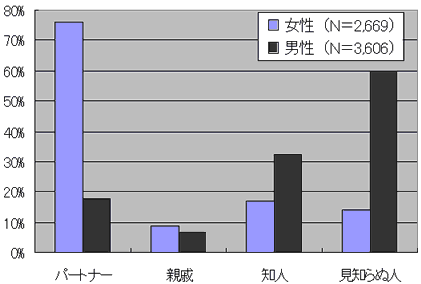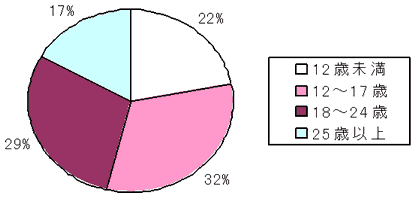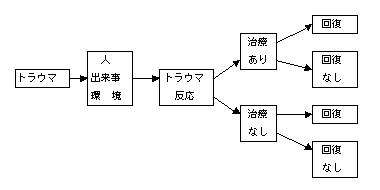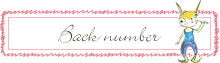ハーバード大学臨床心理学助教授/ケンブリッジ病院暴力被害者治療プログラム主任
メアリー・ハーベイ(村本 邦子訳)
1 はじめに
トラウマにさらされた被害者は、急性もしくは遅延性の外傷後ストレス障害(PTSD)(アメリカ 精神医学会、1994)、複雑型外傷性症候群(Herman, 1992a, 1992b)、一連のトラウマ関連性精神障害(Brett, 1992)、広範囲にわたるトラウマ反応と回復のパターン(Briere, 1998; Browne & Finkelhor, 1986; Cohen & Roth, 1987)を示す可能性があることが、研究結果や臨床経験からわかっている。トラウマ反応の多様性をトラウマ以前の個人特性から理解する臨床家は多い。し かし、その一方、トラウマの程度と持続時間(Kulka et al., 1990)、トラウマとなった出来事の特徴(Herman, Russell, & Trocki, 1986; Roth, Wayland & Woolsey, 1990)、被害者の解釈(Green, Wilson, & Libowitz, 1988)、被害者を取り巻く環境(Green, Wilson, & Lindy, 1985; Koss & Harvey, 1991; Wilson, 1989)が同じように重要であることを示唆する研究も多い。
トラウマに関する既存の文献は、トラウマ反応と回復における個人差に環境要因が関与していることを過小評価する傾向がある。とくに、臨床的な文献は、個 人の回復力(resiliency)、臨床的援助なしの回復の可能性、社会・文化・環境の影響を見過ごしがちである。「回復」の定義づけが曖昧で、トラウ マからの回復を示す基準がはっきりしていないことも多い。
この論文では、これらの問題を取り上げるために、コミュニティ心理学の概念である生態学の視点を利用する。この視点から言えば、人間の心理的特性は、コ ミュニティという生態学的文脈で、もっともよく理解できるし、出来事への反応は、コミュニティで養われた価値、行動、技術、理解に照らせば、もっともよく 理解できる(Kelly, 1968, 1986; Koss & Harvey, 1991)。本論文では、この考え方をトラウマ現象にあてはめ、トラウマ反応と回復の個人差を理解する生態学的モデルを提示する。このモデルでは、個人差 を、人、出来事、環境の3つの要因の相互作用と考える。これら3つの要因は相互作用して、人とコミュニティの力動関係を決定し、それぞれに独自な回復の文 脈をつくる。生態学的モデルでは、トラウマからの回復結果を4つの概念に分け回復の多次元的定義を提示する。臨床的援助が回復を助けるのか、それとも損ね るのかについても取り上げ、臨床的援助とは違ったコミュニティ介入が回復力を育てることにも触れる。臨床的援助もコミュニティ介入も、それが有効に働くか どうかは、人によって違う回復の文脈に、生態学的適合(ecological fit)を果たし、その人とコミュニティの関係をうまく強化できるかどうかにかかっている。
2.生態学の視点から見たトラウマ
(1)生態学の視点とは
生態学とは、有機体とその環境との相互関係を扱う科学である(Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, 1985)。コミュニティ心理学は、生態学的文脈から、コミュニティに関心を向け、人とコミュニティの相互関係を扱う。人は、コミュニティからアイデン ティティ、所属感、意味を引き出す(Kelly, 1968, 1986; Koss & Harvey, 1991)。人の行動を生態学から見る時、コミュニティ心理学者は、実地生態学者が他の生命環境を調べるのとまったく同じ仕方で、コミュニティを調べる。 「生態学のアナロジー」(Kely, 1966, 1986; Trickett, 1984)は、資源と資源交換の特性という観点からコミュニティを記述する。たとえば、コミュニティのお金、サービス、価値、伝統が循環し、共有され、豊 かになったり、枯渇したりといった点に見ることができる。また、コミュニティ成員の欲求と環境に対して、適応と健康を促進したり、逆に、不適応と不健康を 促進するコミュニティの特質にも見ることができる。
生態学のアナロジーをトラウマの領域に応用すると、トラウマとなる暴力的出来事は、人の適応能力への脅威と捉えられるばかりでなく、成員が関わり合っ て、健康と回復力を育てるというコミュニティの能力への脅威とも考えられる(Koss & Harvey, 1991; Norris & Thompson, in press)。つまり、都心部で増えつつある暴力は「酸性雨」のようなもので、成員に安全な天を提供するコミュニティの能力への生態学的脅威と見ることが 可能になる。人種差別、性差別、貧困は環境汚染、つまり、暴力を育て、人のコミュニティの健康促進資源を破壊する生態学的異常と考えられる。
暴力的な出来事がコミュニティ資源を汚染し破壊するように、コミュニティの価値、信念、伝統はコミュニティ成員の防御壁となり、暴力に続く回復を支え る。貧困と人種差別がコミュニティを暴力に晒す危険性を高める生態学的要因だと考えられるなら、経済を安定させ、多様性を認める視点をコミュニティに流布 させることが、暴力を予防するエコロジー要因になる。同様に、女嫌い(misogyny)と家父長制が性暴力を増やし、女性の幸福を脅かす生態学的要因で あると考えられるなら、コミュニティに根ざしたレイプクライシスセンターや「夜を取り戻そう」キャンペーン、性暴力を許さないコミュニティづくりは、女性 の安全と幸福を支持する生態学的要因となろう(Koss & Harvey, 1991)。
ほとんどの人は、多様なコミュニティに属している。たとえば、地理(市、町、近隣)、人種、民族、言語を共有するコミュニティの一員であり、また、職業 や宗教、思想を共有するコミュニティの一員でもあるだろう。ここで提示する生態学的モデルは、トラウマとなる暴力的出来事への個々の反応は、それぞれが所 属しアイデンティティを引き出す複数のコミュニティの特性の組み合わせによって変化すると仮定する。人とコミュニティの相互作用を形づくるのは、人、出来 事、環境のさまざまな組み合わせである。
(2)トラウマの生態学―「人×出来事×環境」モデル
図1はトラウマ、治療、回復の生態学的モデルである。このモデルには3つの前提がある。第1は、 トラウマとなる出来事が同じであっても、誰もが、同じように傷ついたり、影響されるわけではないということである。被害を受けやすいか、被害への反応と回 復は、互いに影響しあう3つの要因によって多面的に決定される。3つの要因とは、巻き込まれた人や人々との関係、経験された出来事、より広い環境である。 これらの要因が一緒になって、人とコミュニティの生態システム(ecosystem)が決定される。その中で、人はトラウマとなり得る出来事を経験し、対 処し、意味づけを行っていく。
生態学的モデルの第2の前提は、トラウマとなる出来事に晒された後、人は臨床的援助を求める場合もあれば、求めない場合もあるということである。求めな い人の方が多いだろう。トラウマを十分に理解するためには、治療を受けない大多数に目を向け、トラウマ後の状態と回復のプロセスを明らかにする調査が必要 である。
第3の前提は第2と密接に関わっているが、臨床的援助は、必ずしも、回復の保証にはならないということである。生態学的モデルでは、回復結果に関する4 つの概念を立てている。1)臨床的援助が他の要因と作用しあい、回復を助ける。2)臨床的援助が回復を妨げ、損なう。3)臨床的援助なしに回復がおこる。 とくに、自然発生的な生態システムが回復力を支え、自然なサポート体制とコミュニティ資源が豊富にあるとき。4)時宜を得た適切な介入がなく、回復できな いまま。
生態学の枠組みで考えると、回復の失敗は、個人の苦悩が持続することを意味するだけでなく、回復する環境の欠如、コミュニティ心理学者が生態学的適合と 呼ぶものを達成するようなトラウマへの介入の失敗をも意味する。生態学的適合を構成するのは、人と社会的文脈の関係の質と有用性であり、人と環境の結びつ きを強める必要がある。つまり、孤立感を減らし、社会的能力を高め、良い対処を促し、コミュニティへの所属感を促進しなければならない。(Levine, 1987; Maton, 1989)。
生態学的モデルは、グリーンら(Green et al., 1985)が仮定した心理社会的枠組みと一致し、ウィルソン(Wilson, 1989)が描いた統合的個人・環境モデルとも一致する。違いは、出来事と環境要因の区別、被害化の社会・文化政治的文脈に置かれる力点、回復と復元力の 源泉としてコミュニティを強調する点である。
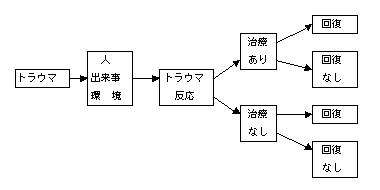
図1.トラウマのエコロジー・モデル
(3)「人×出来事×環境」がトラウマ反応に与える影響
人、出来事、環境に関するたくさんの要因がトラウマ反応と回復に影響を与えるが、なかでも、生態 学的視点からとくに重要なのは、人とコミュニティの関係に影響を及ぼす要因である。そのなかには、臨床家がクライエントのニーズを査定するとき日常的に考 慮されるものもあるが、無視されることが多いものもある。
トラウマ反応と回復に影響を与える人の変数には、たとえば、年齢、発達段階、被害時の苦痛の程度、知性、人格、感情、認知、トラウマ以前の対処能力、ま た、もしあるとすれば、それに先立つ外傷、被害者と加害者の関係、その他もろもろの人口集団的特徴がある。経験を積んだ臨床家ならばほとんどが、これらの 変数に注意を払い、診断決定と治療計画に重要な役割を果たす。生態学的視点からは重要だが、臨床上のアセスメントではあまり注意を払われない人変数には、 トラウマを受けた人が、自分の文化のなかで、被害体験をどう理解するか、さまざまな種類の援助を抵抗なく受けられるかどうか、家族、友人、その他重要な人 が希望、粘り、回復力のモデルを提供してくれるかどうかなどがある。
出来事変数は、一回、あるいは一連のトラウマ体験の特徴を示すものである。トラウマ反応を決定する重要な要因には、経験された出来事の頻度や強度、持続 度、身体的な暴力や性暴力が含まれていたか、恐怖や屈辱の持続度、一人だったのか、他の人と一緒だったのかなどがある。その他、出来事に付随し、その人と コミュニティが重きを置いているものと関わる部分も重要である。たとえば、強い信仰をもつ帰還兵は、敵兵の死体によって負わされた十字架に苦しみ続けるだ ろうし、恐怖のために抵抗できず、加害者に同意と喜びの言葉を強制されたレイプ被害者は、それを恥じ、苦しみ続けるだろう。トラウマそのものがもっとも傷 ついた部分であるはずだという思い込みは捨てる必要がある。そして、トラウマの解釈や記憶、感情と経験のニュアンス、その人のトラウマ反応に影響を与える 固有の社会構造など周辺部分にも耳を傾ける必要がある。
トラウマ反応と回復に影響を及ぼす環境要因はたくさんある。トラウマが経験される生態学的文脈(家、学校、職場、その他)の特徴、自然なサポート体制、 良い適応を育てるシステムの力、トラウマ後の被害者に与えられた安全とコントロールの度合いなどである。被直後、最初の対応者がどんな態度を取ったか、家 族、友人、世話役、その他の重要な他者および集団がどう理解し行動したかは、回復のための重要な要素となる。生態学的視点からトラウマと回復を理解する上 で重要な環境要因は、コミュニティのもつ態度や価値観、人種とジェンダーについての文化的構造、被害者に向けられる政治経済的要因、コミュニティの被害者 援助とアドボカシー資源の質、量、接近しやすさ、文化的妥当性を挙げられる。英語をしゃべれない難民が災害に遭ったとき、その人を取り巻くコミュニティが 移民の増加を恐れ、あからさまに敵対的な態度を取るなら、回復する気力もなくなるだろう。コミュニティに「主流な」サービスの質と利用しやすさがどうであ ろうと、この人にとって、接近しやすさと文化的妥当性はどう見積もっても制限される。同性愛恐怖によるゲイ・バッシングの被害者は、伝統的な道筋からプロ の援助を求めるのは嫌でも、別の設定や非公式のネットワークを通じて得られる適切な援助にはつながるかもしれない。
(4)4つの回復結果
生態学的モデルでは、トラウマを受けた被害者をグループ分けする。どこかの時点で臨床的援助を受 けた人、受けなかった人、トラウマから回復した人、していない人である。概念的に4つの回復結果が考えられるわけだが、それぞれに特有の問題と、臨床的援 助とコミュニティ介入の課題がある。
1. 臨床的援助を受け、回復したトラウマ被害者
このグループは、いちばん臨床家の興味をひくものである。臨床家の援助を受け、あきらかな効果が あった場合である。治療効果を査定し、確認する調査が必須である。トラウマ被害者にかかわる臨床的仕事で有望なのは、今のところ、安全とエンパワメントと いうふたつのテーマを強調するフェミニスト的な治療アプローチ(Harvey & Herman, 1992)、症状を管理し減らしていく認知行動療法的技術(Foa, Steketee & Rothbaum, 1989, 1991; Keane, Fairbank, Caddell, zimering & Bender, 1985; Resick, Jordan, Girelli, Hutter & Marhoefer-Dvorak, 1989)、統合的トラウマ集中治療(Wilson, 1989)、トラウマによる情動とパターンの解決を促進する力動認知アプローチ(McCann & Pearlman, 1990; Roth & Newman, 1991)、孤立感を減らし新しい愛着を形成する安全な場を提供するグループ療法(Koss & Harvey, 1991; van der Kolk, 1987)、段階別・多元的治療アプロ―チ(Herman, 1992b; Lebowitz, Harvey & Herman, 1992)が挙げられる。
2. 臨床的ケアを受けたが、効果なく、回復していないトラウマ被害者
生態学的モデルでは、2番目のグループになる。さまざまな治療アプローチの成功と効果を臨床家が共 有し、研究者が確認する一方で、治療の失敗も同じように立証し、治療を失敗させた生態学的条件を確定することが重要である。たとえば、身体的な安全と生理 的安定が得られて初めて、トラウマの記憶をさぐることが実りをもたらすこと、早すぎる時期に慌ててトラウマを探ることは、傷つきやすい患者を不安定にし、 再度トラウマに晒すことになるという厳しい事実を学んできた臨床家は少なくないだろう(Herman, 1992b; Horowitz, 1986)。同様に、患者のもつ文化・歴史的背景に鈍感だったり、患者の回復予後に関するコミュニティの信念、価値、資源の役割について誤った情報しか もっていなければ、その治療法は、生態学的視点から言って、制限され、失敗しやすい。
3. 臨床的援助なく回復したトラウマ・サバイバー
このグループは、危機と苦境にあって、内的・外的資源をうまく活用できた人々からなる。研究者も臨 床家も、このグループから学ぶことは多い。これらの人々は、ストレスへの抵抗力という内的資源を持っていたのだろうか。回復のスキルを新たに獲得したのだ ろうか。具体的なコミュニティ資源や個人的なサポート・ネットワークによって、防御できたのだろうか。回復の基盤にある資質は、遺伝子的に決定されている ようなものなのか、あるいは、後天的に獲得されたもので、他の人にも獲得することができるものなのだろうか。手短に言えば、このグループにとって、トラウ マへの予防接種の役割を果たした要因は何なのだろう。これらの要因は、臨床的技法とコミュニティ介入によって再製したり、動員したりできるものなのだろう か。
4. 臨床的ケアを受けず、回復していないトラウマ被害者
生態学的モデルで4番目のグループは、長い間、研究者からも臨床家からも目を向けられなかった人々 である。傷ついたまま、孤立して生きており、不適切な対処法と資源に頼っているかもしれない。いずれにせよ、臨床的ケアを受けていない。このグループにつ いて、もっと学ぶ必要があるし、彼らの孤立感を減らし、利用できる資源があることに気づいてもらえるようなコミュニティ介入を考える必要がある。たとえ ば、公共教育のキャンペーンはトラウマ反応に関する理解を促し、これらの反応が奇妙なものではないことを理解する助けとなる。アウトリーチのキャンペーン は、利用可能な臨床的資源をはっきりさせ、接近を促すだろう。これらの資源がないコミュニティでは、コンサルテーション活動と、トレーナーの養成プログラ ムによって、準プロフェッショナル、牧師、しろうとの援助者の理解と技術を促し、治療を受けていないトラウマ被害者に役立つことができるかもしれない。
3.回復の多次元的定義
(1)トラウマからの回復の定義
回復の実践的な定義について書いた文献はあまりない。あっても2種類で、どちらも適切とは言えな い。1つ目は、包括的なもので、長期にわたる心理療法をやり遂げ、トラウマに起因するものしないものも含めて葛藤を統御し、最終的に解決することを目指 す。これらの治療目標は称賛に値するが、トラウマからの回復というより、「包括的精神衛生」と呼べるだろう。トラウマそのものについての理解を助けるもの ではないし、有効な介入計画についても、治療結果の調査に関しても方向性を与えない。2つ目は、外傷後ストレス障害に特徴的な過覚醒と侵入性の症状に限定 したものである。このアプローチは、トラウマからの回復の症状の減少と考えているようだ。たとえば、フラッシュバックや悪夢がなくなるとか、トラウマを想 起するときの反応が穏やかになるなど。この定義には、臨床介入するうえで特別の焦点をあて、症状から逃れることの重要性を強調する利点がある。しかし、そ の他のトラウマ関連性障害、ハーマン(1992a)が「複雑型PTSD」と呼んだものには役立たない。たとえば、症状がなくなっても、恥と自責の念や、い わゆる「サバイバーシップ」(Janoff-Bulman, 1985)と呼ばれる孤立感や不信感などの持続を考えるうえでは不足である。トラウマからの回復を症状の減少だと考えれば、非常に効果的な心理療法の過程 において、症状が強まる時期があることを理解できないだろう(Briere, 1989)。
ここに提示する生態学的モデルでは、トラウマからの回復を、以下のような基準によって特徴づけられる多元的な現象として理解する。
1. 記憶の再生への権限
記憶と意識の変異はトラウマ性障害の中心である(APA, 1994)。トラウマとなった出来事は、記憶の再生と利用に混乱を与える。サバイバーはしばしば、自分が経験したことの記憶の一部がなかったり、その場面 が突然現れて、凍りついてしまったりする(van der Hart, Steele, Boon & Brown, 1993)。トラウマからの回復の最初の兆しであり、それゆえ第一の治療目標となるのは、記憶に対し、新たな権限を得ることである。回復すると、いきなり 意識に侵入してきたものを、思い出すか、思い出さないか、選択できるようになる。記憶喪失がなくなる。思い出せなかった部分が思い出され、新しい意味が記 憶に付け加えられる。記憶との力のバランスが逆転し、サバイバー自ら、まとまり連続した物語として記憶を呼び起こせるようになる。
2. 記憶と感情の統合
単発のトラウマでも、慢性化した一連のトラウマでも、記憶ははっきりとつながっているが、思い出し ても何も感じない、ほとんど感じない場合がある。逆に、特定の刺激に反応して、恐怖や不安、怒りなどが押し寄せるが、これらの感情が何と結びつくのかまっ たくわからない場合もある(Harvey & Herman, 1994)。いずれも、記憶と感情が分離しており、その結果、心理的問題が生じている。回復すると、記憶と感情が結びつき、感情を伴って過去が思い出せる ようになる。その体験をした時に起こった心と体の状態がいくぶんか再現されるだろう。悲しい記憶は再び悲しみを引き起こし、怒り、不安、その他も同じよう に記憶と結びつく。回復すると、過去についての現在の感情も区別して理解できるようになる。たとえば、回復したレイプ被害者は、その時の恐怖を思い出し感 じると同時に、それを思い出している今、新たな怒りと悲しみをも感じるだろう。
3. 感情への耐性
回復とは、トラウマと結びつく感情にもはや圧倒されたり脅かされたりしなくなることである。トラウ マと結びつく感情が、耐えがたいほどの直接性と強烈さを失う。圧倒されたり、防衛的な感覚麻痺や解離なしに、感情を受け入れ、名づけ、耐えられるようにな る。不適切な警報と危険信号から解放される。感情がさまざまに分化し、記憶に一定の反応ができるようになり、現在のストレスに対処する能力が増す。
4. 症状管理
とくに持続していた症状が弱まり、管理可能になる。たとえば、フラッシュバックを引き起こす刺激が 何か知り、避けられるようになる。回復したサバイバーでも症状が続くことはあるが、うまく対処して、症状を減らし、ストレス管理ができるようになる。たと えば、暴力的な映像など苦痛を呼び起こす刺激を避けたり、ストレス管理の技術を使ったり、なかなか消えない症状に対しては、薬を処方してもらって適切に利 用することで改善できるだろう。重要なことは、すべての症状がなくなることではなく、症状を予測し管理できるようになることである。
5. 自己評価と自己の凝集性
1回のトラウマであっても、自己感や自己の価値に対して破壊的な影響を及ぼす力を持っている (Terr, 1983)。幼少期の慢性化し繰り返された被害は、アイデンティティに深刻な影響を与え、自己を不連続で断片化したものにする。回復すると、自己評価と自 己の凝集性の面で、これを修正し制御できるようになる。自傷行為や自己破壊的な衝動がなくなり、健康で自己受容的になる。断片化していた自己は、凝集性を 持ち一貫した自己が体験される。罪の意識、恥、自責の念がなくなり、自己の価値を感じられるようになる。強迫的で自己批判的な考えがなくなり、現実的に自 分を評価し、肯定できるようになる。自分はケアされるに値することに気づき、自分で自分をなだめたり、自己実現していけるようになる。
6. 安全な愛着関係
他者から孤立し、再び被害者となりやすい傾向は、トラウマと密接に関わっている。暴力や信頼の裏切 りを伴うトラウマ体験は、悲惨にも、安全で支持的な人間関係を求め、維持していく能力を危うくする(van der Kolk, 1987)。トラウマからの回復は、対人関係能力の発達、あるいは改善と回復を含む。孤独に固執していたのが、信頼や愛着関係を持てるようになる。人との 関係で身体的、感情的な完全を求め維持できるようになり、いくぶんかの楽観主義とともに、親密な結びつきを期待できるようになる。そこまでいくには、複雑 な再交渉や、重要な人への服喪が必要だろう。ほとんどの場合、サバイバー自ら、社会的な支援のネットワークを広げていくだろう。
7. 意味づけ
最後に、トラウマ、サバイバーとしての自己、トラウマが起きた世界に新しい意味づけがなされる (Janoff-Bulman, 1985)。トラウマの意味づけは個人的なものであり、非常に個性的なプロセスである。とくに、暴力によるトラウマで、人は残虐行為を行うという事実と直 面させられるような場合はそうである。損なわれた自己という感覚がなくなると、それまで不幸を背負ってきたと思いこんでいたものが、力と共感を得たという 新たな発見に変わる場合もある。自分の体験を創造的に表現したり、確固たる社会活動へと変容させ、サバイバー使命を抱くことが回復のプロセスの一部となる 人々もある(Herman, 1992b)。「なぜ」「なぜ私が」という問いにスピリチュアルな答えを出す人もあろう。プロセスはさまざまだが、回復したサバイバーは、トラウマに名前 をつけ、喪に服し、命を肯定し自己を肯定するような意味づけを行う。
これらの基準は、1回、あるいは一連のトラウマによって否定的な影響を受け得る心理機能の全領域を反映している。すべてを含めて、回復の多面的な定義であ り、臨床家、サバイバー、研究者に個々人の回復を査定し、臨床的介入、コミュニティ介入が目指すべき基準を与えてくれる。治療を受ける受けないにかかわら ず、サバイバーの回復と復元力を生態学的視点から多次元的に査定する概念的枠組となる(Harvey, Westen, Lebowitz, Saunders & Harney, 1994)。この枠組では、トラウマに影響を受けたどの領域でも、プラスの方向で変わったとすれば、回復が進んだということになる。あまり影響を受けな かった領域があり、その領域の力を使って、問題のある領域に対処し、回復できるとすれば、これは、復元力と呼べる。たとえば、記憶の侵入などに苦しんでい るサバイバーが、相対的に損なわれなかった領域にある対人関係能力を使って、誰かに支えてもらったり、有益な心理療法を受けることもあろう。安全な愛着関 係の領域にある強さと復元力を動員して、症状管理と記憶再生への権限の回復を得たと言える。人と会うのが怖くなった暴力被害者は、しっかりした自己感とス ピリチュアルな価値感を動員することで、信頼と結びつきの感覚を取り戻すかもしれない。この場合、自己評価と意味づけの領域の力が、安全な愛着関係の領域 の修復を助けたと言える。
(2)レイプからの回復-生態学的モデルによる事例と分析
生態学的モデルは、トラウマ反応のさまざまを予測することができる。人・出来事・環境要因の相互作用と、トラウマ反応・回復への環境の影響力について、二人の女性を対比させながら例示しよう。どちらも近所のバーで知り合った、いわゆる「顔見知り」の男性にレイプされた。
サラは21歳、白人の中流階級に属するボストンの大学生。どちらかと言えば平等主義の家族に育ち、両親はともに子育てに関わってきた。サラはフェミニス ト・グループの一員で、さまざまなキャンパス活動に従事している。ある夜、地域のバーで友人と別れた後、ちょっと興味のある男性と話し始めた。彼が送って くれると言うので、サラは、もっと彼を知る機会だと期待し、同意した。帰り道、サラは彼のあからさまな性的行動が嫌で、突き離した。すると、彼は怒り、暴 力でもってレイプしたのである。
ジョアンも21歳の白人。ボストンから西へ数マイル離れた田舎にある労働者階級のコミュニティに住む、信心深い閉鎖的な大家族で育った。ジョアンは運動 が得意で、自己主張的なので、二人の兄は「おてんば」だと思ってはいたが、彼女の強さを誉めてくれた。しかし、両親は、ジョアンの「女らしくない」行動に 腹を立てることがしばしばだった。学校の成績もよかったが、高校を卒業すると同時に結婚。今は離婚し、4歳と2歳の子どもと、実家近くの小さなアパートに 暮らしている。地元のレストランでパートタイムで働き、地域のソフトボールチームの強力な選手でもある。試合に勝った夜、ジョアンは友達と近所のバーに 寄った。その夜のバーは、とくに騒々しかったが、友達と別れた後、彼女はもうしばらくそこにいた。それまでも見かけたことのある男性が、家まで送ろうと 言った。その男は、駐車場で、人気のないところまで運転するよう命令し、レイプしたあげく、行ってしまった。
1. 人×出来事×環境要因について
人の属性という観点から言えば、サラもジョアンも多くの共通点がある。どちらも白人で21歳、両親 の子育て態度と、家族の教育水準は違うが、どちらも養育が行き届き、結びつきの強い家族の育った。それぞれ違う点は、サラは未婚で、ジョアンは離婚したこ と。サラは大学生、ジョアンは働いていた。サラは中流階級、ジョアンは労働者階級に属していた。サラの生活は、金銭的に困るようなものではなかったろう し、責任も少なかった。ジョアンは、しばしば家族に経済的な援助を求めなければならなかった。サラにとって、女性も男性と同じ機会と生活様式が与えられる べきであることは明白だったが、ジョアンは、社会的な制限に反発しながらも、同時に伝統的な性役割のステレオタイプと、家族やコミュニティを特徴づけてい る信念を是認している部分もあった。
2. 出来事について
どちらも、近所のバーで出会い、知り合いになりたいと思った男性にレイプされた。どちらも身体的な 残虐性と屈辱が伴い、どちらもアルコールが一要因になっている。レイプの後は、侵入的な記憶を経験し、恐怖と苦痛を再体験した。非常に長い間、個別の特徴 が頭から離れなくなる。サラは、レイプした男性に最初にひきつけられたのは自分だったという事実を思い出して、特別恥ずかしく感じるだろう。ジョアンは、 恐怖のあまりに戦えず、自分の肉体的な力が役に立たなかったことに屈辱を感じるだろう。
3. 環境について
しかしながら、回復の予後に関する限り、生態学的視点から最も重要なのは、彼女たちの状況を特徴づ ける環境要因である。サラもジョアンも心から心配してくれる友人や家族がいたが、二人を支えるネットワークを構成する人々は、レイプに対する見方、アル コールへの態度、専門的な援助や精神科医の治療を受け入れる素地という点で大きく異なる。二人が住むコミュニティとそこでの選択肢も非常に違っている。
たとえば、サラは、フェミニスト仲間に友人がたくさんいて、その大半は、これがレイプであり、責任があるのは加害者の方だということをはっきり理解してい る。サラの友人のなかにも、「私を変だと思う人」もいるし、サラも、彼女たちの言葉を「本気でそう思っているのかしら」と疑うことはある。それでも、サラ のコミュニティには、彼女を支える人々がたくさんいるし、必要な資源も豊かにある。彼女の親友のなかには、これらの資源のことをよく知っていて、利用する よう励ましてくれる女性もいる。彼女の家族は、専門機関を利用することに慣れている。家族も「誰かに話を聞いてもらう」こと、とくに、レイプ・クライシス についてのトレーニングを受け、トラウマの知識がある人に聞いてもらうことを励ますだろう。
ジョアンの状況は違っている。彼女の故郷である田舎には、レイプ・クライシス・センターも、特別な訓練を受けた緊急医療隊も、地域警察の性被害対策部もな い。彼女の話を聞き、家族に電話した方がいいのか、するとすれば、いつ、何を話せばよいのか、決めるのを助けてくれるレイプ・クライシス・ワーカーもいな い。ジョアン自身も自分の体験をどう考えたらよいのかわからない。これはレイプだろうか?彼女の両親を含め、彼女の故郷であるコミュニティの多くの人は、 「良い娘」はレイプされないと信じていることだろう。ジョアンの町には、公的な資金によるメンタルヘルスケアの方法はほとんどないだろうし、トラウマに対 するサービスは実質的に皆無だろう。個人開業している臨床家はわずかながらいるだろうが、ジョアンやジョアンの知り合いが予約の電話をすることはないだろ う。彼女の家族でセラピーを受けたことのある人はいない。友人のなかには、十代の息子を指導カウンセラーに連れていった人、夫をつれて、夫婦カウンセリン グに行こうと考えている人はいるが、ジョアンは彼女たちに、レイプのことを話そうとは思わないだろう。
4. 臨床介入による査定と援助
サラの生活の現実は、臨床家に査定と援助を受けるにいたる生態学的条件をつくりだしている。資源が 豊富にある都会のコミュニティには、多くのメンタルヘルスの実践家や専門家がいて、そのなかから選択することができる。選択肢が広いので、サラに合う実践 家が見つかる可能性は高いだろう。また、若い白人、シングル、中流階級、教育水準が高いなど、サラと多くの共通点を持つボランティアスタッフをたくさん抱 える草の根的なフェミニスト資源も揃っている。多くの共通点を持つ人々がいることで、これらの資源の文化的妥当性は高まり、サラがそれらを効果的に利用す る可能性も高くなるだろう。これらの資源は、サラの回復を助けるコミュニティ・サポートとなるだけでなく、専門家への紹介にも結びつくかもしれない。これ らの条件が、必ずしも容易な回復や最善の臨床経験を保証するわけではないが、サラは、これらの条件のなかで回復の道を探ることができるだろう。サラの生態 系は、その伝統、信念、価値観などが有効な臨床資源の利用を促進する力を持っている。
他方、ジョアンの方は、臨床的な援助を受ける方法をさがせそうにない。その経験を誰かに話すよう励ます友人はいるかもしれないし、自分のレイプの体験を話 してくれる友人もいるかもしれない。お酒でも飲んで気持ちを紛らわしたらと言う友人もいるだろうし、教会に戻って、司祭に話すよう勧める人もいるだろう。 でも、専門的な援助を受けるよう励ます人はほとんどないだろう。もちろん、状況が変わる可能性はある。とくに、レイプの体験そのものが、ジョアンとコミュ ニティの生態学的な関係を変えることがある。たとえば、彼女が告訴を決めれば、弁護士に会うことになるが、その弁護士が、はっきりとそれはレイプであると 言い、心理的査定を受けるよう紹介するかもしれない。法廷の被害者権利擁護の人が、適切なサービスを紹介してくれることもあるだろう。彼女の体験したレイ プの状況と残虐性がコミュニティの誰かに知れて、ジョアンに援助の手が差し延べられ、そこから臨床的援助へとつながる可能性もあるだろう。しかしながら、 生態学的視点から言えば、ジョアンが臨床的援助につながる可能性、仮につながったとしてもそれが彼女の回復に役立つかどうかは、サラと比べれば、はるかに 当たりはずれのあるものになる。臨床的援助のあるなしより、ジョアンの回復は、それ以外の資源に大きくかかってくるだろう。
5. 回復への生態学的影響
レイプの直後、サラもジョアンも激しい苦痛を経験し、自己感覚や他者への信頼、世界観にひどい混乱 が生じたことだろう。生態学的視点から言えば、時間が経つにつれ、回復を支える他者や環境の違いが、多次元の回復領域における修正と復元力の程度の違い、 トラウマから回復へいたる道の違いとして現れてくる。サラは、被害にあったその夜、別の選択をすればよかったと考えては、自己感と自己評価をかき乱される 思いを経験するかもしれない。自分をレイプするような男に興味を持った自分を責め、彼が暴力的な男であると見抜けなかった自分を腹立たしく感じもするだろ う。そのうち、コミュニティのなかに、彼女が期待するほど断固として彼女の味方になってくれない人もでてくるかもしれない。たとえば、友人の少なくとも何 人かは、なぜ、なんとかしてレイプを防げなかったのかと思っていることが判明するかもしれない。家族のなかにも、学校の職員や警察のなかにも、彼女がどの くらいお酒を飲んでいて、その時の判断力が鈍っていたかを問う人がいることだろう。
サラは、ほとんど同じことを自問自答していたことに気づく。自分のことを心配してくれる人々に申し訳なくて、自分がまた前の状態に戻れるのだろうかと不安 に思うことだろう。しかし、結局のところ、サラを支えてくれる人々の多くは、彼女の経験がレイプであると理解できるので、彼女の苦痛を理解し、この一貫し た見解で支えてくれるだろう。彼女たちは、臨床的援助を受けてみるように励ますだろうし、サラもその勧めに従うことだろう。レイプ・クライシスのボラン ティアと話すことで、さまざまな医療および法的選択があることを理解し、選択の助けとするだろう。のちには、心理療法が自己感と自尊心を脅かす感情や記憶 を点検する助けとなるかもしれない。トラウマの記憶が侵入してくるのは症状のひとつであることを知り、少しずつコントロールできるよう治療を利用するだろ う。人一般、とくに男性に対して不信感と恐怖を感じるかもしれない。その場合、レイプ・サバイバーのグループに参加することで、他者を警戒したり、安全で 満足のいく人間関係を求めているのは自分一人でないことを理解するようになるだろう。心理療法の内でも外でも、このような目標をもって、肯定的な愛着と比 較的損なわれていない対人関係能力の蓄積を活かせるようになるだろう。そして、新たな人間関係をつくり直し、自分の経験を意味づけることができる。
レイプ後のジョアンの経験は、ずいぶん違うようだ。トラウマの記憶に襲われることを、ジョアンも身近な人も、レイプによって起こり得る感情的な反応として 理解できない。ジョアンは自分が傷ついたこと、怒っていることを知っているが、それがレイプだったのかどうかには確信がもてない。少なくとも、彼女の両 親、近所の人、友人たちがレイプと思わないことは確かだろう。両親は深く恥じるかもしれない。近所の人たちに知られたくないだろう。兄弟は加害者に腹を立 てるだろうが、危険な行動をとったジョアンにも腹を立てることだろう。ジョアン自身、傷つき、我が身を恥じている。
ジョアンも、サラのように損なわれた自己評価を修正し、対人関係を作り直し、自分の経験の意味づけをしなければならない。しかし、サラと違って、まずレイ プに対する新しい理解ができるようになる必要があるし、家族や近隣、教会に行き渡っているジェンダー構造に挑戦し、新しい社会的サポートと理解の資源をさ がさなければならない。そうするさい、彼女は、自分が保持している力を使って、自分がレイプされても仕方ないことをしたのだと仄めかす態度をきっぱりと拒 否する必要があるだろう。彼女の兄弟がその判断にアンビバレントではあっても、彼女の力を認め、彼女の勇気を褒めるなら、彼女の重要な資源となるだろう。 互いの関係を大事に思うチームメイトは、文化的妥当性から言えば、サラにとってフェミニストのコミュニティにあたり、これもまたはかり知れない資源の一部 となる。この仲間にレイプのことを話せれば、多くの人がそれをレイプだととらえ、彼女の苦しみに共感を示し、再び生活のコントロールができるよう励まして くれることがわかるかもしれない。さらに、チームにおける自分の地位を確認することで、ジョアンは、再び自分の肉体的力を感じ、スポーツに打ち込む力を少 しずつ取り戻していくだろう。気持ちを建て直すなかで、わずかながらあるコミュニティの資源を見つけ、公的なサポートによって回復を助けてもらえるかもし れない。たとえば、地域の弁護士事務所、法廷の被害者権利擁護プログラムなどである。こういったものがあって、活用できれば、彼女の回復が助けられるだけ でなく、その社会活動の成果や、彼女の経験をはっきりレイプと定義する州法によっても益することになる。
6. 介入と生態学的適合を構成するもの
生態学的モデルは、介入が成果をあげるためには、個々人の回復の文脈にうまく適合するものでなけれ ばならないことを示唆する。サラが利用できる臨床的援助は、この基準にうまく合うかもしれない。他方、ジョアンの回復に対する臨床的援助の適切さは、制限 されている。まず、彼女がいる地域のコミュニティに適切な資源があるかどうかわからないし、あってもその質はどんなものかわからない。さらに、ジョアンが 臨床的援助にうまく馴染めるかどうかを決定する生態学的要因も制限されている。レイプ被害から数週間、数ヶ月経てば、ジョアンのチームメイトによる援助と 法廷にある被害者権利擁護の側のアウトリーチの方が、彼女にははるかに有益で、生態学的適合を達成していることがはっきりするかもしれない。ジョアンの回 復には、文化に浸透しているジェンダー構造と個人的に対決し、あまりに馴染み深い加害者を支持するような信念の点検が、確実に必要である。ジョアンに新た な社会的サポートの道とレイプに対する新しい理解を提供するコミュニティ介入は、これを促進し、コミュニティと彼女の生態学的関係を決定的に変えるだろ う。それこそが有効な臨床的介入の唯一の道であるかもしれない。
4.臨床的介入と調査へのヒント
生態学的モデルを念頭に置くと、ほとんどのサバイバーは複雑に入り組んだ世界に生きており、トラ ウマにいつも臨床的援助があるとは限らず、ない場合がほとんどであること、あったとしても臨床的援助はつねに有効とは限らないし、当てにならないことも多 いということを思い知らされる。サラとジョアンの事例は、多くの点で似た状況にあり、初めての単発トラウマの例である。二人の人種、民族の特徴を変えた り、あるいは子ども時代のトラウマ、大人になってからの殴打、深刻な物質依存の家族歴や差別、貧困、制度上の無視と個人間の暴力が日常的であるようなコ ミュニティに住んでいるなど、レイプされた女性の条件を変えていけば、彼女たちの回復への生態学的課題は、もっと複雑になる。どんな介入も、その有効性 は、その課題に適い、孤立感を減らし、当人になじみのある社会的文脈のなかで有効な対処法を促進できるかどうかにかかっている。
(1)生態学的視点から見て適切な臨床的介入の特質について
有効な臨床的介入は、生態学的視点を入れた査定から始まる。トラウマからの回復の多次元的定義か ら言えば、損なわれた領域と、力として残っている領域の両方を特定する査定が重要である。回復と復元力の多次元的査定(Harvey et al., 1994)に基づいて治療計画を立て、被害者とコミュニティの関係に肯定的な影響を与える臨床的介入のデザインの基礎をつくることができる。多様な個人の 予後と回復にもっとも適した臨床的介入の特質は何なのか、はっきりさせるような研究が必要である。この特質には、介入の試みがなされるタイミング、設定、 目的と方法論が、そして、力のある部分を促進したり、損なわれた部分を修正するような特質、また、トラウマを受けた人の住む文化およびコミュニティの特徴 が含まれるはずである。生態学的枠組みでは、トラウマが生じた社会・経済・政治的環境は同じだけ重要だし、サバイバーが自分の経験を理解するうえでコミュ ニティが影響を及ぼすことに臨床家が気づいていることも重要である。有効な臨床的介入をするためには、トラウマ被害者がアイデンティティと意味づけを引き 出すより文化、人種、民族、言語的コミュニティに普及しているトラウマ理解、被害化と援助に対する理解について知っておく必要があるし、場合によっては、 それらに挑戦しなければならないだろう。
(2)社会変革とコミュニティ介入について
臨床的援助を利用しない人、あるいはそこから利益を得られない人たちは非常に多いので、治療を受 けないサバイバーの回復の研究と復元力についてのコミュニティに根ざした研究が必要である。効果的なコミュニティ介入の努力もますます必要になってくるだ ろう。たとえば、幅広い人々に対してトラウマと暴力についての情報を与え、トラウマに続いて多くの心理的な反応が起こるが、それは正常であることを理解さ せるような公共教育活動は、臨床的介入の効果を高めるものである。ある人たちにとっては、これらの介入は、臨床的援助以上に高い効果をあげる。同様に、そ れぞれの成員の権利を擁護し、抑圧の政治的修正を目指す市民の人権グループ、子どもの権利擁護団体、フェミニスト・グループ、レズビアンとゲイの組織は、 被害化の経験の意味づけを変えるうえで、数年にわたる個人セラピーよりもずっと多くのことができるかもしれない。警察官による不適切な取扱をなくすための 法改正や、告訴弁護士、救急医療隊員も被害者の予後を助けることができる。臨床的援助という選択肢と競合する必要はないが、臨床的、コミュニティ的、社会 的介入といった幅広い範囲を捉える視点が必要である。
5.要約
生態学的視点からトラウマを見るとき、トラウマ後の反応と回復パターンは、人・出来事・環境の3 要因が複雑に作用し合って決定されると考えられる。生態学的モデルは、サバイバーを、臨床的介入を受けた人、受けない人、さらに、それぞれについて、回復 した人、していない人の下位グループに分ける。どのグループにも、臨床調査、コミュニティ調査に固有の問題提起を行い、異なった課題がある。とくに、私た ちがふだんほとんど会うことのない人々のことを知っておく必要がある。それは、専門的援助なしに回復した人、専門的援助が必要なのに、得られず回復してい ない人である。
生態学的モデルは、トラウマからの回復は多次元的であること、臨床的援助のない回復もあることを認め、個人の持つ復元力、環境の役割、自然な援助、適切 なコミュニティ介入などにも目を向ける。これらの介入は、現在、治療を受けておらず、おそらくは孤立したまま苦しんでいるサバイバーの回復を促進するうえ で重要だし、トラウマを引き起こす暴力的な出来事を減らすうえでも重要である。
References
References
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington,DC: Author.
Brett, E.A. (1992). Classifications of PTSD in DSM-Ⅳ: Anxiety disorder, dissociative disorder, or stress disorder. In J. Davidson & E. Foa (Eds.) Posttraumatic stress disorder. DSM-Ⅳ and beyond (pp.191-204). Washington,DC: American Psychiatric Press.
Briere, J. (1988). The long-term clinical correlates of childhood sexual victimization. Annals of the New York Academy of Sciences, 52(8), 327-334.
Briere, J. (1989). Therapy for adults molested as children: Beyond survival. New York: Springer.
Browne, A., & Finkelhor, D. (1986). Impact of child sexual abuse: A review of the research. Psychological Bulletin, 99, 66-77.
Cohen, L., & Roth, S. (1987). The psychological aftermath of rape: Long-term effects and individual differences in recovery. Journal of Social and Clinical Psychology, 5, 525-534.
Foa, E.B., Steketee, G.S., & Rothbaum, B.O. (1989). Behavioral/cognitive conceptualization of post-traumatic stress disorder. Behavior Therapy, 20, 55-176.
Foa, E.B., Rothbaum, B.O., Riggs, D.S., & Murdock, T.B. (1991). Treatment of post-traumatic stress disorder in rape victims: A comparison between cognitive behavioral procedures and counseling. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 715-723.
Green, B.L., Wilson, J.P., & Lindy, J.D. (1985). Conceptualizing posttraumatic stress disorder: A psychosocial framework. In C.R. Figley (Ed.), Trauma and its wake, Vol Ⅰ: The study and treatment of post-traumatic stress disorder (pp.53-69). New York: Brunner/Mazel.
Harvey, M.R., & Herman, J.L. (1992). The trauma of sexual victimization: Feminist contributions to theory, research and practice. PTSD Research Quarterly, 3(3), 1-7.
Harvey, M.R., & Herman, J.L. (1994). Amnesia, partial amnesia and delayed recall among adult survivors of childhood trauma. Consciousness and Cognition, 3, 295-306.
Harvey, M.R., Westen, D., Lebowitz, L., Saunders, E., & Harney, P. (1994). Multidimensional trauma recovery and resiliency interview and Q-sort. Unpublished Manual. Cambridge, MA: The Cambridge Hospital Victims of Violence Program.
Herman, J. (1992a). Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma. Journal of Traumatic Stress, 5(3), 377-391.
Herman, J. (1992b). Trauma and recovery. New York: Basic Books.
Herman, J.L., Russell, D.E.H., & Trocki, K. (1986). Long-term effects of incestuous abuse in childhood. American Journal of Psychiatry, 143, 1293-1296.
Horowitz, M. (1986). Stress response syndromes (2nd ed.). Northvale, NJ: Jason Aronson.
Janoff-Bulman, R. (1985). The aftermath of victimization: Rebuilding shattered assumptions. In C.R. Figley (Ed.), Trauma and its wake, Vol.Ⅰ. The study and treatment of post-traumatic stress disorder (pp.15-35). New York: Brunner Mazel.
Keane, T.M., Fairbank, J.A., Caddell, J.M., Zimering, R.T., & Bender, M.E. (1985). A behavioral approach to assessing and treating posttraumatic stress disorders in Vietnam veterans. In C.R. Figley (Ed.), Trauma and its wake, VolⅡ: The assessment and treatment of posttraumatic stress disorders (pp.257-294). New York: Brunner/Mazel.
Kelly, J.G. (1968). Towards an ecological conception of preventive interventions. In J.W. Carter (Ed.), Research contributions from psychology to community mental health (pp.3-57). New York: Behavioral Publications.
Kelly, J.G. (1986). An ecological paradigm: Defining mental health consultation as a preventive service. In J.G. Kelly & R.E. Hess (Eds.), The ecology of prevention: Illustrating mental health consultation (pp.1-36). New York: Haworth Press.
Koss, M.P., & Harvey, M.R. (1991). The rape victim: Clinical and community interventions. Newbury Park, CA: Sage.
Kulka, R.A., Schlenger, W.E., Fairbank, J.A., Hough, R.L., Jordan, B.K., Marmar, C.R., & Weiss, D.S. (1990). Trauma and the Vietnam war generation. New York: Brunner/Mazel.
Lebowitz, L., Harvey, M.R., & Herman, J.L. (1992). A stage by dimension model of recovery from sexual trauma. Journal of Interpersonal Violence, 8(3), 378-391.
Levine, M. (1987). An analysis of mutual assistance. American Journal of Community Psychology, 16(2), 167-188.
Maton, K.I. (1989). Towards an ecological understanding of mutual-help groups: The social ecology of "fit." American Journal of Community Psycholory, 17(6), 729-753.
McCann. L., & Pearlman, L. (1990). Psychological trauma and the adult survivor: Theory, therapy and transformation. New York: Brunner/Mazel.
Norris, F.H. & Thompson, M.P. (1995). Applying community psychology to the prevention of trauma and traumatic life events. In J. Freedy & S. Hobfoll (Eds.), Traumatic stress: From theory to practice. New York: Plenum.
Resick, P.A., Jordan, C., Girelli, S., Hutter, C., & Marhoefer-Dvorak, S. (1989). A comparative outcome study of behavioral group therapy for sexual assault victims. Behavior Therapy, 19, 385-401.
Roth, S., & Lebowitz, L. (1988). The experience of sexual trauma. Journal of Traumatic Stress, 1(1), 79-107.
Roth, S., Wayland, K., & Woolsey, M. (1990). Victimization history and victim assailant relationship as factors in recovery from sexual assault. Journal of Traumatic Stress, 3(1), 169-180.
Terr, L. (1983). Chowchilla revisited: The effects of psychic trauma four years after a school bus kidnapping. American Journal of psychiatry, 140, 1543-1550.
Trickett, E. (1984). Toward a distinctive community psychology: An ecological metaphor for the conduct of community research and the nature of training. American Journal of Community Psychology, 12, 261-279.
Van der Hart, O., Steele, K, Boon, S., & Brown, P. (1993). The treatment of traumatic memories: Synthesis, realization and integration. Dissociation, 6, 162-180.
Van der Kolk, B.A. (1987). The psychological consequences of overwhelming life experiences. In B.A. van der Kolk(Ed.), Psychological trauma (pp.1-30). Washington, DC: American Psychiatric Press.
Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1985). Springfild, MA: Merriam-Webster.
Wilson, J.P. (1989). Trauma, transformation and healing. New York: Brunner/Mazel.
Wyatt, G.E., Guthrie, D., & Notgrass, C.M. (1992). Differential effects of woman's child sexual abuse and subsequent sexual revictimization. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60, 167-173.
Wyatt, G.E., Notgrass, C.M., & Newcomb, M. (1990). Internal and external mediators of woman's rape experiences. Psychology of Women Quarterly, 14, 153-176.
注)本論文は、Plenum Publishing Corporationの許可を得て、"Journal of Traumatic Stress, Vol.9, No.1"より翻訳転載しました。
『女性ライフサイクル研究』第9号(1999)掲載