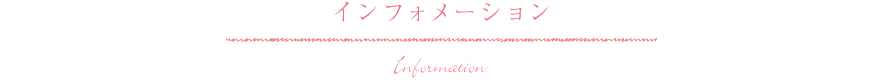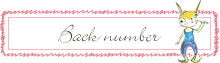- 1991.11.23 年報『女性ライフサイクル研究』
- 女性のライフサイクルについての試論
村本邦子(女性ライフサイクル研究所)
(1)はじめに
娘として生まれ、育ち、他家に嫁いで妻や母や嫁としての役割を果たした後、今後は息子の嫁を迎え て姑になる・・・というのが、従来の女性の道だった。基本的には、どんな家に生まれるか、そしてどんな家に嫁ぐかが女の別れ道であり、その決定は当人の意 志ではないものに委ねられていた。ライフサイクルという意味では、比較的単純で、有無を言わせぬものだったと言える。誰々の娘、誰々の妻、誰々の母といっ た何者かに付随する形でアイデンティティが規定され、個々の女性は、その時々、自分に与えられた枠内で、悩み、苦しみ、喜び、楽しみ、それなりに自分を表 現してきたと言える。
ところが、この枠組み自体が崩れつつある。時代は変わったと言う時、その変化を支えた女たちの苦闘は背後に隠れ、見えなくされてしまう。私たちは、変化 の御利益を当然のごとく享受すればするほど、その影の部分に目を配ることを忘れてしまいがちであるが、御陰様で、時代は確かに変わりつつある。結婚するこ とが必ずしも自明のことではなくなったし、結婚しても仕事を続け、妻としての役割よりも自分自身の人生を重視することは可能だし、子供を持たぬ選択をする カップルもでてきた。結婚せずとも子供を持つことはできるし、妻や母として生きていた人生を途中でスパッと捨てることも不可能ではない。女性の生き方が多 様化したぶん価値観は混迷し、自由が増したぶん責任は重くなった。このような時代に生きる私たち女性は、いったい何を基準にして生きていくのだろうか。そ れに伴い、女性のライフサイクルはどのように変化していくのだろう。
(2)これまでのライフサイクル研究
ライフサイクルの研究としていつも挙げられるのが、エリクソンの研究とレビンソンの研究である。ここでは、ふたりと、これらに先立つユングの研究を紹介しよう。
1.エリクソンの研究
前論文でも紹介されているように、エリクソンの発達概念の根底にはエピジェネシス(個体発達分化 と訳されたりする)という考えがある。これは、未分化なものが時間とともに次第に分化していく様相を表すものであり、ひとつの段階が終わって次の段階に変 わるというよりは、もともと可能性として全てを含んでいる人間のその時々の現れの順路のようなものを意味している。彼は、社会的側面と関わりながら発達し ていく段階を次のように8つの段階に分け、それぞれを特徴的な社会的、心理的危機と対応させ、危機をどのように乗り越えるかによってパーソナリティが形成 されるとする。この場合、危機とは、破局を意味するものではなく、発達のための転機であり、「成長と回復と分化の可能性を統合しつつ、各発達段階での発達 課題が達成されねばならないときの、必要不可欠な転回点や決定的瞬間を指すもの」である。エリクソンの用語については、さまざまの訳語が提案されている が、本論文では、桑原(1990)、細木(1983)、河野(1985)を参考にする。
1.乳児期は、信頼対不信。母親的人物との相互的な関係のなかで、他者に対する信頼と自分に対する信頼を学ぶ。
2.早期児童期は、自律性対恥・疑惑。親的人物(複数)との関係で、自律性を身につけ、自分が一個の人間であることを確信する。
3.遊戯期は、積極性対罪悪感。家族のなかで、同性の親との同一化によって性役割を学ぶ。
4.学童期は、勤勉性対劣等感。学校生活において、仲間をつくり、学び、ものを作ることを通じて自己の拡張を図る。
5.青春期は、同一性対同一性拡散。他の人々や集団のなかで期待される役割の遂行や情緒的コミュニケーションを通して得られる安定感や連帯感を通じて、自分はこれこれこういう人間であるという実感を得る。
6.若い成人期は、親密・連帯対孤立。異性と親密な関係を結び、結婚が課題になる。
7.成人期は、生殖性対停滞。自分たちのパーソナリティとエネルギーを、共通の子孫を産み育てることに結合したいという願望を基盤に拡がっていく発達課題である。
8.成熟期は、統合性対絶望。何らかの形でものごとや人々の世話をやりとげ、子孫の創造者、物や思想の生産者としてのさけがたい勝利や失望に自己を適応させた人間だけが7つの段階の果実を次第に実らせていく。
エリクソンは、社会との関わりを重視したので、基本的には社会的役割を果たし、社会の要請に答え ることが発達の主眼となる。もちろん、この場合、それは本人の自然な欲求に基づくものであるはずであり、彼も社会的役割に縛られて息絶え絶えになっている ような適応の仕方は考えていなかったことだろう。しかし、今や、社会の要請と個人の欲求との間に大きなズレが生じており、とくに女性に関しては、個々人の 欲求と期待される役割とのギャップが大きくなりすぎたあまり、エリクソンの発達課題を踏むことが、必ずしもそれぞれの「果実を実らせる」ことにつながらな いと考えられる。私たちは、このギャップをはっきりと認識し、社会的役割自体を問い直さなければならない時にきていると言える。
2.レビンソンの研究
レビンソンは、伝記的面接法(biographical interviewing)という研究方法によって個々の人間のケーススタディから人生を四つに分けた。レビンソンの訳語については、河合(1983)と山下(1990)を参考にする。
1.児童期と青年期(0~22歳)
2.成人前期(17~45歳)
・成人への過渡期(17~22歳)
・おとなの世界へ入る時期(22~28歳)
・30歳の過渡期(28~33歳)
・一家を構える時期(33~40歳)
3.中年期(40~65歳)
・人生半ばの過渡期(40~45歳)
・中年に入る時期(45~50歳)
・50歳の過渡期(50~55歳)
・中年の最盛期(55~60歳)
4.老年期(60~)である。
細かく分けられた年令はわかりやすいものでありながら、研究対象となったアメリカ男子の平均値を 示すに過ぎず、日本に住む私たち女性のことにまで一般化するには無理がある。しかし、彼が自分の著書を「人生の四季(The Seasons of a Man's Life)」と名づけているのは示唆的で、人生の四季の変化になぞらえていると考えられる。そのまま春夏秋冬とあてはめているのか定かではないが、「過渡 期」という言葉が所々に現れてくるように、クルクルとめぐり移り変わっていく人生の変化を考えているのだろう。この過渡期を彼が重視したことも意義深く、 とくに私たち女性にとっては、体が大きく変化する時、社会的役割が転換する時である過渡期あるいはイニシエーションの意味がもっと研究されてしかるべきと 思われる。
3.ユングの研究
時期的には前後することになるが、ユングは1946年の論文で、ライフサイクルという言葉を使っていないながらも、人生全体の心理学の先駆者とされている。彼は、人生を少年期、青年期、壮年期、老年期の4つに分け、太陽の運行に例えて次のように美しく語る。
朝になると、この太陽は無明の夜の大海から昇ってくる。そして天空高く昇るにつれて、太 陽は、広い多彩な世界がますます遠く延び広がって行くのを見る。上昇によって生じた自分の活動範囲のこの拡大の中に、太陽は自分の意義を認めるであろう。 そして最高の高みに、つまり自分の祝福を最大限の広さに及ぼすことの中に、自分の最高の目標を見いだすであろう。この信念を抱いて太陽は予測しなかった正 午の絶頂に達するのである――予測しなかったというのは、その一度限りの個人的な存在にとって、その南中点を前もって知ることはできないからである。正午 十二時に下降が始まる。太陽は矛盾に陥る。それは、あたかもその光線を回収するようなぐあいである。光と暖かさは減少して行き、ついには決定的な消滅に至 る。(ユング,1979,p.50)
彼の考えでは、東から西へ向けて四等分された半円のうち、最初の少年期は問題のない状態であり、 問題は自覚されず、他人にとって問題であるだけである。青年期には、母親からの独立、強い自我の達成、子供としての地位を放棄して大人としてのアイデン ティティを獲得すること、健全な社会的地位の達成、結婚、出世が課題となる。正午を経て、価値観の決定的転換が生じなければならず、これまで外界での成功 へ邁進していたのが、内的価値を求めるようになり、意味と精神的価値への関心へと変わっていく。老年期は再び無意識的状態へと沈みこんでいく。彼の考えの ユニークな点は、「正午の革命」とも呼ばれる中年期に起こるこの価値観の逆転であろう。これは心理的次元ではもちろんのこと、肉体的次元においても生じる と言う。たとえば、南方の諸民族においては、中年の女性は声が低くなり、口ひげが生え、顔つきも険しくなり、他のいろいろな点でも男性的特徴を示すように なり、逆に、男性は脂肪ぶとりや容貌の穏やかさといった女性的な特徴によって和らいでくる。武人でもあるインディアンの酋長が、心の正午、夢のお告げを受 け、以後、女子供と起居をともにし、女の衣装をつけ、女の食べ物を食べるようになったが、声望を失うことはなかったという例も報告されている。
ユングによれば、一般に、人生前半(青年期)には、社会的役割を重んじ、達成することを目指し、 人生後半(壮年期)には、文化・社会的役割から自由になり、個々の価値観に目覚めていくということになる。ところがこれに反して、現代の若者たちが必ずし も社会的役割や外界での成功にとらわれず内的価値を求めようとする傾向をもつことは既に指摘されている。つまり、インディアンの酋長の例のように男が典型 的な「男らしさ」を達成した後、女性性にも目覚めていくというのではなく、最初から男性性をも女性性をも生きようとする女男が出現しつつあるとも言える。 この場合、外的価値から内的価値へという転換はあまり意味をなさなくなる。
彼の太陽の比喩はたいへん興味深い。一日の人生を一日の太陽の運行に準えるなら、1年、10年、100年・・・と考えていくと、どれほど多くの人々が生 まれ、死んでいくことか。この発想は、想像もつかないほど大きな宇宙の存在を意識させてくれる。この意識こそ、おそらく、ライフサイクルを考える際、根底 を流れる視点であると言えるだろう。
(3)女性のライフサイクルをどう考えるか?
これまでのライフサイクル研究を概観して、ライフサイクルが社会的役割、あるいは社会の要請と切 り離せないものであることがわかっただろう。同時に、前、村本詔司論文でも明らかにされているように、ライフサイクルは、個体からもっと大きな存在へとひ ろがりゆく生命の鼓動や欲求とも深く関わり合っているのである。まず、社会的側面から、次に生命的側面から、現代に生きる女性のライフサイクルを考えてみ よう。
1.時代はどう変わったか? ――社会的連関に生きる私たち
女性としてライフサイクルを考える時、男性中心社会が女性に課する役割や要請と、女性の生命の鼓 動や欲求とに大きなズレがあることは既に述べた。たとえば後の津村論文のテーマでもある結婚生活における役割に関する葛藤に関しても、いわゆる良妻賢母を 押しつけられ、その役割を果たそうとする無理から、子供が手を離れた後、結婚生活が破綻する可能性が示唆されている。本当は、その時々で押しつけられる社 会的(あるいは家庭的)役割に縛られるのではなく、自分の人生全体を見渡して、現在をライフサイクルのどんな時として位置づけるかという視点が必要なはず だ。そんな視点を持つことは、私たちがどのような社会に生き、どのような影響を受けてきたのかを自覚し、現在自分が生きようとしていることは自分の欲求に 適ったことなのか、あるいは誰かの利益を支えるために動かされているのか見極めることである。それには、情け容赦なく、自分の人生の責任を背負う重みが 伴っている。
女性についてのライフサイクルあるいは発達段階についてはほとんど論じられていないなか、ユング 派であるE・ノイマンが女性心理の発達段階を論じている。ユング派は、女性原理ということを強調することで、これまで無視され続けてきた人間のある側面に 光をあて、女性のことを考えるひとつの手掛かりを与えてくれたと言える。ノイマンは「心理的条件がどの程度社会的情勢に影響をおよぼし、また逆に集団的な 社会情勢がどの程度個人としての女性の心理に影響をおよぼすかは、本論ではさほど重要な問題ではない。」(ノイマン,1980,p.20)と頑なな態度を 保ちながらも、一方で、現在の社会的情勢における女性のありかたを見事に分析している。彼自身がその矛盾を意識していたのかどうかわからないが、とくに、 父権制結婚の形に含まれる精神状況について、次のように語っているのは興味深い。
結局、女性的なものにとって父権制が有する否定的な意味合いは、循環論法をなすのである。男性的 なものは女性的なものをまず力づくで、ただもう女性的であるほかない領分に限定し、同時にしかし、女性的なものが真の意味で父権文化に関与することを不可 能にし、女性的なものに二流の劣等者の役割を押しつける。しかし、女性的なものがこうして娘のような未成年者の役柄を脱することができないので、男性的な ものはその後見役を務めなければならない。そうすれば男性的なものは、女性的なものの価値を奪っておいてなお申し開きが立つのであり、女性的なものは、い わゆる生まれつきの劣等性に居直る口実ができるわけである。このような状況によって悲惨な影響を蒙るのは女児である。彼女はこの父権利的な価値体系のなか に生まれおち、自分自身の価値の無さを教えこまれる。女に生まれなかったことを日ごとに神に感謝するユダヤの男性の朝の祈りや、女性の「ペニス羨望」に基 づいて構築されたフロイトの女性心理学は、このような父権的状況を表す極端な例であり、父権的な文化的共生を強いられている女性的なものの危機的状況を物 語っている(ibid.,p.44)。
これを読み替えるならば、「父権制において、男はロゴスに同一化し、女は力づくでエロスに同一化 させられた。父権文化はロゴスに価値を置き、エロスに二流の劣等者の役割を押しつける。このような役割分担のために、女もエロスも危機的状況に置かれてい る」となる。さて、時代は変わったという時、まず、女たちがロゴスを発展させたために、エロスとのみ同一化させられる強制に反発しだした。それが、男性と 同一化しひたすらロゴスを追い求めた初期の女性解放運動にかかわった女性たちである。一方、女性をエロスと同一化することは受け入れ、そのかわりにエロス に二流の価値しか見出さないことに反発するグループも出てきた。彼女あるいは彼らは、エロスを崇拝し、女を理想化することになった。いずれにせよ、ノイマ ンが記述した状況から、事態は大きく変化し、物事をそう単純に考えることはできなくなった。ノイマンが女性心理の発達段階として記述したものも通用しなく なりつつある。
ノイマンの意図は、今日の文化危機を乗り越え、社会の健康を取り戻すために、女性原理の独自性を 発見しなければならないというものであった。しかし、女性原理と言われるものは、生身の女と直接結びつくものではなく、抽象概念としての「女性」、一般に 「女性的」性質として人々が考えているもの、つまり、意識、文化、分析、客観性など「男性的」性質と対立する無意識、自然、統合、主観性などと関係するも のである。しかし、これらの用語を借りて言うならば、人間の可能性を男性原理と女性原理の対立で考えること自体、男性原理的発想だと言うこともできる。女 を考える時、女性原理について考えることから出発すれば、出発の時点からすでに、男によって分析され、振り当てられたものから始めることになる。「女性原 理の独自性」を求めようとするならば、男性原理、女性原理という二分法をそもそも捨てなければならない。しかも、これだけ時代が変わり、私たちが全体性を 求めている現在、この古くなった性別役割を用いることはもはや時代錯誤と言うべきだろう。もちろん、今もなおエロスを女性特有のものと、ロゴスを男性特有 のものと信じる人々がいることは事実である。しかし、それを前提にしてさえ、女性をエロスにのみ限定するのではなく、女性も男性的側面を生きるように求め られている今(たとえば、学校生活では女性であってもロゴスがある程度評価される)、女性原理、男性原理に変わる言葉が求められていると言えよう。本稿で は、いささか乱暴ではあるが、とりあえず女性原理(「女らしさ」と考えられるものと同じではないが、かなりだぶっているものである)をエロス、男性原理 (同様に「男らしさ」とだぶる)をロゴスと言い換えてみた。エロスが女と、ロゴスが男と必ずしも結びつくわけではないことは、ギリシャ神話のエロスが男で あり、プシケー(ロゴスとだぶる)が女であったことを、思い起こしていただきたい。
この文化的危機を乗り越え、社会の健康を真に取り戻そうとするのなら、私たちが常に社会的連関のなかにあることを認め、社会を信頼することに始まり、社会に対する批判と働きかけなしにはあり得ない。
2.生命としてのライフサイクル ――いきいきとした感覚を求めて
お伽噺が結婚に終わりメデタシメデタシとなったり、「大きくなったら何になるの?」と問われて、 女の子が「お嫁さん」とか「お母さん」と答える時、その後の女性の人生は見えてこない。あるいは、「結婚は恋愛の墓場」と言われるように、結婚によって男 との関係が発展をやめる時、女男の関係の未来は見えてこない。人生そのものが生きたものであり、過去が現在に通じ、現在は未来へと開けていくという展望を 持てなければ、あるいは生命の流れが個人のなかに閉ざされることなく、自由に他の生命とつながれるのでなければ、人生は硬直化し、生命の流れは妨げられ る。このことは、数多くの弊害をもたらし、神経症や鬱病やあるいは精神病の原因となっているようにも見える。一方、あまり健康的とは言えないこの社会自体 が既に硬直化を示しており、個々の女性の欲求の変化についていけず、柔軟に対応していくと言うよりは、必死になって既に過去のものとなった社会的役割を押 しつけることにしがみつくことで、何とか現状維持している状態のように思われる。たとえば、全体性を求める女性たちは、結婚生活において、当然パートナー にも全体性を求めることになるが、なかなかここのところで潔く事が運ばない。現実的に男たちが女の犠牲の上に乗っかっているのがほとんどであるし、たと え、心ある男たちが全体性を求めようとしても、彼らに課されている社会的役割がまた道を阻むことになる。
ライフサイクルということを考える時、個体を超えた大きな存在、人間という種族全体の流れや生物 の発生、宇宙などといった超個人的なものとのつながりが暗示されると同時に、個々の生命の原理や欲求などとも切り離せないことはすでに見てきた。それは、 自分の生命の欲求を大切にすることが、ひいては大きな生命の流れを大切にすることに他ならないという生命への信頼を基盤としている。このような全体的なも のとのつながりは、ひとりの女性が自分の子供を産むということに限定されない。子供を産まずとも、私たちはこのようなつながりを感じることができる。
女性にとって、このようなつながりを感じさせられるのは、自分の体を司っているサイクルを意識する時であろう。月ごとのこのサイクルは、さまざまな体の 変化や気分の変化を生み出す。女性のさまざまな可能性をギリシャ神話の7人の女神に準えて語ったボーレンは、
この変化に敏感な女性たちは、サイクルの前半では自立している女神たち(特に外向的で世 の中に出ていくことを重視するアルテミスやアテーナー)により強くひかれていることに気がつく。そしてサイクルの後半になると、妊娠のホルモンである黄体 ホルモンが増加するため、「巣づくり」傾向がより強くなるように感じられ、家にいつもいたいという気持ちや誰かに甘えていたいという気持ちがより顕著にな ることに気がつく。デーメーテール、ヘーラー、ペルセポネーあるいはヘスティアーがもっとも強く影響を及ぼすことになるのである。(ボーレ ン,1991,p.46)。
と述べているが、自分の欲求や気分が周期的に変化していくことをおもしろく感じている女性も少な からずあることだろう。ホルモンの影響は絶対的なものでは決してないが、ホルモンがドラマティックに変わるとき(思春期、妊娠期間、および更年期)、女性 が大きな変化を経験する可能性は高い。このような時を過渡期と考えることができ、過渡期に危機はつきものである。このサイクルは、体内からくる力でありな がら、月の満ち欠けに代表されるような宇宙力ともつながっている。「月の神話と女性原理」の関連を論じたハーディングは、次のように言う。
女にとっては、生そのものが周期的なのである。生命力は、彼女の経験の中で、男の場合の ように、夜と昼のリズムで退いたり満ちたりするばかりでなく、新月、半月、満月、衰退期そして闇へとまわる月の周期でも退いたり満ちたりするのである。こ れら二つの変化が相まって月の変化のような、また大きな月々の周期が、日毎の変化といっしょになって作り上げる潮のようなリズムをつくる(ハーディン グ,1985,p.88)。
もっとも、ここでは、女性の体を司るこのようなサイクルを絶対視したり、ハーディングのように 「女性の神秘」を強調することは意図していない。女と男を同質のものだとは考えないものの、既に述べたように、「女性原理」という言葉自体に疑問を感じる からである。女性がこの力によってのみ動かされているわけではないし、このサイクルとの関わり方は各々の女性で違っている。男だってホルモンの影響を受け ているのだし、「神秘」と言えば、生命そのものが神秘なのであって、男も生命である以上、女性だけを神秘視するのは不自然である。
女性が、このサイクルを感じ取り、その移り変わりに身を委ねながらも、個人の人生全体を見通し、そこに現在を位置づけていくという視点がもてないものだ ろうか。このことは、通過儀礼(イニシエーション)とも関わってくる。ヘンダーソンは、次のように言っている。
なぜイニシエーションが必要なのであろうか。おそらく男性はそれを知りながら、それを体験することができず、一方女性はそれを体験しながら、それを知ら ないからであろう。したがって、各人が体験することができると同時に、その体験をはっきり意識することができるような能力を獲得するようにならなければな らない(ヘンダーソン,1974,p.264)。
たしかに、これまで女性は自分の体験の意味を把握し、人生全体を見渡すことに躓いてきた。それ は、その方が現在の社会にとって都合が良かったからでもあるが、たとえば、仕事にいきがいを見出しキャリアを積みながらも、他方で良き母となる(良き母と は、仕事より子育てを優先するものである)未来を思い描く若い女性は、そこに分裂した自分があることに気づかない。子供を育てる葛藤は子供を持つまで想像 できないし、健康に暮らしている者が病気を忘れているように、更年期の動揺や、その後の老いは、若い女性にとって他人事であり、ギリギリまで目を背けてい たいものである。しかし、その場限りの生き方は、しばしば自分の欲求すら感じられなくし、社会や文化の硬直化した要請に振り回される危険を孕んでいる。
これは、世代間の葛藤をも引きおこす。つまり、自分の人生を見通すことなく「かくあるべし」とい うところから人生を生きる女性にとって、「女の道」は、踏み外してはならない絶対的な道であり、そこには躍動する行きつ戻りつはなく、年齢を重ねた者ほど 人生の先を行く者として立てられなければならないという倫理観を生むことになる。自分自身が自分の生命の原理を信じることのできる人は、他者の生命の原理 を信じることができるし、年令や経験を積むことが重要なことというわけではなく、すべては可能性として元からあって、私たちはそこを回っているのだという ことが前提となれば、年配の者に対しても、年下の者に対しても、等しく敬意を払うことができるはずである。子供を未熟な大人と見る者は、硬直化した縦の直 線の上に人々を上下に位置づけて並べるのに対して、子供を独立した一個の存在として認めることのできる者は、自ら子供になったり老人になったりするイマジ ネーションを駆使し、時間的長さとは関係なく、のびやかな人生を送ることができるはずである。
(4)おわりに――FLC研究所の抱負にかえて
すでに述べてきたように、私たちは、女性が既成の概念に縛られず、自由にいきいきと生きられるこ とを望んでいる。ライフサイクルという言葉を使うことで、特定の問題にこだわらず、さまざまな側面に対応できることを狙ったつもりである。非常に漠然とし ており、アピールに乏しいことは事実であるが、自分たちを限定せず、その時々の欲求や必要性に応じて柔軟に姿を変えていける生命体のようであればと考えて いる。ライフサイクルが個人のものにとどまらず、家族のライフサイクルや社会のライフサイクルにまで拡張できるように、FLC研究所自体もライフサイクル をもつことになるだろう。今は、私たちにとって曙であり、今後の全体を思い描くには、まだまだ時期尚早のようである。ということから、本稿を「女性のライ フサイクルについての試論」としたが、もともと、エリクソンやレビンソンのように、発達段階を論じるつもりはなかった。結婚するとか子供を産むとかいった ことが、女性のライフサイクルに大きな影響を与える一方、結婚や子供を選ばなかった女性たちには、また違ったライフサイクルが考えられるし、思春期や更年 期にホルモンによる大きな影響を受ける女性もいれば、そうでもない女性もある。結局のところ、重要なのは、各々が自分の人生を全体との関係のなかでとらえ ていき、しかも、個人を超えた力や他者とつながりながら、自分の人生を生きていくということである。既に述べたように、女性に期待される社会的役割が女性 の生命力を枯渇させる方向にある今、社会への働きかけなしに女性の自己実現あるいは個性化はあり得ない。FLC研究所は伸び伸びと自由に自分の人生を生 き、自分とは違った他者をも受け入れ、社会全体がもっといきいきと活気づくことを願う女性たちのホームでありたいと考えている。
文献
J・S・ボーレン(1991),『女はみんな女神』(村本詔司・邦子訳)新水社.
Erikson, E. H.(1968),Identity, Youth and Crisis. New York:W.W.Norton & Company.
M・E・ハーディング(1985),『女性の神秘』(樋口・武田訳)創元社.
細木照敏(1983),「青年期心性と自我同一性」『岩波講座 精神の科学6 ライフサイクル』岩波書店.
C・G・ユング(1979),「人生の転換期」(鎌田輝男訳),『現代思想臨時増刊 総特集=ユング』青土社.
河合隼雄(1983),「概説」『岩波講座 精神の科学6 ライフサイクル』岩波書店.
河野貴代美(1985),『女性のための自己発見学』学陽書房.
桑原知子(1990),「青年期の女性の自己同一性」『現代青年心理学-男の立場と女の状況』(氏原・東山・岡田編)培風館.
Levinson, D.(1977),The Seasons of a Man's Life. New York:The William Alanson White Psychiatric Foundation.
E・ノイマン(1980),「女性心理の発達段階」『女性の深層』(松代・鎌田訳)紀伊国屋書店.
山下景子(1990),「おんなのわかれ道」『現代青年心理学-男の立場と女の状況』(氏原・東山・岡田編)培風館.