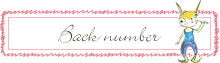- 1994.11.23 年報『女性ライフサイクル研究』
- 表現と「力」
女性ライフサイクル研究所 村本邦子
この年報も4号となり、研究所を開設してまる4年、5年目に入った。何かできたらというささやかな想いで出発したが、ふと気がつくと、活動範囲は 着実に拡がり、方向性もはっきりしてきたように思う。経済的な基盤、日常の運営については、悩みが尽きないけれども、社会に対して発言したり、自分たちの 思いを表現したりする機会は確実に増えた。こうして書いたものが印刷されてばらまかれ、講演や講義などの形で不特定多数の人々に向かって話をする機会を持 つようになると、そこで表現されたものは、私たちが個人レベルで考えたり感じたりするものを越えていくことになる。ある意味で、それは「力」を持つことだ と言えるだろう。
この「力」は、私にとって脅威である。昔から不特定多数の人と話すのは苦手だった。一対一の関係では、すれ違いや誤解があっても、ある程度までなら取り 返しがつくし、自分の失敗を償うこともできる。もちろん、決して償うことのできない過ちもあるが、それを極力避けるように努力することは少なくとも可能で ある。ところが不特定多数との関係は一方通行で、自分の表現したものがどのような形で相手に届いたのかを確認しようがない。受け手がそれを「よいもの」と して受け取ってくれれば、あるいは何ら影響を及ぼさないものとして受け取ってくれればまだよいが、それによって誰かが傷ついたり、自分が貶められたように 感じたり、何か悪いことのために利用されることだってあるかもしれない。仮にそれを確認できたとて、それらすべて責任を負えるかと言うと、たぶん不可能だ ろう。誰かとの関係で非対称な「力」、一方的な「力」、責任を担いきれない「力」を持たされることは、だから私には恐怖である。
でも、この「力」に喜びが伴うことがある。それは、たとえば、私の知らないところで誰かが私の表現を受け取り、それを育ててくれたことを知った時。こち らでは誰であるかよくわからないような人が、「あの話を聞いて、あの文章を読んで、とっても心に響くものがあって、私はこんなことをやるようになったんで す」なんて言ってくれると、嬉しくなって胸が躍る。自分の思いを誰かが受けとめてくれて、まったく思いもよらない形で展開してくれるとすれば、自分の思い が自分から離れて新しい生命を持ったことになる。また、たとえば私たちは2年ほど前から、性虐待の防止教育に取り組んできたが、これもさまざまな形であち こちに拡がった。規模としてはもちろん微々たるものではあるが、それでも、自分たちが全国の家を一件一件訪ねて回って話をすることなどできないのに、こん なふうに拡がりを持つという形で、虐待防止について意識を持つ人が一人でも増え、子どもたちが一人でも救われるとすれば、それもやっぱり嬉しい。
それでも、やっぱり「力」を持つ者がちやほやされる文化の中にあって、「力」を持つことは恐怖だ。「力」を持つと、その周りに虚構が多くなって、「本当 のこと」が見えなくなったり、「大切なもの」を失ったりしやすい。「力」がその人から離れて存在するようになると、人々がその「人」にではなく「力」に群 がってくるようになるからだ。そうすると、その人は否応なく、個人として存在するよりも、「力」の象徴として存在させられるようになる。虚構が大きくなれ ばなるほど、つまり「力」と「人」のズレが大きくなればなるほど、「力」の責任は個人で担いきれないものとなる。「力」を持たされた者が、そのズレに気づ き、それを修正していくことができるのかどうか、私は懐疑的である。それは、とても不幸な事態だと思う。
そんなことを考えていた頃、マスコミやミニコミで「差別と表現」がテーマになっているのが目に入るようになった。正直、ギクッとした。私はどちらかと言 えば個人主義的に生きてきたので、自分の目の前に差別が見えたら異議申し立てしてきたつもりだが、意識的に学んでいかなければ個人的には知りえない歴史 的、社会的差別には疎かった。遅ればせながら少しずつ勉強するようになったが、まだまだ勉強不足で、そのことにある種の劣等感、罪悪感を持っている。意図 的な差別はもちろん論外だが、こういう文脈にあっては、意図せぬ差別を自分が行う可能性が生じてくる。つまり、個人レベルでは責任のない出来事に対して、 歴史的、社会的存在として自分が投げ込まれたところにたまたまあった責任を担わせられるのである。この「たまたま」投げ込まれたところに差別や抑圧でな く、責任があるというのは、マジョリティであったことを意味している。ここでも、また「力」の問題がつきまとう。マジョリティであることは、意図せぬ 「力」を持たされることである。
差別と抑圧の構造の変数は数限りなくあるから、人は状況に応じてマジョリティであったりマイノリティであったりするが、その総計から差別構造のどのへん に自分がいるかというアイデンティティが規定される。つまり、自分が社会的弱者であるとか、強者であるとかいった認識が生まれてくる。ところがこの変数に 無自覚でいると、弱者のアイデンティティを持つ者がある時ふと強者の側に回ったり、その逆のことが生じても、それに気づかないということもあるのだ。たと えば、子育てにおいて。子どもを育てるということは、否応なく親として、大人としての「力」を持たされることだ。この事実を認識できない時、虐待が起こ る。虐待が起こる時、ふつう虐待者は被害者意識を抱えており、(それが可能になった時)その埋め合わせに、「力」を行使して衝動的な他者のコントロールを 行い、ひとときの「力」の幻想に酔う。だから、強い抑圧を受け続けてきた者が、状況の変化によっては自分も強者になり得るのだと認識できない時、今度は抑 圧する側に回ることもある。
こうして「力」のピラミッド構造ができあがる。誰もが多かれ少なかれ、自分より下にいる誰かを踏み台にしているわけだ。この「力」に基づく社会にあって は、ほとんどの場合、人は誰かから抑圧され、同時に誰かを抑圧している。もちろん、だからと言って、その罪が帳消しにされるわけではなかろう。ピラミッド の上層部にいればいるほど、意図せずとも踏みにじっている人々の数は増え、それだけ罪深くもなる。自分の投げ込まれたところにすでにある差別や抑圧、もし くは「力」と責任は、どちらも宿命であるが、その決定的な違いは、前者は選択の余地なく背負わされるのに対して、後者は、それを背負うか否かは自由意志に よる選択が可能であることだ。
本当の自由は、自分の宿命の無自覚と無関心のなかにはないだろう。逆に、自分の投げ込まれたところにつきまとう宿命の自覚と、そこから解き放たれようと する意志のなかにあるのだと思う。だが、ここでまたしても「力」の問題が足をひっぱる。意志や選択や自由は、「力」を前提にしているからだ。結局のとこ ろ、自由は、自分に対する責任は言わずもがな、他者に対する責任をも内包していることになる。
このようなところから、本特集を企画することになった。第一章では「表現と自由」一般について論じる。私自身、「表現の自由」という表現は、今や強者の 逃げ口上としてのみ使われるので、あまりに白々しく感じているからこの表現を避けた。「表現の自由」が切迫感を持って響くとすれば、それは非常に危険な状 況であることを意味するだろう。本来、「表現の自由」という言葉は、社会的弱者のためのものだ。目次を見ればお気づきのように、この章の書き手は、当研究 所に関わる者のパートナーである。3組のカップル(越智、西、村本)だが、このメンバーでは、大概は女性陣と男性陣に分かれることになって、何度か議論を した。
一番難航したテーマは、西晃氏が「抗議する側の倫理」を強調しようとするように私たちには見えたことだった。それは、もちろん大事なことだけれども、そ れを言う以前に抗議を受ける側の倫理を考えるべきだと私は思っている。そのやり取りの中で、図らずも、抗議する側の困難さを体験することになった。私自身 は、いつも編集にあたって、書き手に書いて欲しいことが明確にあるわけではない。自分なりの筋書きはある程度あって出発するにしても、さまざまな書き手 が、期待されたテーマをきっかけに、編者の意図を超えて、新たな表現を展開してくれることを切望しているし、それが喜びでやってきた。だから、一定の結論 に向けて、書き手を力づくでねじ伏せようとは毛頭思っていない。ただ、初めに述べたように、印刷物を出すという意味では、不特定多数の受け手に対して、で きる限り責任を負えるような編集をするよう努力したいとは思っている。ところが、議論を吹っ掛けられる男性陣は、そういったこちらの思いを、「検閲」のよ うに受け取るようだった。
そもそも編集者としての私には、客観的に言ってたいした「力」はない。財政的にはいつも苦境に立たされているし、世間からは「わけのわからないことを やっているうさんくさいところ」と見られたり、無視されることもしばしばである。ましてや、原稿料が払えるわけでなく、執筆者に対して、どのような「力」 が行使できるのか。そんな中で、西晃氏からおもしろい発言が飛び出した。「僕は、自分より村本さんの方が強者だと思っている。僕なんか吹けば飛ぶような存 在だ。」と言うのだ。私自身を含めて一同、妙に納得したのは事実だが、そこで言われているのは、非常に内面的な(主観的な)「力」だろう。仮に、多額のお 金が必要になったとして、弁護士である彼にはお金を貸してくれる所があるだろうが、私に貸そうというところはまずないだろう。女であり、大きな組織に所属 しているわけでもない私には、哀しいかな、夫の後ろ盾がなければ部屋を借りることすら不可能だったし、クレジット・カードをつくってもらうこともできな かった。社会的信頼、地位といったことでは彼の方が強者であることは間違いない。
一方で、内面的な「力」、自己主張の強さとか、自尊心とか、議論する力などについて言えば、確かに私の方が強者になるのだろう。私自身は誰かを「力」で ねじ伏せようと意図していなくても、相手が自分自身の内面的な「力」を評価できない時、黙ってしまう、主張せずに従ってしまうという形で、結果的に相手が 抑圧されるということがあったと思う。このような状況では、そもそも対等な議論自体が不可能だろう。初めに述べた「力」に対する恐怖は、私のこういった過 去の苦い体験の積み重ねを引きずったものかもしれない。自己主張しないように奨励されている文化にあって、主張することは、ましてや女として主張すること は、非常にネガティブな結果を引き起こすから。
「力」にはたくさんの次元が交錯している。客観的に言って、社会的「力」を持つ者がその「力」を認識しない時、意図せぬ抑圧が起こる。たとえば若い頃に は批判精神旺盛で権力に反発し続けてきた者が徐々に評価され、社会的「力」を持たされているのに、それに気づかず、相変わらず自分は一匹狼だ、マイノリ ティだとしか認識できない時。筒井康隆の一件では、彼が自分を「ブラック・ユーモアの作家」と認識しながら、その作品が教科書に載るというギャップなど は、こういう例だろう(彼が差別表現をしたか否かということよりも、その後の姿勢を指す)。
越智裕輝氏は、表現者の問題とくに社会的「力」を持つ者として、専門家や知識人、文化人と称される人々の倫理的責任について論じるとともに、受け手の問 題についても言及する。つまり、差別とは個性が分化した差異の自覚のないところに生じる全体主義であり、ファシズムや戦争といった事態を避けることができ るためには、表現する者とその受け手の双方の成熟を必要とすると言えるだろう。
西晃氏は、最終的には、できる限り中立的な立場で、表現と抗議に関して法的にはどう理解されているかをわかりやすく説いてくれた。「国家・社会的利益」 という考え方は、ふだん法的なことから遠い私たちには馴染まない概念であるが、「福祉」と置き換えるとわかりやすい。法的な思考様式や手続きを知ること は、弱者の戦略として有効だが、マッキノンが指摘するように、法の上の「人」が何を指すか、「福祉」が誰のものか問いなおすことから始めねばなるまい (K.A.マッキノン『フェミニズムと表現の自由』、明石書店、1993)。
「抗議」については、若干の補足を加えたい。自分たちの議論で感じたのは、抗議する側、される側の心理をもっともっと細かく分析する必要があるというこ とだ。それは「抗議する側の倫理」としてではなく、むしろ「抗議する側の戦略」として役立つだろう。たとえば、自分自身、抗議や糾弾を受けるかもしれない 側に立つことをイメージすれば、それに対してネガティブな感情が沸いてくる気持ちもわからなくはない。それは、たとえば、これまで疑いもしなかった価値観 を崩される恐怖(これは強者の論理から言えば、非合理的と思われる論理を押しつけられる恐怖として体験されるだろう)、自分が成してきた様々な表現のう ち、たったひとつの表現でもって自分が置き換えられ、それ以外の自分(個性)は無視されてしまう、極端に言えば、抵抗の余地なく圧倒的な力に抹殺される感 じ(本当はこれらこそ、強者が弱者に押しつけてきたものだったが)などなど。自分の「力」に対する責任を無視して生きていればそれだけ、これらの恐怖は妄 想のように大きく膨れ上がる。
逆に、抗議や糾弾を行う側に立つならば、問題となった表現に対する修正を求めると同時に、そんな表現が生まれてきた土壌を問い質し、考え直して欲しい、 わかって欲しいという気持ち(これは人として当然の感情であろう)、それに対して抗議や糾弾を受けた側、が上述したような恐怖から、頑なにそれを拒否しよ う、あるいはそれから逃げたり誤魔化そうとするならば、だんだんとその感情は怒りに変わり、攻撃的行動にもなるだろう。さらに極端には、ひとつの差別表現 を成した特定の個人が、差別全体のスケープゴートになるかもしれない。
抗議される側の恐怖については、「Y氏のセクハラ事件」に関する一連の流れを私なりに見てきた中でも痛感したことだった。身近な人が、その流れをよく知 らないまま、たとえば大越愛子氏らが東福寺に意義申し立てしたことを指して「あれは集団リンチだ」「ヒステリックなこわい女のいじめ」などと言っているの を聞くと、抗議行動が起こった時に、人々がどんな反応をするかよくわかる。私自身は、この事件と直接何の利害関係もないが、新聞報道を注意深く追っていく と、どちらが感情的に支離滅裂な行動をとり、どちらがあくまでも冷静に論理的に行動してきたかがよくわかるし、大越愛子氏がこれまで思想的に深めてきたこ とを、現実につなげて速やかに行動したことなど、研究者としての誠実さだと高く評価してきた。やはり、抗議する側の倫理よりも、受け手の倫理が問題なのだ と痛感する。たとえば、部落解放同盟の糾弾に関しても、発言しているリーダーたちの言っていることは、まったく筋がとおっている(たとえば、山中多美男 『ここが大切!人権啓発』解放出版社、1992)。
これらの思い込みやすれ違いをどうやったら解きほぐしていくことができるのか、「筋がとおっている」だけでは太刀打ちできない現状をどう変えていけるか、戦略としても今後もっと考えていければと思っている。
第二章は、「抑圧と表現」とした。正確には、被抑圧者の表現を取り上げたかった。とくに、子どもと女性の問題を取り上げた(子どもに書いてもらったわけ ではないので、大人の立場から、子どもを代弁することになった)。長年、吃音者のセルフ・ヘルプ・グループのリーダーシップをとってきた伊藤伸二氏や、子 どもの心理治療に関わってきた市川緑氏の描写から、抑圧を受ける子どもやその親たちの姿が浮かび上がってくる。抑圧されてきた者が新たな抑圧を生まないた めにも、子どもを取り巻く大人たち、とくに親や教師たちにとって、抑圧からの回復と解放は課題になる。子どもを取り巻く学校や教師の問題についてと、女性 の怒りの表現については、当研究所の前村よう子と西順子が、それぞれ自分の体験を交えて論じた自己表現と自己肯定によるエンパワメントが必要ということに なろうが、精神科医である越智友子氏から「主体を損なわれた者に表現は可能か」という根源的な問題が提示されることになる。一章で村本詔司氏が論じたよう に、そもそも「表現」は、すでに個の確立を前提にした概念だから、主体と客体、あるいは内界と外界という二元論に基づく限り、抑圧によって主体を損なわれ た者にとって、そもそも表現すること自体が不可能になる。行き着く先はまだ漠然としているが、「表現」の概念自体を解体し、二元論を超えていくところから 新たなシステムが生まれてくるのかもしれない。
第三章は「創作と表現」である。主体があって客体としての表現作品が生まれるという二元論を越えていくためには、主体と客体を切り離して論じることがで きない創造領域について考えてみたいと思った。イラストレーターのY・Aさん、サックスのMASA、劇団『青い鳥』の芹川藍さん、墨絵のおぎようこさんと いったさまざまな表現活動をしている女性たちの姿を紹介することで、創作とその人との深い結びつき(主客の一致)を感じてもらえればと思う。「言葉」の問 題も取り上げてみたいと思ったが、「言葉」による表現につきまとう一致と不一致をとくに「詩」の形で、原祥雄氏と白川比呂樹氏が論じてくれた。原氏は現在 は編集に関わる仕事をされているが、これまでもミニコミ誌の編集や自ら詩、小説を発表されているし、白川氏も詩人として創作活動をしてきた人である。
第四章は「セクシュアリティにおける表現と自由」とした。表現のことを考える時に欠かせないテーマであると思ったからだ。とくに性の領域においては、女 性はいつも表現の対象であり、主体を持たされずにきた。この喪失を取り返すのは非常に困難である。どうやら、単純にこれまでのパターンを裏返して、女が主 体となりかわれば解決するわけでもなさそうである。それでは一体どうしていけるのか、モデルがないだけに私たちは途方にくれている。この章では、とくに女 性の性に関する誠実かつ気鋭の発言と活動をなさってきたお二人、敦賀美奈子さんと、中野冬美さんの原稿に加えて、座談会を盛り込んだ。一人一人違ったセク シュアリティのあり方を大事にしたいと思ったからである。座談会参加者にとっては、女だけで思う存分セクシュアリティについて語り合う貴重な場だったが、 その場で分かち持たれたことを十分に文字にできたとは残念ながら思えない。セクシュアリティに関して表現する、しかも言葉を使って表現するというのは困難 なことだ。それでも、女が女のためにセクシュアリティについて発言するという試みはまだ始まったばかりだから、多少、無様でもいいじゃないかと思ってい る。他の章の原稿と並べて、それができたことを嬉しく思っている。
難しいテーマだったが、全体的に奥行きのある質の高い議論ができたのではないかと自負している。いろいろな点で編集は難航したが、編集者としては、結果 として十分に報われた気分である。一緒に最後まで辛抱強くこのテーマに取り組んでくださった執筆者たちに、この場を借りて心から感謝したい。また、名前を 挙げることはできなかったが、座談会に出席してくださった皆さん、快くインタビューに応じてくださった皆さん、「私と表現」に手記を寄せてくださった皆さ んにも感謝したいと思う。これは、当研究所と関わりの深い人たちに「ネットワークから」という形で原稿を寄せてもらったものだが、ひとつの章にまとめるよ りもコラムとして全体に散らす方がよいのではないかと思って、今号はこのような形にしてみた。それぞれの立場から読み応えのある充実した原稿を寄せて頂け て喜んでいる。それからいつも表紙や題字、イラストをデザインしてくれる村本順子さん(私の義姉である)、レイアウトに力を貸してくれた原祥雄さん、いつ もお世話になっている地水社さんにもお礼を言いたいと思う。こうしてボランティアで快く原稿を書いてくださったり、サポートしてくださる方々に支えられて ここまでやってこれたこと、また雑誌やニュースレターを講読して声援をおくってくださるみなさん、さまざまな形で私たちと関わってくださっている皆さんに も、スタッフ一同いつも感謝している。
内容については、同時に、やはり、まだまだ不十分であることも痛感している。とくに
マイノリティの問題についての議論が十分にできなかったこと、「ポルノとセクシュアリティ」に関してもっと掘り下げて考えていけたらと思うが、今のところ力不足を感じている。先送りの課題としたい。ご批判や感想などいただけたら有り難い。


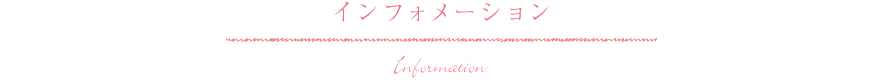
 昨今、犯罪報道をめぐって、表現の「自由」を優先するか、それとも「人権」を優先するかが人々の関心を集めています。何によらず誰かの手によって表現され たことは、その個人を越えて力を持つこととなります。すると、意図するしないにかかわらず、その力は誰かの脅威となり得るのです。本書では、このような力 を持つ「表現」を、様々な角度から再検討しています。例えば、抑圧されている立場の子どもや女性にとって「表現」がどのような意味を持つのか、また、何か を生み出すことと「表現」との関係やセクシャリティの問題などにも言及しています。自分にとっての「表現と自由」について再考するためにも、本書をお薦め します。
昨今、犯罪報道をめぐって、表現の「自由」を優先するか、それとも「人権」を優先するかが人々の関心を集めています。何によらず誰かの手によって表現され たことは、その個人を越えて力を持つこととなります。すると、意図するしないにかかわらず、その力は誰かの脅威となり得るのです。本書では、このような力 を持つ「表現」を、様々な角度から再検討しています。例えば、抑圧されている立場の子どもや女性にとって「表現」がどのような意味を持つのか、また、何か を生み出すことと「表現」との関係やセクシャリティの問題などにも言及しています。自分にとっての「表現と自由」について再考するためにも、本書をお薦め します。