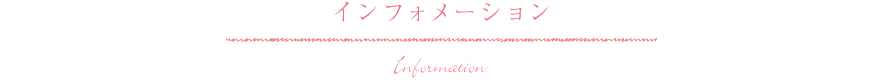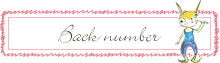- 2004.10.25 活動報告-論文/執筆/学会活動等
- 家族機能の変化と家族援助(2004年)
月刊『子ども未来』7月号 掲載
村本邦子
家族と子育ての変遷
家族は、そこで人が生まれ、成長し、働き、老い、死んでいく共同体であり、社会の基礎的な単位をなします。当然ながら、これは、時代や文化によって変化していきます。産業革命は労働と生活の場を分離し、戦後、民法改正による家制度の解体、高度経済成長に伴う都市化はこれに拍車をかけ、大量の核家族が産み出されました。こうしてできた近代家族は、人々を親族や家のしがらみから解放し、個人主義に基づく家族構成を可能にしました。つまり、愛情によって結ばれた夫婦のもとに子どもが生まれ、父親は経済的責任を果たし、母親は家事・育児の責任を果たすという新しい形です。結果的に、性別役割分業が進み、いわゆる母性神話が強化されることになりました。極端に言えば、子育てが母親による専売特許となり、子どもの私有化が進むことになったのです。
かつて、子どもは、家族にとって、貴重な労働源でした。「きんさん・ぎんさん」として話題になった1892年(明治25年)生まれの双子姉妹の回想によれば、「5つ、6つの頃から畑仕事、谷の井戸まで水汲み、夜なべで糸紡ぎ、眠うて手が休みよるでよう怒られた」そうです。次々生まれた妹弟の世話もあり、小学校入学は9歳時、学校は一日交替でした。母親は機織り、姉妹は糸繰りで一日働き詰め。きんさんは19歳、ぎんさんは22歳で結婚、「祝言をあげるまで、旦那さんになる人の顔なんか見たこともなかった」し、「出戻りなんかしたらもう生きとれんかった」と言います。きんさんは11人子どもを産みましたが、「栄養がようないから乳もでんかった」ので、5人が1年以内に死に、ぎんさんは5人中1人を亡くしています(総合女性史研究会編、1993)。
ここに、わずか1世紀のあいだに、家族と子育てがどんなに大きく変化してきたかを垣間見ることができます。人々は生きるのに精一杯で、子どもが生まれ、あるいは死に、育つことは、家族の生活の些細な日常の1コマにすぎず、取り立てて、「子育て」などという発想は持たなかったのでしょう。ぎんさんをして、今は白い米が食べられ「毎日が正月」と言わしめたように、日本社会は戦後50年で急激に豊かになりましたが、その豊かな社会が産んだ弊害も大きかったのです。
現在の家族と子育て
核家族化と少子化は、「子育て」を一大事業にし、子どもを一種の「製品」にしてしまった感があります。子育ての責任を一身に担う母親は、そこに多大なエネルギーを注がざるを得ないゆえに、自分の子育ての評価や確かさを求めるべく、「製品」としての子どもの評価を必要としました。自らもそこで育った知育偏重の社会のなかで、子どもの評価もそこで測られがちです。知育偏重の子育ては子どもたちから現実体験を奪い、情緒面での成熟を阻止し、そうやって育った世代がすでに親になっています。
核家族で育った親たちは子育てを体験していません。「新生児を抱いたのは我が子が初めて」という母親が子育ての第一責任者となるのですから、母親たちの不安と無知にも無理からぬものがあります。マニュアルと明確に測れる評価基準とする親世代にとって、「製品」になりきれない生身の子どもは、扱いのわからないやっかいなものと映るでしょう。また、良くも悪くも「主体性」に目覚めた現代人にとって、滅私奉公を要求される子育てに無理が生じ、それをうまくやりこなそうと必死になればなるほど、その内実は歪んだものになっていくでしょう。人間関係も希薄であることから、子育ての助け合いの実践も、自分たちでは難しいものです。
このような状況のなかで、家族は、そこで人が生まれ、成長し、働き、老い、死んでいく共同体としての機能を失いつつあります。経験のない親が隔離された実験室のような空間で子どもを育てていくということ自体が無理です。高齢化社会の問題もこれに加わります。1990年代、少子化と虐待問題がクローズアップされ、エンゼルプラン、新エンゼルプランが続けて発表され、行政が子育て支援に力を入れ始めたのも当然の流れでしょう。家族が家族として機能するために、社会が子育てをバックアップする時代が来たのです。
これからの家族援助
子どもの権利条約によれば、子どもは、親に養育される権利をもち、親は子どもの養育と発達に対する第1次的な責任を負い、国は、親がその責任を遂行できるよう援助すべき責務があります。私たちが望んでいるのは、子育てを国が代替することではなく、各家族がより良い子育てを実践できるようなお膳立てをすることです。そのために、さまざまな取り組みが始まっています。多様な保育サービスの推進、子育て生活に配慮した働き方の改革、児童虐待防止対策、母子保健対策、母子家庭等の自立への支援など、まさに必要な援助と言えるでしょう。筆者は1990年よりずっと子育て支援に取り組んできましたが、これらハード面の変革による進歩をひしひしと感じています。
他方、ソフト面での進歩を感じにくいのも事実です。子どもたちの生活体験の乏しさ、知育偏重の価値観、情緒面での未熟さ、すでに否定されたはずの母性神話は、相も変わらず生きています。ひとりひとりを大切にしながらも、関係性のなかで人が育ち、育てていくという人々の意識変革が求められていると感じます。これからの家族援助は、つながりをキーワードに、いかに人の心に働きかけていけるかが課題になっていくことでしょう。この時代の親子にフィットする形で援助を提供できる援助者の育成が必要です。閉ざされた家族から子育てを解放すると同時に、私たちひとりひとりが、地域のあちこちで眼にする子どもと親に関心を持ち、血縁を越えたつながりで見守っていく覚悟も必要でしょう。
総合女性史研究会編(1993)『日本女性の歴史~女のはたらき』角川選書