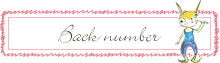- 1998.11.23 年報『女性ライフサイクル研究』
- 今、子どもたちの心と社会は
女性ライフサイクル研究所 村本邦子
「ムカつく」「キレる」などという言い回しが新聞紙面に登場し、理解不可解な今の子どもたちを形容する枕詞にさえなったようだ。しかし、「今時の 子どもたちは......」という言い回しは、非難のニュアンスとともに、いつの時代にもあった。いつの時代でも、子どもたちの心が見えないのは、それを見ようと しないからだし、子どもたちの声が聴こえないのは、それを聴こうとしないからではないだろうか。
私は60年代を子どもとして過ごし、70年代に思春期を迎え、大学時代は家庭教師として子どもたちと関わった(週8軒回ったりしていたから、6年間の学 生生活で30人以上の子どもたちと関わった)。その後は、思春期外来で子どもたちと会い、子どもを産んで、我が子や周囲の子どもたちともつながっている。 とにかく、途切れることなく、つねに子どもたちと接点があったが、いつの時代も子どもは一緒というのが、私の実感である。たしかに、時代の変化とともに、 表に見える子どもたちの姿は大きく変化したが、子どもたちが感じること、考えることは、私たちの時代と、それほど大きく隔たっているようには思わない。
本特集は、見えにくい子どもたちの心を見ようとし、聴き取りにくい子どもたちの声を聴こうとする試みである。「今時の子どもたちはわからない」という言葉が、子どもたちを理解することへの拒否でなく、わかりたい、わかろうとする謙虚さへの出発になることを願っている。
章外だが、トップ・バッターは、アフリカから徳永瑞子さんである。徳永さんのことはご存知の読者も多いだろうが、NGO「アフリカ友の会」の代表として 中央アフリカ共和国に滞在し、エイズ患者の支援活動をしている助産婦/看護婦さんである。今回は、おもに彼女の3人の子どもたちのことが書かれてあるが、 場所が変わっても、やはり子どもは子ども、世界中一緒であることを、まず知ってもらえたらと思う。診療所を駆け回って仕事の補助をするというポールくんに 社会性がないなどとは思えないが、将来のために教育をと願う徳永さんの親心、それを解せず我が道をいく思春期の子の関係は、日本の親子とそっくり同じじゃ ないかとほほえましかった。一方で、アフリカの子どもたちのおかれている状況の厳しさは、想像を絶するものがある。世界の政治経済を私たち個人が今すぐど うにかすることはできないけれども、通信や交通の発達に伴ってアフリカが決して遠い国でなくなった今、私たちはせめて世界で起こっていることに関心を持ち 続けたいものだ。
さて、第一章は日本の教育への疑問から始まる。服部さんの義務教育カルト論は、初めての方にはいささかショッキングかもしれないが、けっして、読者の皆 さんを混乱させようと意図しているわけではない。子どもの問題が言われだして久しく、さまざまな対策が取られながら、いっこうに変化の兆しが見られないの は、そもそも、学校が建てられている土壌に目を向けてこなかったからだと考えれば、得心するからだ。この章の書き手たちのように、学校内部で真摯に頑張っ ている先生やスクールカウンセラーがいることは重々承知しているが、彼らが子どもの心に寄り添おうとすればするほど、さまざまな矛盾や葛藤に苦しむことに なるというのが現状のように思う。「どうか自分を責めないで。学校だけに囚われず、学校の外の世界とつながることが力になる」と伝えたし、のである。こう いった新しい流れのなかで、周囲の大人たちに支えられながら、国連でプレゼンテーションを行った桂高校の荒井さんたちの答辞は生まれてきたのだと思う。こ こに、本当の教育とは何かを考えるさいのヒントが隠されているのではないだろうか。
第二章は、日々子どもたちの声に耳を傾けているカウンセラーたちの見た子どもたちの姿であり、子どもたちの声の代弁でもある。これらを読めば、一般には 理解しにくい子どもたちの心身症、不登校、キレる、ダべる、引きこもり、性の悩みなどの現象の意味がよく見えてくるのではないだろうか。「今時の子はわか らない」という大人のぼやきは、子どもたちには、拒否と見捨てられを意味しかねない。子どもは、いや大人だって、他者から自分の生に意味を感じてもらうこ とを求めているはずだ。誰かから関心を注いでもらうこと、自分の言葉(時には言葉なき言葉)に耳を傾けてもらうこと、そして理解されることがなければ、私 たちは生きていくことはできないのである。
ただし、ここで私の立場からは、植田先生の「哺乳類の母」と「父親の役割」への反論だけはしておかねばと思う(植田先生、ごめんなさい!)。子育てが一 人より二人で行われる方が負担は少なく、その場合、伝統的な母役割と父役割が二人の間で役割分担される方が効率はよいのだろうし、その役割を、そのまま産 みの母と父が担うということは実際、数として少なくないかもしれない。それでも、これを生物学的なものと前提してしまうことの弊害を私は嫌というほど見て きた。詳しくは拙著(『しあわせ家族という嘘』創元社)で論じたが、母性が必ずしも「母親の体内から、自然に湧き出て」くるとは限らないし、これらの前提 に従わない親たちの罪悪感を煽る。「こういう議論を聞くたびに、どうせ自分はだめなんだ、実の両親に育てられてないんだから、と少々すねた気持ちになるん ですよ」とおっしゃった方もあった。「子どもはそれぞれ違う」を延長すれば、「大人だってそれぞれ違う」に行き着くはずだ。
第三章は、子育てを親の責任に還元していくよりは、社会に開き、コミュニティが親子支援をしていく方向性への提案である。岩堂先生のおっしゃるように、 地域共同体が崩壊し、育児において母親の責任が強調されすぎたことからくる歪みを修正するうえで、今後、コミュニティに開かれた子育ては不可欠である。 「学校カルト論」と同じく「家庭カルト論」もあり得るわけで(実際のところ、虐待が起こる家庭を知れば知るほど、それが小さなカルトであることを感じ る)、もっとも危険なのは、家庭の閉鎖度が高いことだと感じている。どんなに立派な親であってもただの人、だからこそ抱える偏りの弊害を減らすためにも、 佐藤さん、松浦さんたちが試みている保育のように、外から風が吹き込む窓があることは救いになるはずだ。こんな支えがあってこそ、親も子も(保育者も同じ らしい)成長することができる。伊藤さんの提起は、たとえどんなに親が立派でも、子どもを支えるうえで限界があるということを示唆してくれる。吃音はひと つの例だが、親がどんなに子を肯定できたとしても、子の個性を社会が認めてくれない限り、子は人生の発達課題を達成することができないのだ。親子丸抱えで 受け入れてもらえるセルフヘルプ・グループが有効なゆえんである(『女性ライフサイクル研究6号、特集セルフヘルプグループ』をご覧ください)。
第四章では、大人の人生と子どもたちとの関係を考えてみた。子どものことを考えるさい平井さんのように「生まれなかった子ども」にまで想いを馳せるの は、女性ならではかもしれない(このような視座を共有してくれる男性があるかもしれないとほのかな期待を持ちつつ......)。この章から読み取れるのは、子ど もの命や生が、大人の選択によって決定されていく現実だろう。その責任の重さを直視しつつ、私たちはどう生きてきたかが問われ、姿勢を正さざるを得ない気 分になる。子どもとの関わりを通じて私たち大人の生きざまが問われるのだというテーマは、当研究所が一貫して抱えてきたものである。
さて、第五章では、社会に眼を向けてみた。少年事件のたびに新聞を賑わす「少年非行の凶悪化」は、津富さん、小松さんによれば、どうやら嘘らしい。マス コミの報道に乗せられて安易な結論を出すことで、子どもたちの本当の姿を見誤らないよう注意したいものだ。子どもたちの本質は変わらない、問題は大人たち の側にあり、子どもたちは大人社会を映し出しているだけだろう。大人の過ちを子どものせいにするということを、私たちは長いこと繰り返してきたが、自分た ちの失敗を認め、子どもたちを守り育む責任を果していかなければと思う。そのさい、砂川さんが提起してくれた保護と自己決定の双方をよく考える必要がある のだろう。エクパットの活動は、その試みそのものかもしれない。子どものことを考えるうえで、私たちの身近な子どもたちだけでなく、日本の外へも眼を向け る必要性を感じる。なにしろ、わが国は、子どもの商業的性搾取にかなりの程度、加担してきたわけだし、そんな大人の姿を子どもたちはじっと見ているのだか ら。
最後になりましたが、いつも温かく応援してくださっている皆様、原稿を寄せてくださった皆様、表紙とイラストを描いてくれるJunさん、パソコン編集のいのきえみさんに感謝したいと思います。


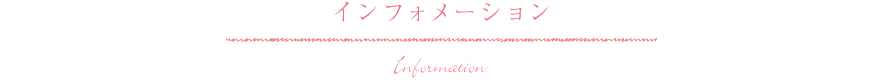
 「今時の子どもたちは...」という言い回しは、非難のニュアンスとともにいつの時代にもありましたが、子どもたちの心が見えないのは、それを見ようとしないからですし、子どもたちの声が聴こえないのは、それを聴こうとしないからではないでしょうか。
「今時の子どもたちは...」という言い回しは、非難のニュアンスとともにいつの時代にもありましたが、子どもたちの心が見えないのは、それを見ようとしないからですし、子どもたちの声が聴こえないのは、それを聴こうとしないからではないでしょうか。