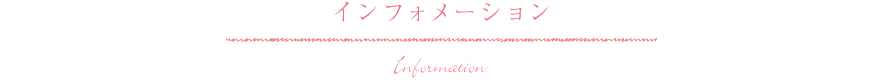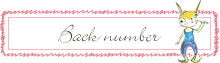- 2006.11.23 年報『女性ライフサイクル研究』
- 想像力とレジリエンス
女性ライフサイクル研究所 西 順子
1. はじめに
日頃の臨床活動では、女性が人生で出会う様々な問題や悩みについて相談に応じているが、なかでも子ども時代の逆境を生き延びてきた方と出会うことが 多い。例えば、虐待やいじめ、親からの見捨てられ、前世代から家族が受けてきたスティグマやトラウマなど、子どもにとってはただそこに生まれてきた運命と しか言いようのない状況、環境のなかで、子どもは持てる力を最大限動員させて逆境を生き延びている。なかでも、「想像力」は、子どもが「自分」という感覚 を保ち続けるうえで重要な役割を果たしているのではないかと感じてきた。例えば、絵を描くのが好きで子ども時代にいつも絵を描いていたという方、本を読む のが好きでいつも本を読んでいたという方など、想像力を使って自分の世界に入り込み、心を満たすことによって、子ども時代の虐待的な環境を生き抜いてきた 方々がいる。
しかも、「想像力」は子ども時代だけでなく、その後の新たなライフサイクルの段階を生き抜くためにも重要な力と感じてきた。例えば、虐待によって受 けた心の傷は、虐待的環境を抜け出した後もなお影響を与え、生き辛さとなって顕在化することがあるが、大人となった今、これからどう生きるのかと方向喪失 しているときにも、「想像力」が必要となる。「理想的自己の再創造にはイマジネーションとファンタジーとを積極的に練磨することも必要となる」(ハーマ ン)と言われるように、新たな自己を創造し、新たな未来を創造するとき、想像力はなくてはならないものだからである。
そこで、本稿では、想像することで子ども時代の困難を生き抜いた女性へのインタビューをもとに、想像力とレジリエンスについて考えてみたい。
2. れい子さんへのインタビュー
れい子さん(仮名)は現在大学4回生、21歳。落ち着いた穏やかな雰囲気のなかに芯の強さを感じさせる女性である。家族は、両親と妹、弟と5人家族。インタビューは2006年6月、就職が内定し、ほっと一息つかれているという時期に行った。
(1)辛かった体験
「これまでの人生で一番辛かったのは、小学校5年生からシンガポールに住んだことです」。子ども時代に困難だったこと、辛かったことは? という質問に対して、れい子さんは迷いなく即答した。れい子さんは小学校5年から中学2年の冬までシンガポールの日本人学校に通ったが、そこでは「今まで 普通にできていたことができなかった。普通に出来ると思っていたことができなかった」と言う。それは、「友人関係」である。
シンガポールの日本人学校は世界で一番大きい日本人学校で、1クラス生徒が約40人、学年で9クラス、毎年クラス替えがあった。5年生、6年生と友 人ができず、中学1、2年のときは、1人の友人ができた。れい子さんは、友人ができないため、学校では1人で過ごしたが、1人でいることより、「1人の私 を周りがどう思ってるんやろう・・」と、周りが自分をどう見ているかということが気になり、そのことが辛かったと言う。
れい子さんは、ある日突然異文化のなかに身をおくことになったと言えるが、仲間関係が重要となりつつある思春期の始まりに、学校という集団のなかで「1人」であったことは、どんなに心細く、孤独であったことであろうか。
その後、れい子さんは、中学2年の冬に小学4年までを過ごした土地に帰国、地元の中学に通うことになる。しかし、そこでも「仲良かった友人はどう思 うんやろう。帰国子女と言われたくないし・・」と、自分がどう見られるかが気になり内気になった。帰国してからの中学時代も辛かったと言う。「1人でいる ことは平気。でも、一人でいる自分を周りがどう見ているのか、1人でいることが変じゃないかと気になった。特に、体育の時や授業のなかでの班づくりが、嫌 だった。班づくりは自由に生徒達に決めさせるもので、最後に1人になるのが辛かった」。れい子さんは冷静に落ち着いてお話くださったが、「今思えば子ど もって残酷。子どもは好きではない」と言う。その言葉から、言葉では表現し得ない心の傷つきが今もなお残っているのであろうと推察された。
(2)辛かった時の心の「オアシス」
小学校5年~中学時代が一番辛かったというれい子さん。当時、れい子さんを支えていたものは何だったのか。れい子さんは、小説を読むのが好きだっ た。小学校に入学時よりいつも図書館で本を借りて読んでいた。シンガポールでは日本の本は高価だったが、自分が読みたい本は親が買ってくれていた。ある 日、家にパソコンがきた。れい子さんの母はタイプ打ちが早く、その姿に憧れて、「自分も早く打てるようになりたい」と練習したが、それが楽しかったと言 う。そして、れい子さんは小説を書き始めた。読み手は家族だったが、中学の時は1人の友達に読んでもらう。友達から「好きな子との恋愛のお話を書いて」と 頼まれて、友達を主人公にした小説を作り、友人にも喜んでもらった。
れい子さんが書いた小説を、母は「天才だ!」と喜んだ。絵を描くのが好きだった弟と妹が小説に挿絵を入れ、母が編集、製本してくれた。シンガポールでは安くて製本が出来たからとのことだが、「それもとても嬉しかった」とれい子さんは言う。
シンガポールでは、子どもが外で遊ぶのは危険なこと。近所に同年齢の子どももいなかったため、放課後帰宅してからは家のなかで過ごす。家で、小説を読んだり、描いたりして過ごすのは、「オアシス」だったとれい子さんは語られた。
れい子さんが書いていた小説って、どんなテーマだったのだろうか。「だいたいは変な話。もぐらが人間になって、またもぐらに戻るような。ファンタジーもの」とのこと。
大人になった今は、当時のことを振り返ってどう思うのだろうか。「中学時代から、『自分は変』って思っていたけど、無理に周りに馴染もうとしていた、そこまでしなくてもよかったな、悩みすぎていたなと思う。今は、変わっていると思われても、平気」と言う。
(3) 「自分らしさの発見」から「人生の選択」へ
「今は、変わっていると思われても平気」と言えるれい子さん。れい子さんは子どもの頃の辛い体験を超えて、今や「私は私」という確固としたアイデンティティを築いておられる。その後、れい子さんはどのような過程を歩まれたのだろうか。
れい子さんは、高校選択の時期、自分の意志で進路を決めていた。「高校は、地元から出たかった。中学時代の人と誰も一緒じゃないところにいきたかっ た。そのほうが、新しい生活をしていけるんじゃないか、友人ができたり、楽しく過ごせるんじゃないか」と、地元以外の高校も受験できる専門科を志望。人文 学科に入学する。
高校では演劇部に入ったが、そこでは、男子も女子も皆、個性が強かったと言う。「こんなんでもやっていけるんや」「自分を表現するのってカッコい い」「皆と同じと思わず、好きなようにしたらいいんや」と思った。また、「負けないように、自分の個性、芯というものを持ちたいと、それにエネルギーを傾 けた」。役者には関心はなかったので、脚本を書いたり舞台の裏方にまわり、照明や演出にエネルギーを傾ける。演劇部に入っているというと、「なんで、役者 しないの?」と言われることが多かったが、「私は裏方が好き」と裏方の仕事にプライドを持ってやっていた。
特に、高校2年の春、三本立てのオムニバス風の劇をすることになったが、れい子さんに演出の声がかかり、はじめて演出を担当。新入生歓迎会で発表す るも、アンケートでは、れい子さんが演出した劇に人気が集まった。れい子さんが演出した劇は、不思議系の劇。演技指導はできないので、照明や音など全体の 雰囲気を演出したという。その経験によって、れい子さんは「自分にしかできないものがある」と、自分の個性を確認すると同時に、「みんなで物をつくるのっ て好き」と、物づくりの喜びを発見されている。
その後、れい子さんは高校を卒業し、志望大学に入学。3回生から就職活動を始め、現在は総合職としてテレビ製作部門の採用内定を得ている。内定の評 価では「物づくりの大変さもわかったうえで、物づくりのおもしろさも知っている」と返ってきた。「実際、どこに配属されるかはわからないし、不安もあるけ ど、ちゃんと自分のことを見てくれているからと、信用できると思う」と嬉しそうに語られた。
就職活動での困難はなかったのだろうか。大学の就職課に求人はほとんどこないため、まずは情報収集をしたが、焦りからも、やりたいと思ったところか ら手当たり次第に申し込んだ。しかし、どれも落とされた。れい子さんは、どうして落ちるのかと考えた。就職セミナーで聞いたことがあった「自己分析」から やってみようと思い立ち、自分はどんな人間か、何がやりたいのか・・と、自分でシートを作って書いていったという。内定をもらった会社は、自己分析をした あとに申し込んだ会社であった。
れい子さんは「物づくり」という好きなことに携われる仕事を簡単に手に入れたのではない。「落とされる」という痛い経験をばねにしながら、「自分と は何か」と自分と向き合い、考え、挑戦し、決断することで、自分の人生を切り拓いていかれている。れい子さんは今度の春には、家を出て、1人暮らしの生活 をはじめるとのことであった。
(4)れい子さんのレジリエンス
れい子さんは、小学校高学年、中学校と心理的困難のさなかにありながらも、想像力によって「心のオアシス」をつくってきた。想像力はまさにれい子さ んのレジリエンスであったと言える。そして、れい子さんは想像力を使って空想の世界で心の翼を拡げるだけでなく、想像的創造によって他者とつながりを回復 し、創造の喜びを他者と共有し、よりひろい世界へとつながりを拡げてきている。
また、れい子さんは15歳の時に自分で自分の進路を決めている。しかも、人に合わせたり、人と比べたりすることなく、15歳の子どもが最善を尽くし て自分の進路、つまりは人生の第一歩を決断した勇気には感嘆する。困難を超えるために、未来に希望を見い出し、自分を信じ、世界を信じて一歩踏み出せるれ い子さんの強さは、子ども時代より育まれてきた想像力が源になっていると言えよう。想像力は自己の内的な力となっている。
このように、れい子さんの想像力は、子どもの頃の困難を超えて生き抜く力となるだけではなく、人生を切り拓く力として未来に活かされ、未来を創るレジリエンスとなってきたと言える。
3. 想像力とレジリエンス
子ども達は、小説、漫画、アニメ、映画などファンタジー物語が好きである。宮崎駿(2001)は自分の子ども時代の体験から、「現実を直視しろ、直 視しろってやたら言うけども、現実を直視したら自信をなくしてしまう人間が、とりあえずそこで自分が主人公になれる空間をもつっていうことがファンタジー の力だと思うんです」と述べているように、想像の世界のなかでは誰もが主人公になり得、自由になれる。
想像することは、子ども誰もにとって力となるのはもちろんのこと、逆境におかれた子どもにとっては、想像力があるからこそ、闇のなかを生き抜くこと ができると言っても過言ではない。なぜなら、「想像力は生の根底にある暗黒物質を変貌させることができる」(ル=グゥイン、2006)からである。ここで は、特に虐待サバイバーの想像力とレジリエンスについて考えてみたい。
(1)子ども時代を生き抜く
筆者はカウンセリングを通して子ども時代の虐待サバイバーと出会うなかで、彼女たちの生き抜く力には感嘆させられてきた。子どもは親に愛着を求める が、それが得られないばかりか、理由もなく怒られ、殴られ、あるいは見捨てられ、性的な対象と見られ、本来子どもとして与えられるべき愛情と保護を受けら れず、子どもにとっては訳がわからず理解できない、理不尽な、不条理な世界を生き抜いてきている。理解できない世界に身をおくとは、なんと不安で恐怖であ ることであろうか。しかし、それでもその世界を生き抜くために子どもは想像力を駆使する。たとえば、ある日、叔母さんから誕生日のプレゼントにもらった漫 画本に感動し、親から見捨てられ、何をやってもダメな主人公に自分を重ね、漫画の世界に自分の世界を見い出し、その世界を楽しむことで子ども時代を生き抜 いたサバイバー。絵を描くときは何時間でも没頭でき、すべてを忘れることができた、絵を描いている時間だけが幸せだったというサバイバー。孤児のファンタ ジー物語の主人公に自分をなぞらえ、「この親は本当の親ではない。どこかにきっと本当の親がいるはず。私の生きる場所はここではない」と空想することで、 外の世界に希望を見出し、家を出れる時期を待つことで生き抜いたサバイバー。他にも、音楽の世界、詩の世界、歴史の世界、植物の世界・・など、さまざまな 想像の世界に没頭したサバイバーたちがいる。
子ども時代に酷い虐待を受けながらも人生の主人公でありえた女性たちは、子どもの頃に「心のなかの神話、空想生活、想像上の友達をもっていた」と ボーレン(1991)は言う。「これらの子どもたちは、自分のことを自分で選んでいくヒロインであった。彼女らは、自分がどのように扱われているかとは別 個に、自分についての感覚を維持した。状況を評価し、現在はどのように反応したらよいかを決定し、将来に備えて計画をたててきたのである」と。子どもは環 境を選べない。しかし、子どもは、想像の力によって、想像の世界に身をおくことで、「自己の感覚」を維持することができる。
(2)人生の物語を創る
逆境を生き延びた後、トラウマを超えて生きようとするときにも、想像する行為はレジリエンスとして必要である。では、どのように必要とされるのか。筆者は臨床経験から、サバイバーが大人になって新たな物語を切り拓こうとする時について、次のようなイメージをもっている。
子ども時代は真っ暗闇のトンネルのなかを手探りで歩くようなものであった。闇の中の光を頼りにとにかく出口を求めて、生き延びてきた。トンネルから 出れば、そこには幸せが待っていると希望をもって。しかし、やっと闇から出られたという時、そこには安堵と共に新たな苦悩が待っている。闇から新しい世界 に出たが、そこはどこなのか、どういう世界なのか、何が待っているのかわからない。その世界はあまりにもまぶしくてよく見えない、見るのも怖いし恐ろし い。知っているのは、闇のなかの経験だけである。これからどの方向に向いて旅をすすめていいのかわからない。手がかりになる指針・羅針盤は手元にはない。 焦り、不安になる。一歩踏み出せば、お化けや亡霊が見えて恐怖に脅える。この世界もまた闇に包まれているのではないか・・。
サバイバーがカウンセリングを訪れる時とは、このように方向を見失い、人生の物語が行き詰ってしまった時でもあるだろう。と同時に、未来へとつなが るために、物語の再創造に向き合おうとするときでもある。方向を見失った時、必要なことは、内なる声に耳を傾け、道が見えるのをじっと待つことであるが、 その答えは無意識からイメージの形をとって現れる。イメージは無意識からのメッセージであり、それ自体に自律性がある(老松、2004)。「無意識は物語 や神話の創造に常に関わっている」(エレンベルガー、1980)と言われるように、自我が無意識からのメッセージを聞きとっていくことで物語は創られてい く。
カウンセリングとは、想像的創造の場を提供し、クライエントが人生の主人公として自分の羅針盤を見つけ、人生の舵をとっていくのを見守ることに他な らず、その物語は主人公自らが創っていくものである。物語を創る(物語を語らせる)ことについて、ル=グウィン(2006)は「いつも、絶えず、生き延び るためにこれをしているのです。世界を物語にできない人は発狂します」と言う。人生を生き抜くためには、想像力によって自己の物語を創っていくことが必要 なのである。
4. 終わりに
本稿では、想像力とレジリエンスについて、女性へのインタビューをもとに、カウンセリングでの経験を照らし合わせながら考えてきた。未来を生きる子 どもたちに私達大人ができることは、子どもの未来を決めることではなく、子どものもつ力を信頼し、子どもの内なる世界を尊重し、見守ることであると、その 思いを強くした。筆者自身は、カウンセリングの場が、物語を紡いでいく想像的創造の場となるようエネルギーを注いでいきたい。
最後になりましたが、快くインタビューに応じ、自分の言葉で語って下さったれい子さんに、心より感謝いたします。
【参考文献】
ボーレン、J.S(1991)『女はみんな女神』(村本詔司・村本邦子訳)新水社
エレンベルガー、H.(1980)『無意識の発見(上)』(木村敏・中井久夫監訳)弘文堂
ハーマン、J.L(1996)『心的外傷と回復』(中井久夫訳)みすず書房
宮崎駿(2001)「自由になれる空間」『ユリイカ』8月臨時増刊号、第33巻第10号
老松克博(2004)『無意識と出会う』トランスビュー
ル=グウィン、A・K(2006)『ファンタジーと言葉』(青木由紀子訳)岩波書店