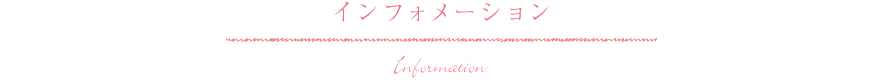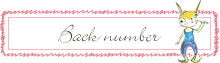- 2006.10.25 活動報告-論文/執筆/学会活動等
- 心理と司法の接点をさがして~アメリカ調査から(2006年)
『立命館大学教育相談室紀要』
応用人間科学研究科教授 村本邦子
1.はじめに
2.ロースクールにおけるリーガル・クリニックについて
3.アメリカン大学ロースクール
4.ジョージタウン大学
5.ワシントンD.C.第一審裁判所
6.ケンブリッジ・ヘルス・アライアンス暴力被害者支援プログラム(VOV)
7.コミュニティ・リーガル・サービス&カウンセリング・センター(CLSACC)
8.マサチューセッツ子どもへの残虐行為防止協会(MSPCC)面会センター
9.ボストン・カレッジ・ロースクール
10.おわりに
1. はじめに
2005年度、立命館大学法科大学院には、「法律相談」、「女性と人権」という2種類のリーガル・クリニックが設置されたが、とくに、後者においては、被害女性のケアにあたって、心理的な問題が生じた場合、当心理・教育相談センターと連携することで、トータルケアを提供することが目指されている。今回、法科大学院の教育プロジェクトの一環として、アメリカにおけるリーガル・クリニックを調査する調査団の一員として、2004年2月20日から3月3日まで、アメリカへ行ってきた。おもな目的は、アメリカにおけるリーガル・クリニックの具体的な運営のあり方を調査することだったが、筆者の任務は、とくに、リーガル・クリニックにおける法と心理の連携のあり方をさぐることにあった。
私は、もともと、女性や子どもを対象にした開業臨床という形で15年ほど臨床実践を行ってきたが、そのなかで、法と接点を持つ機会を幾度となく経験してきた。虐待や性被害など女性や子どもの被害をめぐる問題に取り組むなかで、実践の初期より弁護士とのつながりに恵まれていたので、法的判断を迷う場合に助言を求めたり、逆に、心理的観点から助言を求められたりすることがあった。裁判などの過程に関与する機会もあった。たとえば、インセストの被害女性が改氏名を家裁に申し立てするさい、弁護団の一員に加わったこともあれば、DVの被害状態や子どもの虐待状態を査定して意見書を書く、子どもの証言の信憑性について意見書を書く、弁護士会への人権救済申し立ての過程に付き添う、性犯罪事件の裁判過程に付き添い支援する、逆に、加害女性の心理について意見書を書いたり、加害女性の治療修復の過程の一部に関与したりしたこともある。こういった経験から、とくに被害問題をめぐっては、心理と法の連携が必須であることを痛感してきた。
加えて、応用人間科学研究科と法科大学院の院生を対象に4月より新しく開講された「司法臨床」の授業を、法科大学院の段林和江弁護士と一緒に担当するという機会も与えられ、今後、日本における心理と法の連携のあり方をさぐるために、先進的なアメリカのあり方を調査するという今回の旅をとても楽しみにしていた。非常に限定された個人的体験を除けば、司法そのものについてほとんど無知に等しい状態であったが、調査に先立ち、また、調査後も、調査団のメンバーと定期的に集まり、議論を重ね、貴重な勉強の機会を与えられている。本稿では、ささやかながら私の学びをセンターの仲間や読者の皆さんと分かち合えたらと思う。
2. ロースクールにおけるリーガル・クリニックについて
出発に先立って私がまず理解しなければならなかったのは、ロースクールにおけるリーガル・クリニックについてである。私と同じく、心理がおもなバックグランドである読者の皆さんのために、リーガル・クリニックについて簡単に紹介しておきたい。
日本では、2004年4月から法科大学院制度が開始され、従来、最高裁判所が設置する司法研修所が統一的な実務育成を行っていたものが、司法研修所における修習期間が短縮されて、各法科大学院がそれぞれ独自の実践教育を提供することになった。アメリカのロースクールでは、さまざまな方法で実践的教育が行われているが、もっとも実践的と言えるのがクリニック教育である。臨床心理士を養成している大学付属の相談室(当センター)と類似のものを想像すると良いが、学問領域の違いにより、その中身も違っている。
そもそも、アメリカにおいては、リーガル・クリニックの設置・運営をめぐって、さまざまな議論がなされ、ここ30~40年、現行のクリニック教育の制度が確立してきた。クリニック教育の定義は論者によりさまざまであり、ロースクールが法律事務所設立し、ロースクールの弁護士教員の監督下で学生が直接、事件を担当する「インハウス・クリニック」と呼ばれるものに限定する立場から、実際の事件を素材にしない「シミュレーション」などまで広く含む考え方まであるという。
アメリカでも、実践家のための主要な教育は修習制だったが、19世紀終わり、大学付属のロースクールが急速に発展し、実践教育の第一次的機関としての機能を果たすようになる。1870年、ハーバード・ロースクールが導入した「ケースメソッド・スタディ」(判例を読むことで法理論を学ぶ)と「ソクラテス・メソッド」(教員と学生との対話による教授法)が普及するが、20世紀初頭から実社会で機能する法曹教育として不十分だという批判が起こり、1930年代頃より、医学部のインターンに相当する実践の場が必要であるとの議論が始まった。1960年代になると、市民権運動や反戦運動が盛んになったことから、法律は社会変革の大きな原動力になるとの認識が拡がり、これまで貧困層に十分な援助を提供してこなかったのではないかとの反省も起こる。1968年、フォード基金がロースクール教育に10年にわたって資金提供すると発表したこともあり、多数のクリニックが設置された。60年代後半には、一定の条件下で、学生が依頼者を直接代理できるような資格が必要との運動が起こり、1970年の終わりには30州においてそのような法制度が整備された。現在、多くの裁判所において、クリニック授業をとる学生が直接的な弁護活動に携わっている。
弁護士や法学教授の監督下で学生が実際の事件に関わるクリニック教育は、その目的、活動内容から、①サービスモデル ②法制度改革モデルの2種類がある。前者は、教員指導のもとで学生が実際の事件を担当し、低所得者層の依頼者に法的サービスを提供するというモデルであり、後者は、社会正義の実現を目的に、環境訴訟、市民権訴訟、貧困問題など特定の分野に焦点を当て、目的に適った事件を選別して訴訟活動を展開するというものである(以上、おもな情報源は園田、2005)。
日本では、法科大学院が開設されたばかりであり、リーガル・クリニックの歴史は皆無であるが、これに対する対応は、消極派と積極派の2種類に分かれるという。リーガル・クリニックに消極的な大学院は、法科大学院修了後、司法試験に合格すれば、司法研修所での実務修習の機会があるのだから、学生時代に必ずしも実務に触れる必要はないと考える立場にあり、立命館を含む積極的な大学院は、理論と実務を架橋することが法科大学院教育の理念であり、リーガル・クリニックはこの理念の実現に大きな意味を持つとする立場をとっている。さらに、日本のリーガル・クリニックの実施の仕方には2種類がある。ひとつは、法科大学院の実務家教員、協力実務家がクリニックで法律相談を受け、学生がアシスタント的役割を果たす「ロー・ファーム型」であり、もうひとつは、学生のボランティア活動の一環としての法律相談の伝統を取り入れ、法科大学院の学生が主体で市民に無料で法的アドバイスを行う「学生法律相談型」である。立命館の法科大学院は後者の実現を目指している(この部分、おもな情報源は松本、2005)。
3.アメリカン大学ロースクール
3-1 アメリカン大学ロースクールにおけるリーガル・クリニックについての概要
授業風景(模擬裁判における法心理学者の専門家証言)
2月21(月)~23日(水)のおもな訪問先は、立命館法科大学院の提携校であるアメリカン大学ロースクールだった。20日(日)に関空を立ち、半日分の時差を経て、20日の夜にワシントン入り、翌朝、早速、アメリカン大学を訪ね、まずは、ロースクールの概要を聞いた。法学教授のミルシュタイン先生によれば、アメリカン大学では、1972年、ロースクールの法律事務所が開設された。当時、臨床教育(ロースクールの実践教育は "clinical program"と表現されており、「臨床」の語が使われていた)は、伝統的な法関係者からの攻撃に曝されたという。実務的すぎる、ロースクールに必要なのは理論であるという理由。しかし、自分たちは、理論と実践の統合が必要だと考えており、その理念を実現してきた。アメリカン大学ロースクールには、女性と法クリニック、DVクリニック、知的財産権クリニック、国際人権法クリニック、その他、計9つのクリニックがある。
ロースクールのカリキュラムは3年のうち最初の1年が必須科目履修で、2年目からクリニック授業を選択できる。クリニック授業は2期からなっており14単位(全体の単位数の1/6)。この他に、①エクスターンシップ(法律事務所で学生が働き学校でバックアップする)②シミュレーション(ネゴシエーションやインタビュー、その他のスキルを講義で取り上げる。グループでのロールプレイや、事前にビデオ撮影したものを素材にする)③ライブ・クライエントなどがある。
臨床プログラムのディレクターであるベネット教授によれば、クリニカル・プログラムは、学生2人をペアにして行う。大講義(16~20人)はカリキュラムに添った文献研究、ケース・ラウンド(ミーティング)、シミュレーションから成る。ケース・ラウンドでは、あらかじめ学生にアジェンダを書かせ、準備段階→決定→批判・反省を行わせる。スーパービジョンは、1人の教授とチームである2人の学生で行う。クリニックで扱う事件の選択の仕方については、さまざまな考えがあり、クリニックでインテークを行い、相談に乗っているところもあるが、アメリカンでは、NGOや弁護士会と連携し、リストを提出してもらい、教育的価値を考え、小さなケースを3~4つ選んでいるとのことだった。200人の学生がいて、8人に1人の割合でスーパーバイザーがついている。希望者が多い場合はくじ引き。インタビューをして選抜する所もあるが、クライテリアが不明確であり、教授のナルシシズムに陥るリスクがあるため避けているということだった。
臨床プログラムの評価について質問が及ぶと、リフレクションを重視しているものの、実際には難しく、試験はないので、評価は全般的に高くなる傾向があると苦笑していた。また、適性に欠く学生への対処であるが、だからこそ、2人のペアでチームを組み、補い合うようにしているとのこと、場合によっては、教授が補うとのことだった。ドロップアウトを進めることはないわけではないが、非常に稀であるとのことだった。
臨床心理士養成カリキュラムにおける教授法とも重なる話が多く、興味深く話を聴いた。応用人間のカリキュラムでも、講義や演習の他に、学内実習、学外実習を義務づけているが、理論的基礎も実践も含めて2年でやってしまうという現在のプログラムには、やはり無理があるように思えた。
3-2 ランチ・ミーティングにおける教授たちの教授法研究
21日のお昼は、教授たちのランチ・ミーティングに同席させてもらった。本当のところ、ここで何を見ることになるのか、始まるまで、私たちには皆目見当がつかなかったのだが、毎週1回、教授たちがランチをとりながら、クリニック授業の教授法について研究を重ねているということがわかった。時間は2時間である。この日は、"Provocateurs for Justice?"というテーマで、教授たちが授業のロールプレイを行いながら、臨床プログラムのスーパーバイザーとしての役割について研究していた。
Jane Aiken(2001)による" Provocateurs for Justice"という論文に基づき、これにクエスチョンマークを付すことで、その主旨の賛否を問いかけたもの。"provocateur"の適切な訳語がわからないが、"provocation"、すなわち、挑発したり、扇動したりする行為を動詞化し、それをする人を指しているようである。「正義のための扇動者」「正義のための挑戦者」という感じだろうか。配布されたオリジナルの論文に眼を通してみると、著者は、自分自身、正義の扇動者であることを切望しており、臨床教育には社会正義の実現を目指すという使命が含まれているという立場を取る。そして、正義の扇動者として、いかに学生たちを正義のための行動に駆り立てることができるのかという問題意識から、そのための教育方法論を展開している。
彼女は、"Justice readiness"、すなわち、「正義への準備性」の発達的アプローチを取り、①Right-Wrong Stage(○か×の二者択一的思考段階) ②Critical Thinking(批判的思考段階) ③Justice Ready(正義への準備完了段階) という3つの発達段階に分ける。学生たちは、学習の最初の段階において、法という「事実」を学んでいると考える。第一段階であるこの二者択一的思考段階において、法学教授とは学生に「真実」を伝える権威者である。学生は、正しい答を求め、「法律家らしく思考する」ことをひとたび身につければ、万事うまくいくと考えるが、実際には、いずれ、法律の際限ない不確かさに直面しなければならない。この段階の教育において、学生たちが、現実の文脈においては正しい答などないのだという複雑さに眼を向けることが可能になるようなフィードバックが必要である。
法律家としての知的発達の第二段階において、学生たちは、法を相対化するようになる。この批判的思考段階において、勝負をすること以外に、法律家は無力であると考えるが、実は、自分たちこそ知識と権威の源泉なのだということに気づかせることができれば、第三段階である正義への準備完了段階へ移行することができる。第三段階において、学生たちは、多様な正義のなかで自分がどんな役割をとっているのかを明確にし、その役割を通じて、自分の行動や価値観に折り合いをつけていくようになる。また、社会正義の視点を持って、法的議論をすることができるようになる。正義を尊び、正義の実践を教えることは、プロセスに焦点化することであり、この段階においては、違った役割をとる他者をも重んじることができるようになる。
著者であるAikenは、専門家養成校の教育者として、自分たちは、エリートを育て抑圧的な社会秩序を正当化するようなイデオロギーを強化するようなことがあってはならない、むしろ、正義のための扇動者でなければならないと説く。そのためには、自分たちの持つ法的スキルと学生たちを使って、正義を求めて闘うのでは不十分であり、臨床家として、前線に立つ法律家としてではなく、教育者としての役割を通じて、正義へのコミットメントが求められるのであると結ぶ。
ランチ・ミーティングにおいては、それぞれの発達段階にある学生と教授が、ある事例についてスーパーバイズ・セッションを持っているという状況のロールプレイをし、スーパーバイザーの役割について、また、学生を次の段階へと導くためのフィードバックのスキルについて議論していた。とくに、不法入国による麻薬取引に関する援助が失敗に終わり、がっかりしている学生を例に挙げ、第二段階から第三段階へと導くために、①whatより始め(何の前提で法的解決を取ることが有効であると考えたのか、この状況において法の役割含んでいる暗黙の前提は何か?)②howに移行し(どんなふうにして、法的救済を求める決断がなされたか、法システムは、この法的救済の欠如にどんなふうに反応するのか?) ③whyを投げかけ(この事例ではなぜ、法的救済が無効だったのか、このクライエントにとって、これがもっとも適切な解決だと信じたのはなぜか?)④行動計画と批判的自己洞察へと導く(この状況がまた起こったら、次はどうするか、法システムの有効性について持っていた前提は、どのような影響を与えたのか、この不正義の構造を打破するためにあなたが取り得る役割は何だろう?)ことが有効であるとのことだった。
教育者としての倫理観を議論し、スーパーバイザーとしてのスキルを高めるために、互いに学び合うという熱心さは感動的だった。日本の心理臨床の教育において、これほど真摯に教育者としてのあり方を考えている人たちがいるだろうか。個別にはあっても、大学において、チームとして、毎週、ミーティングを重ね、しかも教授同士がロールプレイをし合うなどということは想像を絶するものがある。そして、うちの研究科でランチ・ミーティングをしているところを想像してみた。
3-3 心理との連携について
心理との連携について触れられる機会がなかったため、この点について質問をすると、1980年代、クリニック内に精神科医を雇ったことがあったが、精神科医はクライエントの利益を優先しようとするのに対し、ローファームはクライエントが望むことを実現しようとするというように倫理的対立が生じるので、アメリカンでは、クリニック内に心理関係者を入れることをやめ、連携しない選択をしたとのことだった。大学によって立場はさまざまで、サイコロジストやソーシャルワーカーを入れ、院生と一緒に取り組んでいるところもあり、代表的なのはイエール大学であるとのことだった。
クリニックの外で、サイコロジストやソーシャルワーカーと一緒に働くケースはあるが、自分たちは、あくまでも、クライエント中心主義の立場からロイヤリング(弁護活動)を行ない、クライエントが望んでいることを中心に理解することを大切にしている。たとえば、ソーシャルワーカーは、子どもにとって何が良いかを推測して判断するが、我々は、その女性が子どもにとって何が良いと思っているのかを大切にする。また、サイコロジストやソーシャルワーカーたちは、女性は被害者であり、弱く、守られなければならないと考えているが、自分たちは違う。子どもの権利を擁護するクリニックを持つロースクールもあるが、非常に複雑であるため、自分たちはやっていない。子どものためにと、学生が自分たちの考えを押しつけるのは間違っている。保護命令中、女性が子どもを連れて戻ってしまったとき、警察や検察は女性を罰するが、自分たちは、女性の選択を受け入れ、怒らない、失望しない、罰しないとの説明だった。
各職業集団の倫理的葛藤については十分に理解できるものであったが、法律家はクライエント中心主義のスタンスを取り、他の職種は、被害者を弱い者と見なし、権威者の視点を押しつける云々の説明には疑問で、「それはディシプリンの違いによるものではなく、フィロソフィーの違いではないか」と言ってみたが、反応はなかった。これらの見解は複数の教授に共有されていた。アメリカンのロースクールでは、他職種との連携をしないという選択をしただけあって、他職種への理解は乏しいのではないかと肩すかしをくらった思いだった。その精神科医との出会いがよほど悪いものだったのだろうか。
ちなみに、アメリカでは、サイコロジストが裁判所に提出する意見書を書くようなことはないのか尋ねてみたが、めったにないとのことで、これも意外だった。なお、心理の教授は置いていないが、ボランティアで臨床心理士や精神科医に関わってもらうことは稀にある。たとえば、過去に、二次受傷を受けた学生のケアという形でサイコロジストに関わってもらったケースがあったということだった。
3-4 女性と法クリニックとDVクリニックとの合同セミナー:法心理学の専門家証言
最後のセッションであった23日の午後は、女性と法クリニックとDVクリニックとの合同セミナーにオブザーバーとして出席する機会を得た。このセミナーでは、期間中ずっと、ひとつのケースをさまざまな観点から学習するという方法をとっており、扱っていたのは、幼い子どもが病院に運ばれ、薬物中毒であることが判明、ニグレクト・ケースとして、2人の子どもの親権を奪われた若い母親のケースだった。このケースをめぐり、学生たちは、すでに、クライエントのインタビュー、ストラテジー・プランニングと事情聴取、カウンセリング、ネゴシエーションなどをテーマに理論やシミュレーションを学習していたが、私たちが出席したその回は、偶然、法心理学者による専門家証言がテーマであった。
前半では、「専門家の専門性とは何か?」をめぐってのディスカッション、「○○は専門家と言えるか、その専門性は何に基づいているのか?」をさまざまな職種に当てはめて議論させていた。○○には、占い師まで登場して面白かった。「科学的で特定された知識に基づいて証明できる、意見を言える」などの条件が挙げられていた。また、専門家が意見を言えるのは、事実から結論までであって、最終的には判事が、その結論に基づいて判断するのだということも確認された。
休憩をはさんでの後半では、教室の使い方が90度回転し、みるみるうちに模擬法廷の設定となったのには驚いた。シミュレーションという方法を使った授業についてはすでに何度も聴き、ロールプレイとどう違うのだろうかと疑問を持っていたが、「なるほど、これは、まさに、シミュレーションだ」と納得した。模擬法廷では、学生たちがそれぞれ、法廷場面での役割を演じ、これまで数百回も法廷で証言してきたという有資格のクリニカル・サイコロジストであるシュテッドマンさんが出演し、法廷における専門家証言をめぐるやり取りが演じられた後、ディスカッションがなされた。証言内容は、ケースの母親の心理査定結果だった。
後で、シュテッドマンさんに少し話しかけてみたが、彼は、法心理学者を名乗り、毎期1度、このセミナーに呼ばれて協力しているとのことだった。「それなら、十分に心理と連携しているじゃないか」と思ったが、おそらく、ここでは、「連携・協働」の語をとても厳格に使用しているのだろう。日本では、多少なりとも接点があれば、安易に「連携」と言う傾向があるが(ひょっとすると、我が研究科においても・・・)、本当は、ひとつのケースに一緒に深く関わり、共に処遇を検討していくという違いの役割を尊重し合った対等性のようなものが不可欠なのだろう。ちなみに、専門家証言の使用は、法律家のストラテジー・プランの一要素にすぎず、いわばツールとして利用すると位置づけられているため、「連携」とは呼ばないのだろうと感じられた。
法心理学(Forensic Psychology)についても、これまで、漠然とながら、心理と法の連携の最たるものとイメージしていたが、必ずしもそうではないことを知った。法心理学の概念は、たしかに法と接する部分の心理学を指しているが、それは、あくまでも独立した一学問領域であり、即、連携というわけではない。なお、"Psychology Information Online: Your Internet Resource for Information about Psychology" ( Practicehttp://www.psychologyinfo.com/forensic/)によれば、「法心理学とは心理学と法の共有部分であり、法的コミュニティに提供される心理学的サービスは、すべて、法心理学的サービスと言える。しかしながら、ほとんどの法心理学者は、本質的に臨床的サービス、法的サービスの両方を提供するものである。交通事故によって心理的トラウマを負った人の治療をするなら、それは、トラウマからの回復を助けるためにデザインされた臨床的サービスであるが、トラウマの程度や心理的損傷を査定するために法廷への報告を行った場合は、法的サービスなのである」。
具体的には、家庭裁判所との関連では、子どもの親権評価、面会によりリスク・アセスメント、子どもに関わる両親間の葛藤仲裁、子どもの虐待評価、養子受け入れ準備性評価、家族再統合プラン作成、親権停止の評価などの法的サービスの他、家庭裁判所からリファーされてくる家族への親子カウンセリング、治療的スーパーバイズド・ビジテーション、ペアレンティング・スキル・トレーニング、アンガー・マネジメント、子どもと大人への離婚への適応カウンセリング、両親間のコミュニケーション・スキル・トレーニングなどの臨床的サービスがある。
民事裁判所との関連では、個人的権利侵害の評価、IMEのセカンド・オピニオン評価、セクシャルハラスメント・性差別における感情的要因のアセスメント、労働者補償の評価、市民として生活できる能力の評価、心理的検死解剖(具体的にどんなことを指すのかよくわからない)などの法的サービス、PTSD、不安、鬱、トラウマ関連の恐怖症、慢性的な痛みにおける心理的要因、アンガー・マネジメント、トラウマ後の適応カウンセリング、関係性に与えたトラウマの影響についてのカップル・カウンセリング、脱感作などにまつわる臨床的サービスがある。
そして、刑事裁判所との関連では、少年犯罪に関する犯罪行為の評価、判決前の評価、保護観察の評価、権利放棄の評価、子どもの証言の信頼性の評価、性的加害者のアセスメント、責任能力の評価、成人の判決前の評価などの法的サービスと、接近禁止命令を破った人のカウンセリング、保護観察中の少年・成人のカウンセリング、犯罪被害者の支持的カウンセリング、裁判を待っている人のカウンセリング、暴力加害者のアンガー・マネジメント・スキル・トレーニング、性犯罪加害者へのカウンセリングと心理療法などがある。
2~3年前、「アンガーマネジメント」(日本語訳では「NY式ハッピー・セラピー」)というコメディがあったが、あれも、確か裁判所命令のアンガー・マネジメント・スキル・トレーニングだった。日本で、裁判所がカウンセリングや心理療法を示唆することはあっても、命令することはないと思う。法心理学が成立するためには、心理士の国家的認知(=資格)が前提条件なのだろう。
4.ジョージタウン大学
ジョージタウン大学のデボラ・エプシュタイン先生
2月23日(水)の午前は、ジョージタウン大学DVクリニックを訪れ、デボラ・エプシュタイン教授のお話を聴き、その後、レストランでランチをご一緒した。エプシュタイン教授は、学生だった1980年代前半、DV被害者を支援するNGOを立ち上げ、ロースクール卒業後、弁護士になり、1993年から、ジョージタウン大学DVクリニックで教えるようになり、教授になった。ジョージタウン大学では、教員も実務家も同等の身分(テヌア)で働いているとのことだった。
ジョージタウン大学ロースクールには、1983年、まず、6単位の性差別クリニックができたが、雇用差別の問題は時間がかかり、教育に適さないことがわかってきた。他方、1987年、D.C.第一審裁判所ではDVの保護命令(CPO's)のケースの援助を始めていたが、その緊急性と進行速度から、それが、すぐれた教育機会であることに気づいた。ほとんどのケースで、4週間以内に提訴過程を経験することができ、1セミスターに2~3ケースをこなすことができるからである。
DVクリニックは10単位を占めるので、セミスターが始まる前の1週間(4日間)10時から5時までインテンシブなオリエンテーションがある。授業では、法手続き、訴訟のスキル、自己洞察できる実践家であること、DVの力動(複雑な心理学的、社会学的、経済学的力動)の理解を目標にしている。DVクリニックでは、保護命令など限定されたケースを扱い、2組みの学生が4人の教員(教授と実務家)と2人の卒業生に指導を受けながら、1セミスターで2~3ケースを扱う。多くの場合、まず、学生が裁判所に行き、民事の保護命令を取ろうとしているクライエントに声をかけ、できるだけパーソナルなコンタクトを保ち、プロセスに留まるよう努力するとのことだった。また、裁判所と密な関係を持っているので、裁判官や事務方などから、クライエントを紹介されることもある。広報はしていない。過去にやったが、1500も問い合わせがあり(年間引き受けられるのは60ほど)、やめた。ただし、ホームページでは告知している。ニーズの高さを感じた。
DVクリニックの受講生は、女性が8割、男性が2割。過去は女性9割だったが、男性が増えつつある。どちらかと言えば、女性はDVというテーマに関心があり、男性は法手続きに関心を持っている。男性は、性被害などのクライエントに遠慮する傾向があるが、男性に積極的にコミットしてもらうことが重要だと考えている。雇用差別を扱っていた時と比べ、DVケースを扱うようになると、学生の仕事のリズムは変化した。学期中、いつもケースの責任が重く、危機状態にあるクライエントのために働くプレッシャーは大きい。学生が個人のコンタクト手段を与えるかどうかは、専門家としての選択をそれぞれにさせているとのことで、保護命令を取ろうとしているDV被害者に個人的コンタクトを与え、24時間体制で支援している学生がいる、そして、それを大学側もバックアップしているということに驚きを禁じ得なかった。
ここでも、心理との連携について質問してみたところ、ジョージタウン大学には心理やソーシャルワークの学部がないので連携できず残念であると、少なくとも連携には好意的であった。学期中に1~2回、授業に心理学者を招き、DVの心理的ダイナミックスなどについて講義してもらったり、ケースを違いにリファーし合う関係はあるとのことだった。また、クリニックをオープンにし、常に心理の研究者たちが出入りして調査をしている状態であるとのことだった。なるほど、クリニックに来るクライエントの心理学的研究ということも連携のひとつのあり方として可能なのだと思った。その研究成果をまた、クリニックに還元することもできるだろう。エプシュタイン教授は、「立命館では、準備段階から心理学者が関わっていてうらやましい」と言ってくださった(実際、今後、どの程度の連携ができるのかが問題である)。
翌日はワシントンD.C.の第一審裁判所見学をしたのだが、ジョージタウン大学ロースクールは、裁判所から徒歩10分ほどのところにある。食事中、裁判所内にあるDV受付センターのことが話題になると、エプシュタイン教授が、「マイ・ファースト・ベイビー」と愛情こめて語っていたのが印象的だった。彼女がDV受付センターの生みの親だということなのだと思うが、学生時代よりDV支援のNGOとして裁判所に出入りし、運動を通して、さまざまなシステム変革を起こし、実践の場で活躍してきたエプシュタイン教授がロースクールにいてこそ、学生が裁判所に出入りしてクライエントを見つけてきたり、裁判所で働くさまざまな職員(裁判官や事務官)が紹介たりと、裁判所とロースクールの連携が、信頼に基づいて、太いパイプでつながれていることが実感できた。教育者であるだけでなく、NGO活動家、弁護士、研究者、D.C.政府アドバイザーと幅広い活躍をしているエプシュタイン教授からは、その情熱が伝播してきて、アクディビストとしての血が騒ぐ思いだった。日程の関係で、ここでわずかの時間しか過ごせなかったことは残念だった。
5.ワシントンD.C.第一審裁判所
5-1 DVコート
24日(木)は、大雪が予報され、裁判所が休みになるのではないかと危ぶまれたが、何とか大丈夫で、雪の中、裁判所訪問する。入り口では、まるで空港の持ち物検査のような厳重なチェックで、カメラ、ビデオなどは取り上げられた。DVコートの教育訓練センターで、コート・ビジター・プログラムというのを用意してくださり、DVユニットの概要を聞き、裁判の傍聴をして、DVインテーク・センターの視察をした。センターは、裁判官と事務官の訓練を行っている。事務官はロースクールを卒業したての人たちで、2~3年、働くが、キャリアになるので人気が高い。エプシュタイン教授が言っていたように、ここからもロースクールのDVクリニックへの紹介ケースがあるのだろう。
DVコートは、ハワイ、フロリダ、ワシントンD.C.に先駆けて出来た。ハワイは家庭裁判所を統合して設立されたもの(子どもの監護権と刑事裁判手続き)、フロリダは刑事と民事の一部が統合(子どもの監護権、面会交渉権、養育費の管轄権なし)されたものであるのに対し、ワシントンD.C.のDVコートは、第一審裁判所の中にあり、DVに特化して、刑事の一部と家事部家族関係担当の一部を統合したものであり、もっとも包括的、総合的に事例を扱えるもので、1996年に設立された。米国では、70年代後半から20年の間にDV関連の法改正が進み、D.C.では、1982年に「家族内犯罪法」が制定された。連邦レベルでは、クリントン政権の1994年に「女性に対する暴力防止法(VAWA)」が制定され、DV対策が大きく前進した。D.C.でも、司法制度改革がなされ、DVコートができたことで、加害者からの報復の減少、殺人事件の減少、被害者の心情、DV事件のコントロール、社会へのインパクトなどの影響があったという(NMP研究会+大西、2001)。
ワシントンD.C.では、DVを広範囲に扱う。同じ家に住む者も含むので、親子、きょうだい、ルームメートなども含み、男女を問わない。85%は女性が被害者であるが、15%は男性。その関係において、暴力、脅迫、財産侵害が発生すると提訴できる。DV法廷での民事的救済の範囲は一時保護命令(TPO)、民事保護命令(CPO)であり、違反すると民事法廷侮辱か刑事法的侮辱に問われ、さらに被害を与えると刑事訴追もある。CPOは最大12ヶ月。
ふたつの裁判を傍聴した。ひとつは、黒人女性が子どもの親権を求めて来たが、立ち退き命令になっていて混乱している。裁判官も黒人女性、弁護士がついていないので困難が伴うケースの実例だった。大半のDVケースで弁護士がつかないが、こういったケースをロースクールの学生たちが担当している。実際には、学生たちの力量や授業期間から、学生たちが援助できるケースはかなり限定されるが、それでも、とても役立っているという評判だった。傍聴席にはアドボケイト(若い学生ボランティア)たちの姿が見られた。市民が関わることで裁判をオープンなものにする機能を果たしていること、こんなふうに学生のうちからボランティアとして被害者支援に関わることの意味を感じた。もうひとつは、保護命令を破った黒人男性のケース、原告は黒人男性だった。両者ともに男性のDVケースなので、関係を理解しにくく、最初はゲイ・カップルなのかと思ったが、片方が片方に住居を提供していたので(それ以上の関係はない)、同居関係として扱われているとのことだった。被告には他にも犯罪歴があり、たまたま法廷で出会った時、原告の子どもに話しかけたということを咎められているそうで、十分には理解できなかった。こちらは、弁護士が白人男性、検事が白人女性だった。
裁判所内での連邦執行官のサービスの説明を受け、裁判所の留置所見学ツアーが用意されており、若い男女の保安官が案内してくれたが、まるで映画の世界に入ったようで(「羊たちの沈黙」)、ちょっと怖かった。ここでは、有罪の人たちはオレンジ色のつなぎを着せられており、「日本と違って明るいんだなぁ」と思ったが、脱走した時に目立つようにだろう。独房は、男女、少年で分けられていた。
5-2 DVインテーク・センター
次にDVインテーク・センターの見学。インテーク・センターは、DV被害者の救済システムへのアクセスを改善することを目指して、DVコートの開設と同時に作られた。"One stop shopping intake center"として、被害者が必要とするさまざまなサービスを一ヵ所に集め、利用しやすいように、公的機関とNGOのパートナーシップで解決していこうとするものである。裁判所において、公的サービスと多種多様なボランティア団体が力を合わせて被害者支援をしていることが印象的だった。日本でも、公的機関と民間の連携が言われるが、実際には、パートナーシップとはほど遠いものがある。公的機関の方が上で、民間を体よく使おうとしている印象はぬぐえない。
インテーク・センターには、NGO緊急家族関係プロジェクト、NGOワシントンD.C.DVコアリション、ワシントンD.C.公設弁護士事務所、警察受付センター駐在所、合衆国検察局被害者証言支援係などの窓口が入っている。インテーク・センターの最初の入り口には、担当の黒人女性とその子どもたちが座っていた。今日は大雪で学校が休みになったので、連れてきているという。アメリカでは、小学生の子どもだけで留守番させるとニグレクトとして逮捕されるため、こうして職場へ連れてくるのだろう。道理で、裁判所内に子どもの姿が多いはずだ。地下には保育室もあるという。
5-3 DCCADV
午後は、インテーク・センターに受付が入っているDCCADV(コアリション)を訪問した。コアリションはDV問題に取り組むNGOが集まって構成された連合体、いわゆるアンブレラ組織であり、DV被害者支援提供グループ、地域啓発活動グループ、法律家などによって構成され、ジョージタウン大学のDVクリニックも関与している。お話をしてくれたのはディレクターのケン・ノイスさん、自分は全米唯一のコアリション男性幹部であると言い、視察団の中に2人の男性が含まれていること(ロースクールの二宮先生と松本先生)を喜んでおられた。
直接的な被害者支援の他に、関連職種のトレーニングもやっており、昨年3月には「119」(D.C.では警察)担当者200人に法律やDVについての基礎的知識を教えた。子ども向けの暴力防止プログラムもやっている。始まったばかりで、賛否両論。システムへの介入もする。これまでにも、致死を防ぐための法案を通したことがある。確立されてから変えるのは難しいので、確立される前に問題を明らかにし、意見を言うことが大切だということだった。DVの子ども支援は遅れているが、D.C.には知っている限りシェルターが持っている3つの機関がやっているとのことだった。
一番印象に残っていることは、DCCADVは現在、35万ドルの予算で動いているが(30万が連邦政府から、5万ドルが寄付)、D.C.からも助成してもらえるよう、2つの経営コンサルタント会社を入れ、5年計画で経済戦略を立てている、また、研究者と連携して学術的な成果報告もしているとのことだった。アメリカのNGOの基盤の堅さに驚くばかりだった。
フルタイム・スタッフは、裁判所5人、サウス・イースト地区の病院3人、事務所3人、スタッフのバックグランドとしては多様で、大卒を義務づけていないが、大卒でないのはDVサバイバーのスタッフのみ。あとは、女性学、アフリカン・アメリカン・スタディ、ジェンダー・スタディなどを卒業した人、修士を持つものもいる。3人はロースクールの出身、これから医学部に行く者もいるとのことだった。スタッフはさまざまなバックグランドから成り立っているようだったので、ここでも、多職種の連携について尋ねてみた。
連携のコツは、それぞれの領域でのミッションがあるから、連携の目的を明確にすること。たとえば、ここには、ソーシャルワーカーを入れないということだった。受付センターで、CPOの申立のさい、子どもの虐待・ニグレクトの訴えを起こされることがある。虐待があって良いということではないが、DV被害者の支援機関としてのここのポリシーは、その可能性によって女性が申し立てを躊躇するようになっては困る。DVの目撃と子どもが引き離されることによる影響の比較研究が今後、必要だと思うが、自分たちは、子どもたちに致命的な被害が及ばない限りは、むしろサポートを提示することを探るとのこと(弁護士倫理と同じで、クライエントの要求以上のことをするにはコミネント・ディスクロージャー)。自分がここにいる6年で、例外は2例のみだった。その2例では、スタッフが見守るなか、被害女性自身が通報した。子どもの安全を保証しながら、徹底した被害者中心主義を貫く彼らのポリシーを感じることができた。
NGOの立場からリーガル・クリニックの存在がどう見えるか尋ねてみたが、その評価はきわめて高かった。年間6000人の申し立て者のうち6~7%しか弁護士つけない状況だから、とても貢献しているとのこと。クリニックの授業をまだとれないロースクールの1年生や入学前の学生は、まず、ここにボランティアとしてやってくる。心理からも来るが、先ほどと同じ理由で、ソーシャルワークーのボランティアはとらないとのことだった(ソーシャワークの学位を持つと、子どもの虐待の通告義務が発生するため)。
6.ケンブリッジ・ヘルス・アライアンス暴力被害者支援プログラム(VOV)
6-1 VOVの概要と研修教育
2月25日(金)、ロースクールの先生方と別れ、ワシントンD.C.から第二の視察地であるボストンへ移動する。ボストンは、昨年6月、「他領域で支える暴力被害者支援を目指して」をテーマに、立命館で、日本コミュニティ心理学会第七回大会を主催した折(うちの研究科が共催)、ゲストとしてお招きしたサイコロジストであるメアリー・ハーベイさんと、弁護士であるオリバー・フォークスさんが住む街である。このお二人が大歓迎してくださり、ボストンに着くなり、早速、インタビューが始まった。ただし、今回は、他の訪問先との関係で、週末のみしか時間が取れなかったため、本拠地であるケンブリッジ病院を訪問することはできなかった。その代わり、メアリーさん、VOVのアドボケーターである春海葉子さんにそれぞれからお話を伺ったうえで、26日(土)は、VOV関係者とレストランで会食、27日(日)は年1回恒例で行われているVOVスタッフの交流パーティに参加という機会に恵まれた。
VOVメアリー・ハーベイさんと
VOVプログラムは1984年にスタート、現在は、クリニカル・サービスとコミュニティ・サービスの二本柱で地域貢献している。クリニカル・サービスには、危機介入的援助、個人治療、グループ・プログラムがある。ハーバード大学やその他の大学の精神科や臨床心理学、ソーシャルワークの学生の研修の場でもあり、博士課程、および、博士課程修了後のインターン生が10名程度、週24時間(週4日で1日は夜勤)、1年以上の研修を行う。研修終了後、ほとんどの研修生は各自、同種の機関に就職する。VOVでの研修は一種の特権と見なされており、就職にも非常に有利で世界各国から希望者が殺到するため、競争率は高いということだった。
最初3ヶ月はスタッフと研修生が1人ずつペアになり、その後慣れてくるとクライシス・アワー(インテーク)を1人で行うようになる。研修を重視しており、毎週3時間のトラウマ・セミナーと毎週3時間のチーム・ミーティングが義務づけられている。セミナーはジュディス・ハーマンさんが主催しているが、コミュニティ・チームからもスタッフが入り、精神医学や心理学を学んできた人たちに臨床の知識だけではなく、コミュニティに関わっていく中でのアドボカシーの重要性や、臨床心理士の役割の大きさについても考えてもらうことを目的としている。ミーティングで、研修生は、自分が抱えている難しいケースを出して相談する。
5年ほど前にも一度、VOVを訪れ、研修の一部に参加させてもらった経験があるが、質の高い研修システムのあり方に印象づけられる。病院という設定の中ではあるが、大学や地域の各機関と連携しながら、地域貢献と学生や若手臨床家の研修・教育を統合させたVOVの理念とシステムには学ぶべきものが多いと感じた。現在、私自身、主宰している女性ライフサイクル研究所にて、臨床心理領域の学外実習先として実習生の受け入れをしており、どのようなシステムをつくれば、クライエントや社会にとっても、実習生にとっても利益のある実習が可能なのか考え、スタッフ、実習生を含む研修システムを整える努力をしている。博士課程修了後のインターン生と修士課程2回生という差はあるが、ヒントとエネルギーを得た思いだった。
6-2 VAST(アドボケイト)の概要とその活動
コミュニティ・サービスには、CCRT(コミュニティ危機対応チーム)、VAST(被害者アドボカシー・サポート・チーム)、CHB(殺人遺族センター)のサービスがある。今回は、そのうち、VASTについて詳しく聞いた(CCRTについては、ハーベイ、2005を参照のこと)。
VASTは、インタビューした春海葉子さんを含む2人のアドボケイトが、担当しており、それぞれ、20時間ずつ週3日勤務している。給料は、政府のOffice of Victims of Crime(暴力被害者への助成金が支払われるオフィス)から、病院を介して支払われる。このチームは、住宅の問題、裁判、警察に関するものなど、トラウマを受けたことによって生じてくる日常的な問題に応対している。他方、被害者への直接支援の他、コミュニティ教育、政策提案もしている。臨床的サービスの提供だけでは問題解決につながらないことから、2000年に開始された。サービス対象は18歳以上の成人男女、DV(90%)、レイプ(5%)、ヘイトクライム(5%)などで、最近は、Policy Trafficking(人身売買)にも取り組み始めた。特徴的なのは、臨床プログラムが有名であるため、重症なケースが入ってくること。つまり、幼いとき虐待を受けていて、大人になってDVの状況にあるというような複合したトラウマ被害者が多い。自殺の可能性も高く、臨床チームと恊働で対応を相談している。枠組みの柔軟性を大切にしているが、同時に自分で線をひいていくのは難しい。
法的支援との関連では、裁判所へ弁護士と一緒に行くことが多い。VOVで法律関係の人と連携しているのはアドボケイトだけ。弁護士との連携はケースを通して個人的につながっていく。アメリカのDVのプログラムで、裁判で扱うものは保護命令だけ、本当に問題に関わっていくと、保護命令はほんの一瞬であり最初の段階である。保護命令を取った後、アドボケイトは離婚や子どもの親権に関わっていく。3~4年かかるケースがたくさんある。ほとんどのケースにおいて、DVや虐待があったとしても、ある程度期間が経っていれば、面会が許可されてしまう。一般的なパターンとしては、監視つき面会が半年あって、監視なしの面会に移る。半年くらいで状況は変わらない。しかも、裁判所が面会の許可(推奨)を出しても、その後は裁判所による強制力がなく、たとえば、裁判所が推奨した加害者治療プログラムを受けなかったからと言って、罰金をとる制度もなければ、それで面会ができなくなるということもない。
よって、法での強制が必要。DVがあっても加害者が逮捕されていないケースが半分以上である。被害女性は、加害者は子どもの父親でもあるし、子どもとの関係を築いてほしいと思っている。重度のケースでは、警察が介入し投獄されることもあるが、それでも面会はなくならない。なぜなら、子どもの虐待の証明が難しいから。たとえば、DVがあり、子どもも身体的虐待を受けているケースでは、病院から児童福祉局に通報があり、子どもと母親を被害者として認める。児童福祉局が母親と父親の両者から聞き取りを行い、その結果父親が家を出ていくことになる。児童福祉局は子どもや高齢者の虐待については警察に通報する義務があるが、母親への虐待については警察に通報する必要はない。母親も警察とは関わりたくないと思っている。多くの場合、保護命令を出して、父親に家を出ていってもらうが、このようなケースにおいて、後々裁判所へ行った場合、たとえ児童福祉局が関わっていたとしても、DVがあったと証明するのは難しい。
児童福祉局が母親と子どもの虐待に関する報告書を出しても、裁判官によって報告書の重要性を決められてしまう。父親が子どもに会いたがっている場合、監視つき面会にするだけでも困難。一般的な面会の形式の例としては、週2回平日に3時間程度と2週間に1回の面会宿泊。DVがあっても、警察が関わっていなければ、3ヶ月くらいでこのような面会の形態になってしまう。3ヶ月の間に、裁判所のなかにあるクリニック(コート・クリニック)にケースが送られ、父親に会っても大丈夫かどうか判断がなされる。コート・クリニックでは、パートタイムの精神科医や心理士(ほとんどが女性)が心理的見解を述べるが、「父親の権利運動」の影響を受けた保守的見解が多く、被害者支援をしている側は、なるべく、コート・クリニックにケースがまわらないように努力している。アメリカでは、コート・クリニックがあるばかりに、他の臨床心理士の声は聞かれない(コート・クリニックへ回る前に、GALというシステムがあるが、ここでは省略する)。システムができているばかりに、機能しないと他の動きがとれなくなるとのことだった。日本から見ると、アメリカはシステムが整っていて羨ましいように感じられるが、理想的とは言い難い内実を見た思いだった。春海さんのお話は、ちょうど、支援体制を被害者サイドから見た感じで、アメリカの裏表が見え、興味深かった。
アドボケイトという資格はない。アメリカでは、アドボカシーという概念が浸透しているものの、アドボケイトの仕事の内容と質はそれぞれであり、裁判所や警察等、とくに権威主義的な場所での風当たりは強い。バックグラウンドがないと、動きにくい時が多く、一人のアドボケイトはソーシャルワーカーの資格をとろうと学校に通っている。実は、ケンブリッジ病院内でも、アドボケイトの役割を理解している人は少ないのだそうだ。春海さんの働きぶりを聞きながら、これまで自分自身がやってきた被害者支援の仕事に近いものを感じた。心理にせよ、司法にせよ、システムとして固まっていないからこそ、柔軟にやれてきた側面にあらためて思い当たる。今後、日本社会がどこを目指して進んでいくべきなのか考えさせられた。
6-3 司法との連携
上記インタビューのほか、VOV関係者との会食、および、VOV19周年パーティに参加し、さまざまな立場の援助実践家たちから話を聞く機会を得た。複数の人から繰り返し聞かされたことは、コート・クリニックが父親の権利運動の影響を受け、面会を子どもの権利としてではなく、父親の権利と位置づける風潮があるということだった。「心理士であれ弁護士であれ、中立的立場を取るならば、社会の流れ、たとえば、そういった父親の権利運動に利用されてしまう。リーガル・クリニックの学生は、社会のコンテクストを理解することの重要性を学ぶべきである」というのがハーベイさんの意見である。ボストンだけの特徴なのか、全般的にそうなのかよくわからないが、たしかに、9.11よりアメリカ全般が保守化していることとパラレルなのかもしれない。また、弁護士と臨床家との協働は、アメリカ全体から言えばごく稀であることもわかった。「弁護士は自分たちが一番偉いと思っているから、他の職種と一緒に仕事をしたいと思っていないよ」と冗談交じりのコメントを何度も聞いた。レキシコンの地域精神病院で働き、個人開業(薬物療法)もしているというコミュニティ精神科医は、弁護士と関わることは多い、アメリカでは精神病患者が拒否する時に薬物を処方するには裁判所の許可が必要だからと言っていた。危険が伴う緊急の場合、1本の鎮静剤と4日までの入院が可能だが、それ以上は不可能ということで、精神医療のあり方も、日本とはずいぶんと状況が違うことを知った。
VOVは、ハーバード大学の医学部と提携していることから、ハーバードのロースクールとの連携についても尋ねてみたが、これまで、ずっと、公式な連携はなかったということだった。個人的なレベルでの関わりはまったくなかったわけではなさそうだった。リーガル・クリニックでDVを扱う上で、VOVスタッフを授業に招かない手はないじゃないかと意外な気がしたが、そうなのだろう。なお、最近、VOVに国際人身売買のセクションができてから、ハーバードのロースクールと共同のプログラムを持つようになり、公式の連携が始まったばかりである。ロースクールとの窓口を担当しているVOVスタッフへのインタビューをアレンジしようとしてくれたが、今回の訪問は日程が限られていたため、それが適わず、残念だった。今後の連携のあり方、そこから開けていく両者の関係に興味がわく。
7.コミュニティ・リーガル・サービス&カウンセリング・センター(CLSACC)
7-1 CLSACCについて
2月28日(月)の午前は、Community Legal Services And Counseling Center (CLSACC)を訪問し、センター長であるレスリー・クライン弁護士、リーガル・ディレクターのエレン・ウィルバー弁護士、カウンセリング・ディレクターのポ-ル・ゴールドムンツ臨床心理士にインタビューを行った。
CLSACCは、1970年の設立以降、低所得者層に無料のリーガルサービスと安価なメンタルヘルスカウンセリングを低所得層に提供してきた民間機関である。現在、4人の弁護士(実務にあたるのは3人)と1人の臨床心理士、6名の事務スタッフ(うち3名が非常勤)に、常時、約85~100の弁護士や資格を持ったカウンセラー、学生ボランティアが年間約1100クライアントに対してサービスを提供しているとのこと。オフィスとして、ケンブリッジ市の建物の半地下部分を利用しており、光熱費を含め使用料は無料とのことだった。
7-2 弁護士と心理士の協働、ソーシャルワーカーの役割
このプログラムで裁判に関わるクライエントたちは、貧困や低所得の問題に加え、危機状態にあって、精神的問題を抱えている場合が多い。クライエントがどういった状況にあり、法廷でどこまでできるかといったことをセラピストが弁護士に説明したり、裁判をスムーズに運ぶために手伝ったりもする。薬物・アルコール依存、精神障害のあるクライエントへの対応、亡命者へのセカンド・トラウマの対応。DVケースでは、避難の後、問題があった関係に戻るのでなく、新しい状況で生活を立て直すためにも、セラピーが必要。
ポールさんの元には臨床ソーシャルワーカーがいて、弁護士と心理士の間をつなぐ役割を果たしている。そもそも、弁護士とカウンセラーは、全く違う世界で教育、トレーニングを受けてきているので、コミュニケーションを図ることが難しく、1人のクライアントに対する仕事の目的・ゴールも違う。他職種でしばしば衝突が生じるのは、守秘義務の違いがある。クライアントが職種によってそれぞれ違う義務を負っていることを理解する必要がある。協働ミーティングを月1回行なっているとのことだった。
他にも、ソーシャルワーカーの役割がある。たとえば、DVケースにおいて、本当に危険な状態にいる人で、週に1度のセラピーを受けようとする人は少ない。その日の子どもの食べ物や、どこに住んだらいいのかなど、現実的な問題が先行する。このような段階にあるクライエントに、ソーシャルワーカーが電話で対応したり、弁護が始まった最初の段階で、裁判所につきそうことが、クライエントにとても役立っている。結果的に、裁判における弁護活動の手助けともなっている。
リーガル・クリニックでは、精神的な障害を持っている人をとりたがらない。ロースクールのリーガル・クリニックは1学期ごとに生徒が変わるので、短期で終わるケースのみを扱う。短期間では、ケースの一部しかわからないということをまず教える必要があると思っているとのことだった。
CLSACCは、まさに、リーガルサービスとカウンセリングサービスとを共存させている場であり、バックグランドの違う専門家たちが互いに尊重し合いながら相乗効果をあげていることが実感された。ソーシャルワーカーの役割も興味深かった。ここでの臨床ソーシャルワーカーは、ちょうどVOVのアドボケイトと同じような役割を担っているように思われたが、心理と司法を繋ぐうえで、このように橋渡しをしてくれる職種が必要なのかもしれない。
8.マサチューセッツ子どもへの残虐行為防止協会(MSPCC)面会センター
MSPCC面会センターのプレイルーム
28日の午後は、長距離バスに乗り、MSPCC面会センターを尋ねた。またもや大雪の予報で、バスがストップする確率が高いとのこと、大急ぎでのとんぼ返りとなったが、とにかく行って見てきたという感じ。MSPCCのシンシア・ジョンソンソンさん、他スタッフの方2名と、通訳として加藤曜子さんが加わってくださってのインタビューだった。
MSPCCは、マサチューセッツ州に18ヶ所あり、親子のための様々なプログラムを提供している。面会センターは2つあり、常勤3名、非常勤12名が働いている。対象児は乳幼児から16~17歳。月25~30家族がこのセンターを使用、現在30件の待機家族がいる。裁判所からの依頼が多く、7割以上がDVケース。アルコールや薬物の問題を持つ親と子の面接や、養子縁組後の面会なども。安全第一なので、来所時間に15分の差をつけ、セキュリティ・ガードを置いている。全般的にうまくいっているが、困難を感じるのは、両親の関係が悪く、話もできないようなケースの場合。ここでの面会はうまくいっても、監督つき面会期間が終われば自分たちにはどうにもできない。
すでに聞いてきたように、背後にDVがあって離婚した親と子の面会では、まず、スーパーバイズド・ビジテーション(監督つき面会)の形を取ることが多いため、面会センターが利用されることになるが、私の一番の関心は、子どもが暴力的な父親を怖れ、面会を嫌がるようなケースはないのかどうか、あるとすれば、どう対処するのかということだった。とにかく、面会を始める前に、一度来てもらって話をする。子どもは部屋やおもちゃを見て、目を輝かせ、次回来るのを楽しみにする場合が多い。まず、「今日ここに来たのは何のためか知ってる?」と尋ね、答えに応じて説明する。それから、「何か心配なことがある?」と聞き、「お父さんが殴らないか」などと言うようなら、「ここではそういうことが起こらないようにスタッフがいる。そんなことが起こりそうなら部屋から連れ出す」と説明する。こうして、最初に安心と信頼を作るが、なかには、DV被害のために、父親もスタッフも信頼することができない母親もいる。
子どもが「会いたくない」と言った場合の対応は年齢によって違う。乳幼児の場合は、母親との分離不安が考えられるので、子どもが泣き出したら別室にいる母親のもとに連れ出し、落ち着いたら父親の元に戻すということを何度も繰り返す。年齢の低い子(だいたい8歳まで)の面会時間は1時間だが、3~4回に分けて面会する。年齢が上になると(だいたい16~18まで)、1時間45分。子どもが嫌だと言っても、面会センターまでは来なければならない。子どもに理由を聞き、話をして、少しでも会わせる努力をする。子どもが父親を本当に怖がっている場合には、MSPCCの方針を説明し(父親が暴力をふるったり、怒鳴りつけたりするようなことは絶対にさせないこと)、安心感を与えるようにするとのことだった。こういったことを3~4回繰り返し、それでもダメなら、ここまでの経過を裁判所に状況説明に行く。途中で子どもの気持ちが変わることはよくあるし、きょうだいのうち一人は面会し、一人は会わないというケースもある。たとえ、子どもが面会を拒否したとしても、裁判所が決めたことなので、誰かが勝手に「今日の面会はなし」とすることはできない。日本では、しばしば、アメリカのスーパーバイズド・ビジテーションについて、子どもが嫌がったら会わなくてもよいと紹介されているが、必ずしもそうではなさそうだ。なるほど、裁判所の決定を第三者が勝手に覆すことができるはずはない。たとえ、子どもの意思表示があっても、コートクリニック、その他で判定がなされた上で、決定されたことだ。
子どもが「会いたくない」という理由としては、母親の影響もあり得るが、DVを見てきた子どもたちの多くは、親にパワーを及ぼすことを欲して、ノーと言うことがある。子どもは面会にノーを言うことでパワーを感じる。特に、DV家庭で育った子どもはパワーを持ちたくなる。それが尊重されることは重要だが、大きすぎてはいけない。枠組みが必要。子どもが怒りや攻撃性から一時的にノーを言っても、後で気持ちが変わることもある。一度ノーと言ったからといって、その状態にロックしてしまわないことが重要。MSPCCは、親子の安全な関係を経験させることを目的にしているとのことだった。パワーとコントロールの問題を抱える子どもたちの課題については、十分に理解できた。
DVのあった親子の面会を長く支援してきたシンシアさんに、暴力が介在するケースでも、子どもにとって面会が良いかどうかという議論に対する個人的意見を尋ねると、「子どもは両親を愛しているし、とてもforgiving。父親が一緒に住んでいなければ、父親のことを心配し、愛しているから、父親が元気でやっていることを自分の目で見たい、会いたいと思っている。そして、今までとは違って、これからどのように良い関係を築くことができるかと望み、常にテストしている」との答だった。子どもたちのそういった思いには切ないほど共感できたが、続いて、「子どもたちのそんな気持ちに、父親たちは応えていると思うか?」と質問してみた。「時に、妻と会うためのチャンス、嫌がらせとして利用する父親もいるが、多くの場合、父親は子どもを愛している。暴力をふるって妻や子どもを傷つけたことを悼んでもいる。だからと言って、暴力の問題が解決するとは限らないが、その気持ちはあると思う」ということだった。
性的虐待などがあった場合、面会ができるようになるまでにたくさんの治療と償いを必要とする。裁判所が、お金を払うこと、お金のない人にはコミュニティ・サービスを命じる。裁判所の便所掃除やホームレスのための仕事。後者はとくに有効である。自分たちでも社会の役に立っているという自己評価、償い、社会の一員であると感じることで孤立を避けることなど。父親としての責任をもたせるため。お金にしろ、労働にしろ、ペイさせることが重要とのことだった。これも、納得のいく話だった。問題は、ボストンで聞いたように、スーパーバイズド・ビジテーションが比較的短期で終了になるのだとすれば、その後どうなるのかということである。面会についての意見書を書くこともある自分の立場からは(しばしば、会わない方が良いという趣旨の)、非常に複雑な問いと課題を残した訪問だった。時間的に不十分な訪問であったが、センターの明るく楽しげで暖かい雰囲気や、スタッフの方々の歓迎的な雰囲気に、このセンターに来る親子もこのような心地よさや安心感を得るのだろうと思われた。
9.ボストン・カレッジ・ロースクール
9-1 ボストン・カレッジ・ロースクールのリーガル・クリニックの概要
3月1日(火)の午前は、ボストン・カレッジ・ロースクールのリーガル・クリニック、リーガル・アシスタンス・ビュローを訪れ、まず初めに、民事事件担当クリニックのカウィーナ・ウェン教授にクリニックの概要を聞いた。
リーガル・クリニックは、市民権運動が盛んだった1968年、貧困層、社会的弱者の力になりたいという学生の意識から誕生した。ロースクール側は責任上、スーパーバイザーとして弁護士を雇っていたが、80年代、臨床教育の場として変革がなされ、現在は、ロースクールの教員が学生の弁護活動の監督をしている。現在、ロースクールは4人の弁護士教授、1人のコンサルタント・教員の臨床ソーシャルワーカーがいる。民事事件担当クリニックは、一般的な法サービスを提供するもので、弁護士資格を持つ教員4人と、コンサルタントとしてソーシャルワーカーの資格を持つ教員1人がいて、学生は24人。需要が高いので1セミスターで、2~3年生の選択授業となっている。クリニックの単位は7(現場4+クラス3)。ここでは学生に2人でペアを組ますことはしていない。責任を持たせる。問題がある場合は、教員がかなりの援助をする。とくにビデオのやりとりを見て、改善のために丁寧に指導するということだった。現場の評価は、5つの領域からなる基準に従い、セミスターの中間と終わりに、学生たちに面談してフィードバックしているとのことだった。D.C.で聞いてきたのと違い、実習授業の評価の基準が明確であり、成績を一方的に言い渡すのでなく、その根拠や課題を含め、学生たちにフィードバックしているという姿勢には感銘を受けた。
クリニックの歴史は長いので、クライエントは口コミで集まる。雇用されているインテーカーが電話でインテークし、可能性あるクライエントを選別し(収入が多い人、対象地域外の人などは他へリファー。裁判所が収入基準を決めている)、基本的な情報収集を行い、その上で、週に2回、教員たちがケースの採用を決めるとのことだった。引き取らないクライエントについては簡単な情報提供をしたり、雇っている学生(ロースクールのキャリア・サービス・センターで募集)が対処することもあるとのこと、ここでのきめ細かなフォローには共感できた。
9-2 他領域との連携
ボストン・カレッジLSのSWリン先生
民事事件担当クリニックには、18年勤務してきたというソーシャルワーカー教員のリン・バーレンベルグ教授がいらっしゃり、クリニックにおける他領域との連携についてインタビューした。多くのクライエントが精神的困難を抱えているため、法的サービス以外のものも必要とされる。自分は、ここでは、ソーシャルワーカーとして仕事をしているのではなく、あくまでもコンサルタントであり、教員である。学生がクライエントを理解し、援助できるように助けることが仕事である。たとえば、子どもに特殊教育が必要なケースの場合、弁護士に、医者や福祉が言っている状況について説明したりもする。
DVケースでは、暴力やレイプや精神障害について教えることがロイヤリング・スキルに必要だし、ケース戦略にも関わる。学生たちは22~23歳で、法については知っており、事実について尋ねることは得意でも、情緒的側面についての質問をすること、どういう質問をすれば良いのか、どのように聞けば良いのかを教える必要がある。弁護士がソ-シャルワーカーやカウンセラーになるわけではないが、ロイヤリングに必要である。ケース戦略にも携わる。学生は身体障害については理解できても、精神障害については理解しにくいので、障害者が政府から支援を受けるさい、サポートするのも重要な役割である。クライエントと会った時に、精神的問題があるかどうか発見させる手助けもする。カウンセリングが必要なクライエントや、子どもにケアが必要なケースもあり、そういったことも見極め、必要な情報を提供することも大切である。他の専門職(医者など)とのつきあい方、アプローチの仕方、他のプロも尊敬すること、一緒に働く時の姿勢なども教える。
学生が自分の個人的背景を自覚し、自分の問題を客観視する援助も重要である。たとえば、ケースとして、アルコールの問題を抱えるクライエントが2回無断キャンセルをした時、学生が「何度すっぽかしたら、ケースを断っていいのか」と怒った。無断キャンセルの理由を聞いたのか尋ね(実際のところ、朝のアポイント設定には無理があった)、アルコール問題を抱えるクライエントにとって社会生活を送ることが困難であることを理解した上で弁護活動をしなければならないことを教えた。後でわかったことは、その学生の父親がアルコーリックだった。プロとしての経験とパーソナルな経験の関係、立ち止まって自分の背景を振り返ることも教えている。また、時に、学生の思いこみが援助を妨害することがある。たとえば、精神障害があると知的に低いと思いこんでいる学生は、情報をクライエントと共有しない。誤った思いこみを認識させることも重要。DV被害者だと、被害経験について話すことが辛いこともあれば、役に立つこともある。
連携のさいの困難として、仕事のゴールや倫理が衝突するという点が挙げられていたので、私の方から、裁判を求めてやってきたクライエントの精神的状況が、専門的見地からは、裁判の過程に耐えられないのではないかというリスクを感じた場合は、どのように対処しているのかを尋ねた。確かに、こちらの持っている情報からすれば、裁判が回復の過程に傷を与えるだろうと予測される場合がある。アセスメントが難しい。クライエントがセラピストを持っている場合、クライエントと直接話し、主治医に相談するように言う。セラピストがついていない場合でも、直接、自分が話をして、安全確保など小さい一歩一歩を示唆する。自分がコントロールしているという意識が重要。それでもクライエントが先に進みたいと言う場合、弁護士がバランスを取る必要がある。弁護士がメンタルヘルス・アセスメントをどこまでできるか、専門家をどんなふうに利用するのか。授業でトラウマやDVについてある一定の知識を与えておくことができるとの返答だった。
9-3 職業によるゴールや倫理の葛藤
このインタビューの後、相談室や受付の写真を撮らせてもらい、他のスタッフと挨拶したが、クリニックの立ち上げから、司法と心理が連携して調査をしていることをとても評価してもらった。他職種と連携してやっていくという方針をもつクリニックならではだろう。その後、法学教授のロバート・ブルーム先生も加わり、インド料理店でランチとなった。インタビューの終わり頃から合流していたブルーム先生は、リン先生の最後の部分には若干、批判的な様子だった。帰りの車の中で、「自分が若い時の失敗を話してあげよう」とあるエピソードを話してくれた。若い頃、ヘロイン中毒の非行少年のケースを扱った。警察の取り調べに不法行為があり、裁判に勝てば釈放されるが、再びヘロイン中毒に戻ることになる。裁判に負ければ治療を受けられる。自分は勝訴するように努力しなかった。ずっと後になって、少年よりクレイムを受けた。「君は私の弁護士だったはずではないか」と。後悔しているケース。人間としては正しい選択だったかもしれないが、法律家としては間違った選択をしてしまったということだった。
「善き人間であることより、善きプロフェッショナルであることが優先されるのでしょうか?」と尋ねたかったが、考え直してやめた。これは、間違った考え方だろう。前者には明確なクライテリアがなく、時に傲慢となる。今の私が彼の立場にあるならば、きっと、状況と自分の危惧をありのままに説明し、「自分は人として、君を勝訴に導く援助をしたくはない。しかし、職業人として最善を尽くす。君の将来を祈っている」ことを伝えるだろう。たとえ、彼の人生に一文の価値をもたらさなくても。弁護士がそんなことを言うことはないのかもしれないが、状況は違えど、心理臨床家として私自身が、そんな決断を迫られることがある。
ついでながら、リンさんの対応について、私は賛成である。ロースクールのコンサルタント、教員として働く以上、クライエントの危機に対して、状況についての最大限のインフォームド・コンセントを行い、弁護士にも伝えたうえで、最終決定をするのはクライエントであろう。弁護士がバランスを取るというのは、そういう意味だろう。そういったそれぞれの立場の違いを理解しあうことができさえすれば、目標や倫理の違いを越えて、他職種の連携は可能になるのだと考える。
10.おわりに
アメリカでは、心理と司法との連携が進んでいると聞いて視察に加わったが、実際には、必ずしもそうではないことを知り、いったい何を調査すれば良いのか、最初、途方に暮れる思いだったが、視察予定の最後に、ボストン・カレッジでの連携の実際を学ぶことができ、安堵した。今回は、リーガル・クリニックの調査について行ったという感じだったが、次回は、是非、積極的に連携を方針としている大学を選んで、調査したいものだ。今回、強く感じたことは、資格問題をはじめとして、臨床心理学のアイデンティティが日本において、いまだ十分に確立していないことが、状況を困難にしているということである。臨床心理士の職域として、福祉、医療・保健、司法・矯正、教育の分野、労働・産業、開業などがあげられるが、それぞれの領域によって、司法との連携のあり方は違ってくるだろう。
司法・矯正の領域における心理と司法の接点は、もっとも「法心理学」に近いものであろう。「法心理学」の実践をそのまま「司法臨床」と呼んで差し支えないのかどうか。今学期より、「司法臨床」の授業が開講したが、「司法臨床」の定義も含め、現在のところ、私自身は、保留にしている。池田(1991)は、「司法心理臨床」を、「犯罪(または非行)事案の捜査からはじまって、犯罪者等の処遇を決定し、さらに犯罪者等の更正と社会復帰を目指す一連の過程において、そこに関係する種々の機関の職員が、心理学的知識、技術、方法を用いて対象者とかかわる活動の総称」と定義し、廣井(2004)は、「司法臨床」を、「司法機関である家庭裁判所において、少年や家族に施される臨床的アプローチ」と定義している。
今回、連携を目指しているロースクール「女性と人権」リーガル・クリニックが当研究科、もしくは当センターに期待している役割は、女性と人権をめぐる比較的新しい分野における心理臨床との関係である。上記の定義から言えば、「司法臨床」は心理学の一領域と位置づけられるが、「司法臨床」の開講目的から言えば、それは、むしろ、「司法領域を含む心理学の実践」であると同時に、「心理領域を含む司法の実践」であるものが求められているように感じられる。「司法臨床」の定義を見直すべきなのか、厳密に言えば、別の命名が必要なのか、学の定義を含め、引き続き、模索していきたい。
メアリー・ハーベイ(2005)「暴力被害者を支えるコミュニティの生態学的架け橋~ケンブリッジ病院暴力被害者支援プログラム(VOV)に学ぶ」『日本コミュニティ心理学研究』第8巻1号。
廣井亮一(2004)『司法臨床入門』日本評論社。
池田美彦(2001)「司法心理臨床とは」『司法心理臨床』(竹江、乾、飯長編)星和書店。
松本克美(2005)「日本のロースクールと立命館大学ロースクールの特徴:アメリカ視察の目的」(未刊配付資料)。
NMP研究会+大西(2001)『ドメスティック・バイオレンスと裁判:日米の比較』現代人文社。
園部直子(2005)「米国ロースクールにおけるリーガル・クリニック教育の実際」『法学セミナー』2005年2月号。