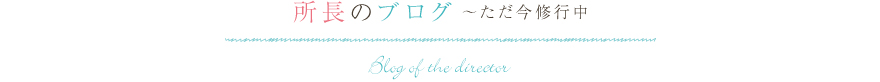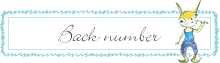今朝は気持ちのいいお天気で一日がスタートしました。
この一週間もあっという間。今週は、女性ライフサイクル研究所のグループルームが、コミュニケーションの場、学びの場として、フレキシブルに活用された一週間でした。順に振り返ると・・
火曜日の夜は定例のスタッフ研修。皆で面接技術を高めるべく、切磋琢磨して臨床について学びあう時間はとても貴重な時間です。スタッフみんなの熱心さに、私自身もエネルギーで満たされました。
木曜日の午前~昼過ぎまで、年報会議。女性ライフサイクル研究所フェリアンと力を合わせて、年報『女性ライフサイクル研究』の発行に向けて、月一回の会議を重ねています。論文にまとめていく過程のディスカッションは考えさせられ、思考を深める機会となっています。今日も様々な発見と気づきがあり、視野が広がりました。
木曜日の夜は、家族看護援助の前期授業一日目。毎年一コマ目は、複雑な問題を抱える家族の心理として、「DV被害者と家族」「子ども虐待と家族」を取り上げています。一番伝えたいことは、回復の指針として、「生活コミュニティのなかに味方が増えること」。「人との信頼のつながり」です。しっかりと受けとってくださり、嬉しく思いました。スタッフもお手伝いで参加してくれました。
そして今日はハンズオン講習会二日目。今日も講師の浅井咲子先生がポリヴェーガル理論をとてもわかりやすく教えて下さいました。マッサージテーブルを使ったハンズオンワークで自律神経系のリズムを感じることはとても興味深いです。身体の不思議というか、生理学の世界に生命の神秘を感じます。「今、ここ」にいる空間と時間を参加者の皆さま、そしてスタッフも一緒に学ぶことができて感謝です。
女性ライフサイクル研究所が、一つの「場」として、活かされることはありがたいことです。今日も「いい場所ですね」「参加できてよかったです」と声をかけてくださり、しみじみと嬉しかったです。「場」として活かされることは、ここに集ってくれる「人」がいてこそ。人とのつながりに、皆さまに・・感謝です。
お勧め情報
★2016年7月3日(日)13:00-15:30 「夏の交流会」のご案内
NPO法人FLC安心とつながりのコミュニティづくり主催で、今年は夏に「交流会」があります。パールノートピアノ演奏♪&団士郎さんのトークライブ「家族のないしょの話」です。
どなたでも参加できます♪ ぜひご参加ください。 →詳しくはこちら
★映画「さとにきたらええやん」のご案内
「こどもの里」は大阪市西成区釜ヶ崎にある、子どもたちの遊びと学びと生活の場です。この映画では「こどもの里」を舞台に、子どもも大人も抱える「しんどさ」と関わり向き合いながら共に立ち向かう姿を追っています。こどもの里を応援しています♪ →詳しくはこちら
なお、昨年、こどもの里館長の荘保さんにインタビューをさせて頂き、ささやかな論文としてまとめました。こちらもお読みいただければ嬉しいです。→『女性ライフサイクル研究第24号:特集 抵抗とレジリエンス』
今朝の一枚。一か月以上咲いてくれています。すごい。