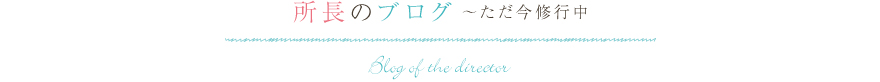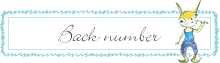- 2024.06.02 日々のこと
- 6月がスタートしました
あっという間に6月に入りました。月一回のブログを目標にしていますが更新できず、6月を迎えました。
日々の生活リズムは、仕事とプライベート生活、そして研鑽のための学習や研修で、一か月半が過ぎました。
また日々、目の前にある現実を生きつつも、人の命やライフサイクルについて思いを馳せていました。
研鑽としてはトラウマに焦点をあてたソマティック・アプローチの学習に勤しみました。
ソマティックなアプローチを学ぶことは、生きるということの深遠さに触れることでもあります。
5月にスタートした女性のトラウマ読書会『なぜ私は凍りついたのか~ポリヴェーガル理論で読み解く性暴力と癒し』では、「はじめに~第三章」までを読みあい、性暴力の現状と刑法改正と問題点について、ボリヴェーガル理論について皆で学びました。
研究所スタッフ読書会では4月は『トラウマと身体~センサリーモーター・サイコセラピーの理論と実践』「はじめに~第一章」の階層的情報処理(認知、情動、感覚運動)について、5月は『複雑性PTSDの理解と回復』「はじめに~第一章」の複雑性PTSDについての基本的理解にについて学びました。
個人の研鑽としては、昨年トレーニングを受けたSP(センサリーモーター・サイコセラピー)の卒業生として学ぶ機会に参加したり、SE™(ソマティック・エクスペリエンシング®)のテキストを読み直しコンサルテーションを受ける等、トラウマへのソマティック・アプローチの知識を整理し、自分を振り返る時間を持つことができました。
学びに終わりはありません。来年一月から始まる関西でのSE™トレーニングも楽しみにしています(詳しくはこちらをご参照ください⇒★)。日々研鑽に努め、成長を感じられるように切磋琢磨していければと思います。
ちなみに、最近お気に入りのセルフケアは、お天気のいい日の休日、外を歩くこと。
今月は雨の日も多くなると思いますが、四季の変化や街の様子を感じながら、外を歩く時間を楽しめればいいなと思います!
先週のお花。芍薬が咲くのが楽しみです。