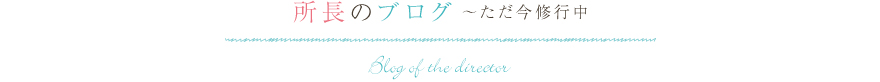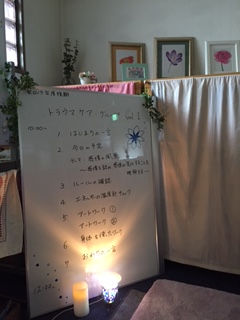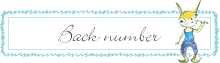- 2019.02.11 グループ/講座
- 2月のトラウマケア・グループ、女性のトラウマ読書会は
寒い日が続いています。昨日日曜日は、2月のグループディ。
いいお天気でしたがグループのお部屋は冷え込み、暖房は空調の他にもホットカーペット、電気ストーブ、ひざ掛けも使って温かくして過ごしました。
午前のトラウマケア・グループの今月テーマは「喪失と発見」。
トラウマには喪失が伴いますが、人々はショックや否認のために喪失を認めないか十分経験することが難しいものです。しかし否認がゆっくり減少するに伴い、徐々に喪失を認め、受け入れやすくなります。喪失が確認され、受け入れられると悲嘆の過程が始まります。この過程には「自己共感」がとても重要と言います。今回のアートワークでは、喪失を認め、自己への共感を高めるためにグリーティング・カードを作りました。
まず準備では、自分と同じようなトラウマを体験した人をイメージし、喪失に名前をつけ、その人に贈る言葉や伝えたいメッセージを考えます。そのあと、アートワークでは真っ白いカードの表紙に、心地よく、希望に満ちたイメージを想像して、水彩絵具を使って描いていきます。水彩なので、紙に絵具がにじんだ感じがとても優しい感じです。カードの表紙ができあがった後は、カードの内側に自分に宛てたメッセージを書きます。
このアートワークを皆でシェアすることで、場が温かい雰囲気に包まれていきました。プログラムにそって考え、イメージし、カードを作成することを通して、自分自身にも温かく肯定的な共感の気持ちをもてることに、とても感動的しました。温かく希望に満ちたワークでした。
午後の読書会では『生きる勇気と癒す力』第二章「癒しの過程」の「打ち明け、対決すること」「許しは必要か」の読みあいをしました。このテーマのなかで、著者は繰り返し「自分のために」と説明しています。打ち明け、対決するにせよ、しないにせよ、一番大事なことは「自分に焦点をあてて自分のために考える」ことだと理解しました。印象に残った言葉を少し紹介しましょう。
「真実を打ち明けたり、対決するのに正しいという手順というものはありません。打ち明ける時期や方法、そしてそれを実行に移すか否かも人それぞれです。けっして無理はしないようにしましょう。虐待者との対決や家族との対話は、癒しの過程に不可欠ではありません。何をするにしても、自分のためにしましょう。」(146頁)
「癒しのさまざまな段階について話をする際、必ず許しについて聞かれます。癒しにとって唯一必要なのは、自分自身に対する許しです。」(163頁)
午前のグループの「喪失」というテーマも、午後の「許し」というテーマも、共通して大切なのは、自分自身への共感や共感的理解なのだなと思いました。
次回3月の読書会の読みあいは「精神世界~魂を癒す」「心の決着と前進」です(169-182頁)。
詳しくはこちらをご覧ください→★
シクラメン、3年目。今年も花を咲かせてくれました!