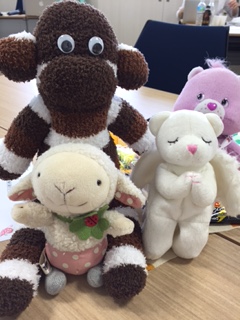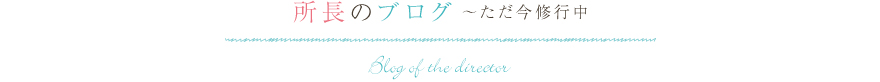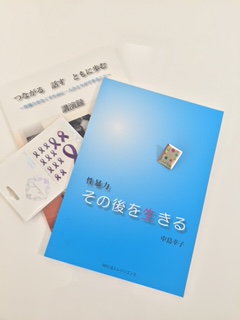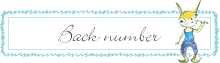- 2016.05.30 学び-ワークショップ他
- 支援者のためのセクソロジー講座に参加して-その3
28日・29日の二日間、東京で開催された「支援者のためのセクソロジー講座」に参加しました。今回はいよいよ全三回講座の最終回でテーマは「性虐待や性暴力とセックス・セラピー:子どもの場合と大人の場合」。
一日目は「性暴力とはどんな問題か」、複雑で多面的な問題であることについて、発生率や影響まで基本的知識について学び、二日目の今日はトラウマ治療に焦点をあて、安全にセラピーをすすめるためのエッセンスから、癒しとエンパワメントに役立つスキルやエクササイズまで、具体的に学びました。
これまで、EMDRやSEなど身体志向のトラウマ・アプローチを学ぶ機会はありましたが、性(セクシャリティ)に焦点をあてて学ぶのは初めて。なので、今回の連続講座を通して、性(セクシャリティ)を扱う統合的なセラピーについて学べて、本当によかったなと感謝の気持ちです。
性(セクシュアリティ)は、よりよく生きるということと密接に関わっているということを実感。性虐待・性暴力から回復するということは、世界への信頼感やつながり、安全という感覚、生きていることの価値を取り戻し、人生に対する自己コントロール感や選択する力を取り戻すことでもあるのだと、再認識しました。
いろいろご紹介くださったエクササイズを、まずは自分で実際にやってみたり、スタッフと一緒に練習してみたいと思います。
情熱的に熱心に教えてくださったダリュシュ・スコブロインスキー先生、そして安全で温かくてリラックスした場を提供くださった主催者のHEART カウンセリングセンターの皆様、講座のスタッフの皆さまには心から感謝いたします。ありがとうございました!
ちなみに、HEART カウンセリングセンター代表の熊谷珠美さん、スタッフの田中美帆さんはSEトレーニングの同期で、SEアシスタント仲間!そして今日は、同じく同期のSEメンバーも数名参加されていて再会を喜びました!そして、EMDRや他の研修でご一緒したり出会った方々・・など、前にもお会いしましたよね、という「つながり」が増えていくのは、とても嬉しく有り難いことです。こうした出会いとつながりの場、学びの場、エンパワメントの場をつくってくださった皆様に心から感謝です。
性虐待、性暴力が減るように、なくなるように・・社会の問題として認識され取り組みが進むことを祈りながら、自分にできることを続けていきたいと思います。
※横浜女性フォーラムで、熊谷珠美さんとフォーラム相談員さんが企画されたグループがスタートします。→「性的な傷つきを体験した女性のためのセルフケア・グループそよら」
※FLCのグループも現在受付中です。→「トラウマを経験した女性のためのセルフケア・グループ」
おのくん(奥松島出身)はじめ、ほっと和ませてくれて、ありがとう♪