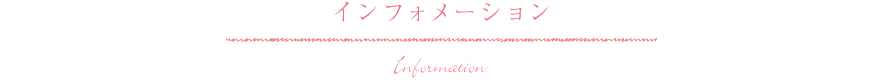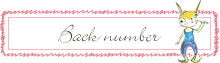2006年『立命館人間科学研究』第10号『立命館人間科学研究』第10号、pp.49-60 より
日本語版MTRR/MTRR-I導入のための予備的研究
トラウマの影響・回復・レジリエンスの多次元的査定
村本邦子(応用人間科学研究科)
1.MTRR/MTRR-Iの意義と日本語版MTRR/MTRR-Iの必要性
2.MTRR/MTRR-Iを支える理論的枠組み
3.日本語版MTRR-Iの作成とワークショップでの試用
4.日本語版MTRRデータの予備的分析
5.今後の課題
文献
A Preliminary Study to Introducing the Japanese Language Version of the MTRR/MTRR-I: Multidimensional Assessment of Trauma Impact, Recovery and Resilience
Kuniko Muramoto
Graduate School of Science for Human Services
Abstract:
This paper describes a recent effort to introduce Japanese clinical psychologists to the Japanese language version of the Multidimensional Trauma Recovery and Resilience measures developed in the United States by Harvey and colleagues (2003). The MTRR and MTRR-I were translated into Japanese and introduced to a group of Japanese clinical psychologists in order to gather pilot MTRR data on trauma survivors in Japan. Although the sample size limits the generalizability of the present study, the findings from a preliminary analysis of 27 cases provides promising results concerning the value of a Japanese language version of the MTRR. Future psychometric studies of the MTRR, parallel to American studies of the English language version of the measure, remain to be conducted. The current investigation opens the door to a series of multicultural studies on trauma impact and resilience. The author and her colleagues are currently awaiting more data to conduct further analyses.
keywords: Japanese language version of MTRR, trauma, assessment, recovery, resilience
本研究は、アメリカにおいてハーベイら(2003)によって開発された「トラウマの影響・回復・レジリエンスの多次元的査定:MTRR/MTRR-I」の日本語版導入の試みをまとめたものである。日本語に翻訳したMTRR/MTRR-Iを、日本の心理臨床家たちに紹介し、日本におけるトラウマ・サバイバーに関するMTRRのパイロット的データを集めた。現時点ではサンプルサイズが限定されており、一般化できない段階であるが、27ケースの予備的分析から、日本語版MTRRの価値が有望であることが導き出された。今後、英語版MTRRに関する心理測定的研究に倣って、基礎的データを集め、日本語版MTRRの標準化を試みる予定である。
キーワード: 日本語版MTRR、トラウマ、査定、回復、レジリエンス
1. MTRR/MTRR-Iの意義と日本語版MTRR/MTRR-Iの必要性
トラウマとその影響に関する研究は、欧米において、相次ぐ2つの世界大戦とベトナム戦争を契機に発展した。1980年、PTSD(外傷後ストレス障害)の概念が、DSM-IIIに初めて現れた。虐待、レイプ、DV、インセストの被害者に見られる症状も、戦闘帰還兵に見られるものと本質的に同じであるということが次第に明らかとなり、複数のタイプのストレス反応症候群が合流したところに、トラウマ心理学という新しい分野が生まれ、急速に知識が蓄積されていった。我が国においては、1995年の阪神淡路大震災を契機に、自然災害、犯罪被害への「心のケア」という形で、また、少子化対策と連動する形での虐待問題のクローズアップ、国際的潮流を受けてのドメスティック・バイオレンスへの取り組みなど、90年代後半から、トラウマが脚光を浴びるようになり、今や、一種の流行とさえ思われるほどである。
他方、トラウマとその影響については、未知の部分が多いことも事実である。たとえば、トラウマとなる経験が単回のものか、長期にわたって繰り返され、慢性化したものかによって、臨床像が違ってくることが指摘されている(Carlson, 1997)。慢性化したトラウマを受けた人の方が、解離やその他の自己催眠状態、気分の変動を生じやすい (Terr, 1991)、子ども時代の身体的虐待、性的虐待を経験した人々では、攻撃性の形をとった強烈な感情の再体験が観察され、解離という回避症状が現れる(Chu & Dill, 1990; Irwin, 1994; Kirby, Chu & Dill, 1993)、抑鬱、自己評価の低さ、無力感といった二次的な関連症状も、長期にわたる慢性的なトラウマと関係している(Briere, 1992; Yama, Tovey & Fogas, 1993; Finkelhor, 1990)などが指摘されている。DSMのPTSDは、再体験、麻痺・回避、過覚醒の3症状群から構成されたきわめてシンプルな診断名であり、PTSDで括りきれないこれらさまざまな症状は、トラウマ関連症状として認識されているのみである。DSM-IVにおいてPTSD概念の修正を検討したプロジェクトチームのメンバーの中には、これらの症状を記述し、複雑性PTSD (Herman, 1992)、もしくはDESNOS (Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified) (van der Kolk, Pelcovitz, Roth, Mandel, McFarlane & Herman, 1996)との診断名を用いる者も出てきた。
トラウマ研究の発展には、当然、トラウマ査定が含まれている。既存のトラウマ査定法には、さまざまなトラウマ曝露の頻度や程度に焦点をあてたもの(Briere & Runtz, 1988a, 1988b; Falsetti, Resnick, Kilpatrick, & Freedy 1994; Gallagher, Flye, Hurt, Stone, & Hull, 1992; Sanders & Becker-Lausen, 1995など)、DSM-III-R やIVによって定義されたPTSDを査定するもの(Blake, Weathers, Nagy, Kaloupek, Charney & Keane,1995; Briere, 1995; Foa, Riggs, Dancu, & Rothbaum, 1994; Keane, Mallow, & Fairbank, 1984など)の他にも、不安、うつ、解離、その他の精神症状に関する標準化された尺度を用いて、トラウマ関連症状を査定するものもある(the Beck Depression Inventory, Beck, 1988; the Dissociative Experiences Scale, Bernstein and Putnam, 1986など)。上述した広範囲にわたるトラウマ関連症状を含む症状を自己評定式尺度以外の尺度で捉えようとの試みも展開している。SIDE(The Structured Interview for Disorder of Extreme Stress)は、長期にわたるトラウマ曝露の影響と、新しい診断名であるDESNOSの妥当性を査定するために開発されたものである(Pelcovitz, van der Kolk, Roth, Mandel, Kaplan and Resick, 1997)。
我が国においては、トラウマ関連の査定尺度として、標準化されたIES-R (Impact of Event Scale-Revised)(Weiss and Marmar, 1997; Asukai, Kato, Kawamura, Kim, Yamamoto, Kishimoto, Miyake & Nishizono-Maher, 2002)、および、CAPS (Clinician-Administered PTSD Scale) (Blake, Weathers, Nagy, Kaloupek, Gusman, Charney, & Keane, 1995; 飛鳥井・廣幡・加藤・小西、2003)がもっぱら用いられている。IES-Rは、自己評定式の質問紙尺度であり、PTSDを構成する症状22項目について、過去1週間にこれらの症状がどの程度で経験されたかを5段階で評価し、合計得点によって症状評価を行うものである。他方、CAPSは、PTSDを構成する17症状について、調査者が構造化されたインタビューを行い、過去1ヶ月の強度と頻度を5段階評価するものである。いずれも、PTSDの症状を査定する尺度であり、上述してきたようなPTSD以外のトラウマ関連症状を測ることができないことが難点である。
トラウマによる苦痛や心理的損傷について明らかにされつつある一方、トラウマ・サバイバーがトラウマ経験に反応する肯定的方法、治療的介入の有無を問わず、回復する力を表すレジリエンスについての研究が始まっている(Grossman, Cook, Kepkep, & Koenen, 1999; Lam & Grossman, 1997; Liem, James, O'Toole & Boudewyn, 1997; Tedeschi, Park & Calhoun, 1998)。レジリエンスとは、回復や復元力、困難をはね返す力などを意味するが、現在のところ定訳はまだなく、そのまま片仮名で使用されることが多い。たとえばアメリカ心理学会は、「APAヘルプセンター」という市民向けホームページで、レジリエンスとは、「逆境、トラウマ、悲劇、脅威、大きなストレスに直面しながらも、うまく適応していくプロセスであり、困難な経験をはね返すことを意味する」と説明している(http://helping.apa.org/featuredtopics/feature.php?id=6)。成人したトラウマ・サバイバーのレジリエンスに関する最近の研究によれば、レジリエンスの表れは多面的、かつ複雑であり(Chambers & Belicki, 1998; Grossman, Cook, Kepkep & Koenen, 1999; Lam and Grossman, 1997; Liem, James, O'Toole and Boudewyn, 1997)、トラウマ・サバイバーは、機能の異なった領域で、傷つきやすさとレジリエンスの両方を示すことが示唆されている(Waysman, Salomon, & Schwartzwald, 1998)。
村本(2004)は、石川(2001、2002)らと実施した女性の性被害に関するコミュニティ調査のインタビュー結果を分析し、①女性の人生における性被害経験率はきわめて高い②性被害が女性の人生に与える影響は非常に大きい③性被害の長期的影響は認知されにくく、年齢の低いときの被害ほど認知されない④能動的対処の有無と、被害体験を話し受けとめてもらえたかどうかの2要因が、性被害の影響を減ずるために貢献する⑤子ども時代のトラウマは新たなトラウマを招き、トラウマの複合が生じやすい⑥性被害はほとんど専門機関で相談されない⑦性被害を受けた女性は相談機関の充実を求めていることを明らかにし、性被害に対し有効な臨床的介入をするには、生態学的視点からのコミュニティ介入が必要であると結論した。たとえば、治療を求めない大半の被害者たちに、公共教育を通じて働きかけるなどである。また、治療的介入のなかった3事例を紹介し、レジリエンスを示唆するトラウマからの回復に影響を与える要因について考察している。トラウマの影響を全般的に捉え、レジリエンスの多様な表現を含めつつ臨床的介入を可能にするためには、トラウマ・サバイバーの臨床状態を査定する体系的な方法が必要である。
これに応えようとするのがMTRR/MTRR-I(Harvey, Westen, Lebowitz, Saunders, Avi-Yonah, & Harney, 1994; Harvey & Westen, 1996; )である。これらの尺度は、英語のほか、スペイン語、フランス語、ポルトガル語にも翻訳が試みられ、中央アメリカ、カナダのフランス語圏、オーストラリア、そしてアメリカ都心部と農村部出身のトラウマ・サバイバーの回復状態を査定するために使用され、心理測定研究やナラティブ研究においても、文化的に多様な臨床研究に用いられてきた(Harvey, Mishler, Koenen, & Harney, 2000)。その結果、MTRRは、いくつかの課題が残されているものの、臨床と臨床的研究の双方において、信頼性、妥当性、実用性の当初の基準に適っており、異なる回復段階にあるトラウマ・サバイバーたちを識別できることがわかっている(Harvey, Liang, Harney, Koenan, Tumamal-Narra & Lebowitz, 2003)。
筆者は、おもに女性と子どもを対象とした開業臨床を15年実践してきたが、クライエントの多くは、虐待やドメスティック・バイオレンス、性被害などのトラウマ被害者であった。1999年にMTRR/MTRR-Iと出会い、2000年に日本語に翻訳し、臨床場面での導入を試みた。トラウマ・サバイバーを査定し、治療計画を立てるさい、また、治療の途中や最後の治療効果を測るさいに有用であることを経験し、この間、MTRR/MTRR-Iについて知り関心を持った日本の臨床家たちからのコンタクトを受けてきた。日本語版MTRR/MTRR-Iを正式に翻訳し、標準化して日本の臨床家に紹介する必要性を強く感じてきた。本研究は、そのための小さな第一歩である。
2. MTRR/MTRR-Iを支える理論的枠組み
ハーベイ(1996)は、コミュニティ心理学の生態学的視点を用い、極度のストレスに対する反応を形づくる人、出来事、環境の相互作用に注目しながら、トラウマの影響に多次元的視点を与え、トラウマの影響、回復、レジリエンスは、相互に関連する8つの心理的経験領域にわたって多様に表現されることを記述した。このモデルでは、人間の心理的特性は、コミュニティという生態学的文脈で、もっともよく理解できるし、出来事への反応は、コミュニティで養われた価値、行動、技術、理解に照らすことでよく理解できると考える(Kelly, 1968, 1986; Koss & Harvey, 1991)。個人差を、人、出来事、環境の3つの要因の相互作用と考え、これら3つの要因は相互作用して、人とコミュニティの力動関係を決定し、それぞれに独自な回復の文脈をつくる。
トラウマの生態学的モデルでは、トラウマからの回復結果を4つに分け、回復の多次元的定義を提示する。トラウマ反応に対し、治療(臨床的援助)がある場合とない場合があるが、それぞれに、回復がある場合とない場合がある。したがって、回復結果は、①臨床的援助が他の要因と作用しあい、回復を助ける ②臨床的援助が回復を妨げ、損なう ③臨床的援助なしに回復がおこる(生態システムが回復力を支え、自然なサポート体制とコミュニティ資源が豊富にあるとき) ④時宜を得た適切な介入がなく、回復できない の4つとなり、図1のように示される。

図1 トラウマの生態学的モデル(ハーベイ、1996)
また、MTRRを構成する8つの心理機能と各領域における回復基準は以下のとおりである。
①記憶の再生への権限:回復の過程のある時点で、トラウマ・サバイバーがかつては思い出せなかったり、あるいは逆に、望みもしないのに勝手に意識に侵入してきたりした経験について、思い出す、思い出さないを自分で選択することができるようになる。
②記憶と感情の統合:記憶に伴う感情を感じることができ(もとの経験に伴った感情を現在感じる能力)、過去の記憶だけでなく、過去を思い出している現在、新たに生まれる感情を経験することができるようになる。
③感情への耐性と統制:経験できる感情の範囲と、困難な感情に持ちこたえ、扱える能力の程度を示し、トラウマ・サバイバーが幅広い感情に触れることができ、なおかつ、その感情の強烈さに耐えることができるようになる。
④症状管理:トラウマによって生じた認知と感情の混乱を予期し、管理し、収め、予防することができるようになること。この基準は、トラウマ症状が残っていることを前提にし、回復は、症状の軽減ばかりでなく、軽減しない症状を予期し、管理し、対処できれば達成されるものであると考える。
⑤自己評価:自分のことを配慮する経験(自分をケアする価値ある存在と見なす)と、自分をケアする能力(自分への配慮を行動レベルで表現できる)の両方を指す。回復のサインと治療目標は、サバイバーが健康的な仕方で自分の身の回りの世話をすることができるようになり、純粋に自分を配慮できるようになることである。
⑥自己の凝集性:思考、感情、行動の面で、自分自身を統合されたものと感じたり、断片化していると感じたりする程度を指し、かつてはひどく解離していた患者が、人生初期に極度の暴力に曝されていた結果として、自分が複雑な解離によって適応してきたことを理解し、それをコントロールできるようになったり、過去には、秘密と状況による仕切りによって人生を編成していたサバイバーが、世界にひとつの統合された自己表現をすることができるようになったりしたら、回復と考える。
⑦安全な愛着関係:他者との関係で、信頼、安全、継続的な関係を持つ能力を示し、信頼できる愛着関係を結び直したり、新たに結んだりする能力、関係のなかで自分の安全を交渉して確保できるようになる。
⑧意味づけ:トラウマを与えた過去を精算したり、棚上げしたりするのではなく、むしろ、過去のトラウマの影響について理解し、意味づけ、自分、他者、世界についての理解、希望、オプティミズムを求め続けることである。
それぞれの回復基準は、心理的機能の領域全体を表している。トラウマが起こり、トラウマ後の条件を形成していく個人の内的・外的資源、そして生態学的環境のあり方によって、これらの領域のそれぞれが、否定的影響を受ける場合もあれば、そうでない場合もある。ある領域が相対的に影響を受けずにすんだ場合、また、影響を受けた個人が、影響の少なかった他の領域の力を駆使して、別の領域の影響を修正した場合、そこにレジリエンスを見ることができる。そして、どの領域においてであっても、より望ましい状態へと変化した場合に回復を見ることができるとされる。
MTRRは、この生態学的枠組みで明確にされたトラウマの影響、回復、そしてレジリエンスの多次元的見解を駆使して構成された99項目からなるリカート式質問紙である。単独での使用も可能であるが、MTRR-Iとセットで使用することもできる。MTRR-Iは、単独で用いることもできるし、MTRRと併用して使用することもできる半構造のインタビュー・フォーマットである。MTRR-Iでは、8領域それぞれにおける個人の機能についての情報を集める。インタビュアーは、被験者に自由な流れで人生を語るよう求め、出身家族の背景、現在の家族関係、社会的関係、職業生活について尋ね、さらに、トラウマ歴とトラウマ後の症状の経験、それに対処する力、自分や他者に対する思考や感情、症状に対処し、時とともに変化するのに役立ったもの、未来について感じていることについて尋ねる。単独で使用する場合、MTRR-Iは、質問と分析によるナラティブの手法を加えることで、質的データを生み出す。訓練された研究者がMTRR-Iを用いてMTRRを評価すれば、治療過程における特定の時点で、トラウマ患者の治療前後の状態を評価できるばかりでなく、異なる時、異なる回復段階にいるトラウマ・サバイバーの多次元的プロフィールを含む量的データを生み出すことができる。
3. 日本語版MTRR-Iの作成とワークショップでの試用
まれた(注1)。この機会を、日本語版MTRR/MTRR-Iを作成し、将来的な標準化を目指す第一歩とするべく、あらためて正式な翻訳作業を行った。まず、翻訳家と臨床家の2人がペアとなり、MTRR/MTRR-Iを日本語に訳した。それをバイリンガルの日本人が英語に戻し、オリジナルの英語との違いを吟味して、改良を加えた。できあがった日本語版MTRRを6人の臨床家が実際のクライエントにあてはめ使用を試した上で、わかりにくい部分をさらに改良した。最後に、MTRRワークショップ前日に、MTRR/MTRR-I作成者であるハーベイ氏とワークショップ協力者8名が集まり、日本語版MTRR/MTRR-Iの最終確認を行った。最終的に、表現が曖昧で誤解を生む可能性があると考えられた2項目について、話し合いの後、修正の工夫が加えられた(注2)。
ワークショップは、「トラウマの影響・回復・レジリエンシー査定のための多次元アプローチ~MTRR/MTRR-I、2つの新しい尺度の紹介」と題して開催された。30名定員の少人数による1日ワークショップであったが、シンポジウム関係者を含め、計46名の臨床家が参加した。ハーベイ氏による「MTRR/MTRR-Iの 理論的枠組みと事例紹介」の講義から始まり、「MTRR/MTRR-I記入と議論(文化差の考慮)」、「MTRR使用の実際 (アセスメント・治療計画)」のワークをはさんで、再び、ハーベイ氏による「さまざまな回復の次元・段階における治療的アプローチ」の講義を経て、「MTRR/MTRR-Iの使用可能性」について議論の時間を取った。ワークの部分では、参加者に日本語版MTRR/MTRR-Iを配布し、ワークにおいて、自分が関わっているトラウマ・サバイバーを思い浮かべ、日本語版MTRR/MTRR-Iを用いた評定を行ってもらった。
これらの経験に基づいて、議論の部分では、ハーベイ氏の他に、甲南大学の羽下大信氏、兵庫教育大学の冨永良喜氏と筆者が加わり、フロアも交えて議論し、日本語版MTRR/MTRR-Iの可能性について検討した。日本においても、MTRRが、IES-RやCAPSでは捉えきれないトラウマが与える影響を多次元的に捉える可能性があること、複雑性PTSDを査定する有望なツールになること、トラウマによって損傷を受けた機能とそうでない機能とを明確にすることで、治療方針を立てるさいの指針となることなどが確認された。また、経験の浅い臨床家の訓練にも有効なのではないかということが示唆された。トラウマ治療の経験が浅い臨床家では評定できない空白部分が多くなり、必要な情報が聞けていないのではないかと想定されたためである。日常の臨床にMTRRを導入することで、自身が普段、十分な関心を注げていない欠損領域やレジリエンスを意識することができるようになるだろう。
他方、翻訳の難しさや文化差についても議論された。たとえば、英語における"emotion"、"feeling"、"affect"などの使い分けは、必ずしも、日本語にうまく一対一対応していないことが指摘されたが、ハーベイ氏のコメントは、英語でもこれら3つを厳密に区別しているわけではなく、十分に重複する概念であることから、その部分に神経質にならなくても良いのではないかとのことだった。また、「恥」や「罪」という文化的価値の影響が、自己評価に違った影響を及ぼすのではないだろうかとの意見もあった。全般に外向的でボランティアや社会活動が盛んなアメリカと、どちらかと言えば内向的な日本人とでは、「意味づけ」を測る項目内容が違うのではないかとの批判もあった。その他、アジア人では、トラウマの影響が身体化される傾向が強いため、身体的な訴えをチェックする項目を増やし、とくに、自己の凝集性を表す領域に入れるのが適当ではないかとの意見もあった。ハーベイ氏からは、MTRRの基本的理解が得られたら、日本の臨床家たちの経験に基づいて、項目を削除したり、付加したりということを自由にやって欲しいと柔軟な姿勢が示された。
なお、このワークショップにおいて、日本語版MTRR作成のための研究協力が呼びかけられた。実際のクライエントを対象に評定したデータ提供の依頼である。ハーベイ氏からは、この研究方法が、アメリカ心理学会倫理委員会の審査を経たものであること、すなわち、数値としてのデータ提供は守秘義務に反するものではなく、倫理的問題を含まないことが説明された。なお、アメリカにおいては、どんな研究も倫理委員会の審査を経ずに行われることは許されていない。これらの手続きの結果、日本語版MTRRを用いた27人分の評定データ得られた。
4. 日本語版MTRRデータの予備的分析
評定の対象となった27人の性別構成は93%が女性、7%が男性であった。平均年齢は32歳(レンジは14-51歳)、治療平均年数は26ヶ月(レンジは1-120ヶ月)だった。ただし、5人は治療的介入を受けておらず、1人は不明であったため、治療平均年数の集計に含まれていない。治療的介入を受けていない5ケースは、評定者が治療者として関わったトラウマ・サバイバーではなく、個人的つながりのあるサバイバーを評定対象として選んだ結果であると推測される。経験されたトラウマのタイプとしては、子ども時代の身体的虐待経験者が48%、性的虐待経験者が44%、成人後のレイプ経験者が29%、配偶者・パートナーからの暴力経験者が33%、トラウマとなるような喪失体験を持つ者が30%であり、多くが複数のトラウマを経験していた。回復に関して評定者自身の評価を3段階で尋ねた結果、15%が「ほぼ完全に回復」、65%が「部分的に回復」、19%が「ほとんど回復していない」と評価され、1名のみ不明(未記入)であった。
表1は、回復状態別にMTRRの得点を表したものである。なお、スコア平均値のあとにある括弧内の数値は、比較のために、アメリカにおける研究データ(Harvey, Liang, Harney, Koenan, Tumamal-Narra & Lebowitz, 2003)を入れたものである。現時点ではサンプル数が小さすぎるため統計処理をしていないが、表1からは、すべての領域において評定者が評価した回復の程度とMTRR得点による回復状態の相関が推測され、評定者はどの領域においても、スコアの全範囲から幅広く評定していることがうかがえる。また、回復状態の違いによるスコアの拡がりは、領域Ⅷを除けば、すべて日本のデータにおいてより大きくなっているが、全般的に類似の傾向を見ることができる。領域Ⅷの得点が日本において全般的に低くなっていることは、回復を示す「意味づけ」の領域に何か文化差が存在することを示しているかもしれない。いずれにしても、サンプル数を揃えた上での統計処理が求められる。
表1 回復状態別のMTRRスコア平均値 (N=26)
| | 回復状態 | スコアの平均値
(アメリカのデータ) | スコアレンジ |
|---|
| 8領域の総計 |
1
2
3
|
3.94 (3.04)
3.04 (2.86)
1.94 (2.71)
|
3.60-4.24
2.45-3.56
1.80-2.10
|
領域Ⅰ
記憶の再生への権限 |
1
2
3
|
4.16 (3.12)
3.19 (3.03)
1.75 (2.90)
|
3.73-4.55
2.38-4.45
1.50-2.09
|
領域Ⅱ
記憶と感情の統合 |
1
2
3
|
3.88 (3.60)
2.77 (3.27)
1.78 (3.20)
|
3.20-4.50
1.60-4.00
1.40-3.20
|
領域Ⅲ
感情への耐性 |
1
2
3
|
4.32 (3.24)
3.00 (3.17)
1.78 (3.04)
|
3.93-4.27
2.13-4.13
1.60-2.00
|
領域Ⅳ
症状管理 |
1
2
3
|
3.62 (3.11)
3.02 (2.95)
2.25 (2.65)
|
2.88-4.33
2.33-3.67
1.75-2.67
|
領域Ⅴ
自己評価 |
1
2
3
|
4.13 (2.80)
3.29 (2.62)
2.06 (2.62)
|
3.27-4.60
2.50-4.20
1.38-2.43
|
領域Ⅵ
自己の凝集性 |
1
2
3
|
4.29 (2.44)
3.33 (2.68)
1.78 (2.62)
|
4.00-4.63
1.33-4.57
1.25-2.50
|
領域Ⅶ
安全な愛着 |
1
2
3
|
4.18 (3.13)
3.16 (2.75)
2.31 (2.67)
|
3.73-4.61
2.29-4.12
1.78-3.07
|
領域Ⅷ
意味づけ |
1
2
3
|
2.97 (3.22)
2.53 (2.77)
1.47 (2.34)
|
2.33-3.40
2.00-3.20
1.07-1.83
|
回復状態:1=ほぼ完全に回復 2 =部分的に回復 3=ほとんど回復していない
図2は、回復別比較の例として、回復のそれぞれの段階における8領域総計の平均にもっとも近い平均得点を得た対象を各回復段階から1人ずつ選び出し、それぞれの領域の得点を示したものである。評定者によって、「1=ほぼ完全に回復した」と評価された群から選び出されたNo.10は、トラウマとなる喪失を経験し、個人療法とグループ療法を10年にわたって受けてきた51歳女性である。「2=部分的に回復した」と評価された群から選び出されたNo.24は、子ども時代の性的虐待を経験し、7ヶ月の個人療法を受けてきた28歳の女性である。「3=ほとんど回復していない」と評価されたNo.14は、子ども時代の身体的虐待と、配偶者・パートナーからの暴力を経験し、個人療法、グループ療法、薬物療法を6ヶ月受けてきた38歳女性である。
図2を見る限りでは、回復状態と各領域得点は全般的に相関の傾向を示しながらも、それぞれの対象者が、ある領域では高いスコアを示し、別の領域では低いスコアを示していることがわかる。ここから、これらの結果がトラウマの多次元的影響とレジリエンスを示唆するものと考えることができる。たとえば、「部分的に回復」とされたNo.24のケースでは、Ⅱ領域(記憶と感情の統合)とⅧ領域(意味づけ)において、いまだトラウマの否定的影響が見られるが、Ⅰ領域(記憶の再生への権限)とⅥ領域(自己の凝集性)においては回復、もしくはレジリエンスの存在を示唆している。なお、ここでも、Ⅷ領域(意味づけ)における落ち込みが見られ、ワークショップの議論のなかで出てきた、全般に外向的でボランティアや社会活動が盛んなアメリカと、どちらかと言えば内向的な日本人とでは、「意味づけ」を測る項目内容が違うのではないかとの批判を支持する結果と仮定することができるかもしれない。

図2 3人の評定対象者のMTRRスコア
なお、今回、意図せず、治療を受けたことのない対象者のデータが5人分回収された。彼らの回復の状態は、1人が「ほぼ回復していない」、1人が不明であるが、3人は「部分的に回復」とされており、レジリエンスの存在を示唆するものとして興味深い。
5. 今後の課題
今回の報告は予備的なものであり、十分なデータを集め、日本語版MTRRの信頼性と妥当性を検討することが求められる。今後、ハーベイら(Harvey, Liang, Harney, Koenan, Tumamal-Narra &Lebowitz, 2003) の研究に従って、日本語版MTRRの評価者間一致度、および、MTRR/MTRR-Iの内的一貫性と構成妥当性について検討していく予定である。その上で、MTRRは、臨床評価や治療結果を査定するためのツールとしてのみならず、トラウマからの回復とレジリエンシーについて仮説検証するツールとしても使うことができると考えられる。とくに、トラウマが与える影響の文化差比較研究や、臨床的介入を得て回復していくトラウマ・サバイバーと、臨床的介入を経ず、非公式のコミュニティ資源を利用しながら回復していくトラウマ・サバイバーを比較し、それぞれに有効なコミュニティ資源を特定していくことも重要である。最終的には、我が国の文化的土壌に即した査定ツールとしての改良も必要かもしれない。また、ハーベイらの示唆(Harvey, Liang, Harney, Koenan, Tumamal-Narra &Lebowitz, 2003)のように、MTRR-Iを使用したナラティブ・アプローチによる質的研究の道も開かれるだろう。
MTRRが基盤としているトラウマからの回復モデルは、ハーマン(Herman, 1994)によって示された回復の三段階モデルである。これまで、エビデンスに基づくトラウマ治療は、認知行動療法とEMDRに偏っていた。これは、症状の有無を測る査定ツールしかなかったことに由来するところが大きく、MTRR/MTRR-Iの使用によって、これまでエビデンスを示しにくかった精神力動的アプローチの有効性が示されることになるだろう。他方、人格変容を含むとされる複雑性PTSDの治療モデルは、当然ながら、その社会が持つ「健全な人格」の基準と切り離せないものとなる。これは、心理療法を超える問題を提起する。今後の課題として、順を追って、取り組んでいきたい。
文献
Asukai, N., Kato, H., Kawamura., N., Kim. Y., Yamamoto, K, Kishimoto, J., Miyake, Y., & Nishizono-Maher, A .(2002). Reliability and validity of the Japanese-language version of the Impact of Event Scale-Revised: four studies of different traumatic events. Journal of Nervous and Mental Disease. 190, 175-182.
飛鳥井望・廣幡小百合・加藤寛・小西聖子. (2003). CAPS日本語版の尺度特性.『トラウマティック・ストレス』1(1), 47-53.
Beck, A. T. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review. 8, 77-100.
Bernstein, E. M. & Putnam, F.W. (1986) Development, reliability and validity of a dissociation scale. Journal of Nervous and Mental Disease. 174, 727-735.
Blake, D. D, Weathers, F. W, Nagy, L. M, Kaloupek, D. G, Gusman, F. D, Charney, D. S, & Keane, T. M. (1995). The development of a Clinician-Administered PTSD Scale. Journal of Traumatic Stress. 8(1), 75-90.
Briere, J. (1992). Child abuse trauma: Theory and treatment of the lasting effects. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Briere, J. (1995). Trauma Symptom Inventory: Psychometrics and association with childhood and adult victimization in clinical samples. Journal of Interpersonal Violence, 10, 387-401.
Briere, J. & Runtz, M. (1988a). Symptomatology associated with childhood sexual victimization in a nonclinical adult sample. Child Abuse & Neglect, 12, 51-59.
Briere, J. & Runtz, M. (1988b). Multivariate correlates of childhood psychological and physical maltreatment among university women. Child Abuse & Neglect, 12, 331-341.
Carlson, E. B. (1997). Trauma assessments: A clinician's guide. New York: The Guilford Press.
Chambers, E. & Belicki, K. (1998). Using sleep dysfunction to explore the nature of resilience in adult survivors of childhood abuse or trauma. Child Abuse & Neglect, 22, 753-758.
Chu, J. A., & Dill, D. L. (1990). Dissociative symptoms in relation to childhood physical and sexual abuse. American Journal of Psychiatry, 147, 887-892.
Falsetti, S. A., Resnick, H. S., Kilpatrick, D. G., & Freedy, J. R. (1994). A review of the "Potential Stressful Events Interview": A comprehensive assessment instrument of high and low magnitude stressors. The Behavior Therapist, 17, 66-67.
Finkelhor, D. (1990). Early and long-term effects of child sexual abuse: An update. Professional Psychology: Research and Practice, 21, 325-330.
Foa, E.B., Riggs, D. S., Dancu, C.V., & Rothbaum, B.O. (1994) Reliability and validity of a brief instrument for assessing post-traumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 6, 459-473.
Gallagher, R. E., Flye, B. L., Hurt, S. W., Stone, M. H., & Hull, J. W. (1992). Retrospective assessment of traumatic experiences (RATE). Journal of Personality Disorders, 6, 99-108.
Grossman, F.K., Cook, A.B., Kepkep, S.S., & Koenen, K.C. (1999). With the pheonix rising: Lessons from ten resilient women who overcame the trauma of childhood sexual abuse. San Francisco: Jossey-Bass.
Harvey, M.R. (1996) An ecological view of psychological trauma and trauma recovery. Journal of Traumatic Stress, 9 (1), 3-28. メアリー・ハーベイ.(1999). 生態学的視点から見たトラウマと回復.『女性ライフサイクル研究』9, 4-17.
Harvey, M.R., Westen, D., Lebowitz, L., Saunders, E., Avi-Yonah, O., & Harney, P.A. (1994). Multidimensional Trauma Recovery and Resiliency Interview. Unpublished Manuscript.
Harvey, M. R. & Westen, D. (1996). Psychometric review of Multidimensional Trauma Recovery and Resiliency Measures: The MTRRI (interview) and the MTRRQ (sort). In: B.H. Stamm (Ed.), Measurement of stress, trauma, and adaptation. Lutherville, MD: Sidran Press.
Harvey, M.R., Mishler, E. G., Koenen, K.C., & Harney, P.A. (2000). In the aftermath of Sexual abuse: Making and remaking meaning in narratives of trauma and recovery. Narrative Inquiry, 10(2)-291-311.
Harvey, M.R., Liang, B., Harney, P.A., Koenan, K., Tumamal-Narra,P., and Lebowitz, L. (2003) A multidimensional approach to the assessment of trauma impact, recovery and resilience: initial psychometric findings. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 6 (2), 87-109.
Herman, J. L. (1992). Trauma and recovery. New York: Basic Books.
Irwin, H. J. (1994). Proneness to dissociation and traumatic childhood events. Journal of Nervous and Mental Disease, 182, 456-460.
石川義之(2001)『性的虐待の被害者についての調査研究』女性のトラウマを考える会.
石川義之(2002)『性的虐待の現在』女性のトラウマを考える会.
Keane, T. M., Malloy, P. F., & Fairbank, J. A. (1984). Empirical development of an MMPI Subscale for the assessment of combat-related posttraumatic stress disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52, 888-891.
Kelly, J.G. (1968). Towards an ecological conception of preventive interventions. In J.W. Carter (Ed.), Research contributions from psychology to community mental health. New York: Behavioral Publications.
Kelly, J.G. (1986). An ecological paradigm: Defining mental health consultation as a preventive service. In J.G. Kelly & R.E. Hess (Eds.), The ecology of prevention: Illustrating mental health consultation. New York: Haworth Press.
Kirby, J. S., Chu, J. A., & Dill, D. L. (1993). Correlates of dissociative symptomatology in patients with physical and sexual abuse histories. Comprehensive Psychiatry, 34, 258-263.
Koss, M.P., & Harvey, M.R. (1991). The rape victim: Clinical and community interventions. Newbury Park, CA: Sage.
Lam, J.K. & Grossman, F. K. (1997). Resiliency and adult adaptation in women with and without self-reported histories of childhood sexual abuse. Journal of Traumatic Stress, 10, 175-196.
Liem, J. H., James, J.B., O'Toole, B.A., & Boudewyn, A.C. (1997). Assessing resilience in adults with histories of childhood sexual abuse. American Journal of Orthopsychiatry, 67, 594-606.
村本邦子(2004). 性被害の実態調査から見た臨床的コミュニティ介入への提言.『心理臨床学研究』22(1) ,47-58.
Pelcovitz,D., van der Kolk, B., Roth, S., Mandel, F., Kaplan, S., & Resick, P. (1997). Development of a criteria set and a structured interview for disorders of extreme stress. Journal of Traumatic Stress, 10, 3-16.
Sanders, B., & Becker-Lausen, E. (1995). The measurement of psychological maltreatment: Early data on the child abuse and trauma scale. Child Abuse and Neglect, 19, 315-323.
Tedeschi, R. G., Park, C. L., & Calhoun, L. G. (1998) Posttraumatic growth: Positive changes in the aftermath of crisis. Volume VII: The LEA Series in Personality and Clincial Psychology. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Terr, L. C. (1991). Childhood traumas: An outline and overview. American Journal of Psychiatry, 148, 10-20.
van der Kolk, B.A., Pelcovitz, D., Roth, S., Mandel, F.S., McFarlane, A., & Herman, J.L. (1996). Dissociation, somatization, and affect dysregulation: the complexity of adaptation of trauma. American Journal of Psychiatry, 153, 83-93.
Waysman, M., Solomon, Z., & Schwarzwald, J. (1998). Long-term positive changes following traumatic stress among Israeli prisoners of war. [Hebrew]. Megamot, 39 (1-2), 31-55.
Weiss, D. S., & Marmar, C. R. (1997). The Impact of Event Scale-Revised. In J. P. Wilson & T. M. Keane (Eds.), Assessing psychological trauma and PTSD. New York: Guilford Press.
Yama, M. F., Tovey, S. L., & Fogas, B. S. (1993). Childhood family environment and sexual abuse as predictors of anxiety and depression in adult women. American Journal of Orthopsychiatry, 63, 136-141.
(注1)2004年6月25~28日、立命館大学衣笠キャンパスにて、日本コミュニティ心理学会第7回大会を主催した。日本学術振興会海外研究員短期招聘助成、立命館大学国際集会助成を受け、立命館大学応用人間科学研究科の共催で、「他領域で支える暴力被害者支援を目指して」をテーマに、ボストン・ケンブリッジ病院VOV(暴力被害者支援)プログラムディレクター、コミュニティ心理学者であるメアリー・ハーベイ氏と、弁護士のオリバー・フォークス氏を招き、ワークショップ、講演、シンポジウムを開いた。うち、講演とシンポジウムの内容に関しては、日本コミュニティ心理学会の機関誌である『コミュニティ心理学研究8巻1号』に報告掲載したが、本稿は、ワークショップの報告を兼ね、日本語版MTRR/MTRR-Iの紹介をしたものである。
(注2)こうして作成された日本語版MTRR/MTRR-Iは、/info/2014/04/000153.phpから入手できる。