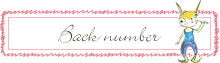- 1993.11.23 年報『女性ライフサイクル研究』
- 「もつれ」 女性の発達における食物、性、攻撃性
ポリー・ヤング・アイゼンドラス、Ph.D.
食物、性、攻撃性は人間の生活の基本的な3つの側面である。人間は長期にわたって栄養を貯めてお くことはできないので、生きていくためにはしょっちゅう食べなければならない。性的な表現は、生殖の手段であると同時に、重要なコミュニケーションの手段 でもある。攻撃性というのは、私たちそれぞれが他者に対して自分自身の欲求を通そうとする手段であると私は定義している。
北米やヨーロッパ社会では、これら人間の経験の基本的側面にそれぞれ、男性的とか女性的という特徴が割り当てられている。生まれた赤ん坊が女の子か男の 子か、解剖学的なサインが読み取られた瞬間からそういうことが起こる。食物、性、攻撃性に関して、女と男には、意味、特権、力についての異なるカテゴリー が振り当てられる。女にとって、人生を構成するこれら3つの要因はしばしばひどくもつれあっていて、自分が食物、あるいは性に飢えているのかどうかわから なくなることがある。食べている時に「自分を攻撃しているのか」それとも「栄養をつけているのか」わからなくなるし、パートナーが自分の体に要求してくる ものが性的なものなのか、それとも攻撃的なものなのかについても同様である。以下に、とくに女性の発達と関わるジェンダーについての私独自の理論を要約す るが、さしあたって、ジェンダーが、私たちの存在の基盤である体、性、自己感覚を形成していくうえで強力なカテゴリーとなることを強調しておこう。
摂食障害を扱う臨床家の多くはいまだに、クライエントの体験のうちのジェンダーに関する側面を深刻に受けとめてはいない。そのため、治療のなかでジェン ダーについての考慮を統合することができない。フェミニストによる重要な文献(たとえば、Orbach, 1979, 1986; Chernin, 1981, 1986; Wooley & Wooley, 1979; Wolf, 1991)では、女性を外見と痩身に没頭するよう駆り立てている広範にわたる特有の社会文化的要因の検証が展開されてきたが、これらの特徴を念頭において 議論された特定の事例はほとんど聞いたことがない。それをすれば、ピア・グループ(同年齢集団)、家族あるいはコミュニティにおけるジェンダーとその発達 という見地から、クライエントの考えと行動を捉えていくことができるのだが。
臨床家たちは摂食障害についての議論からジェンダーを排除するかもしれないが、フェミニストの学者や研究者は、無意識の問題、言い換えれば、投影や投影 的同一化といったジェンダーの意図せぬ側面について排除することがしょっちゅうである。これらが、身体イメージとセクシュアリティについての女性の関心に 影響を与えているのである。フェミニストでありユング派の分析家である私は、これらの視点を結合させることが役に立つと思っている。ここでは事例を素材に 議論するなかで、この2つの視点を使うつもりである。文脈を明らかにするために、これら2つの視点について簡単に述べておこう。
私は、フェミニズムが市民権運動であると同時に、大人のあいだの平等で相互的な関係を促進することを目指す思考と行動の修練の場であると考えている。 フェミニズムは、女か男かということがもつ意味と影響、とくに平等で相互的な関係を妨げるようなそれに私たちの関心を集中させる。私の考えでは、女か男か の違いは、意志決定権、文化の創造、また日常生活でこれらが暗示するものの分野での力の違いの根っことなっている。
ここでユングの分析心理学について包括的な記述をすることはできないが、簡単に述べておくと、それはカール・ユングによって創立された分析の学派であ り、(夢、症状、神話といった)イメージと象徴に現れる無意識の意味を研究するものである。普遍的なものと個人的なものの緊張に光をあてると同時に、「女 性的なるもの」「男性的なるもの」についても説明していることで有名なので、ユング心理学はジェンダーについて議論するごく自然な場所であるように思われ るかもしれない。ここ十年来、私はユング派の同僚に対して、ジェンダーに関するフェミニズム分析を持ちかけてきた。反応してくれたのは、ごく少数だった。 私たちは、女と男の「本性」には普遍的な対比があるとする独自の発想からつくられた性別理論を、そこに刻々と働いている無意識的な意味という観点から男女 の違いを点検していくモデルに書き換えようと取り組んできた。ジェンダーはあらゆる人々に分割をつくりだす。心の中でも、また対人関係でも、自己と他者を 分けてしまうのである。この分割が、しばしば自分自身の行動を説明するのに使われる他者についての恐れや空想、理想化へと結びつく。心の中のことで言え ば、ジェンダーが、投影を引き起こす要因になるのである。
フェミニズムを摂食障害の臨床的な事柄についての精神力動的な説明とミックスさせると、ジェンダーの社会文化的意味と無意識の意味の両方に注目していく ことができる。摂食障害の無意識的、象徴的意味のいくつかに光をあてるために、ひとつの事例をあげ、補足的に他の摂食障害の女性たちの夢を示そう。それら は食物、性、攻撃性のもつれを表現する夢である。
【生きた象徴としての摂食障害】
これらのことに言及する前に、摂食障害を女性の抑圧の生きた象徴と見ることの重要性について一般 的なことを言っておきたい。後で見るように、摂食障害の女性の夢には無力感がしみわたっている。切迫した死の宣告と無力感の表現が、精神分析の文献に出て くる摂食障害のクライエントの夢の主なテーマである。(たとえば、Levitan, 1981; Sours, 1980; Thoma, 1967)。ジャーナリストであるナオミ・ウルフ(1991)は女の体につきつけられる現代の要求を「美の神話」と呼んでいるが、私は、これらのテーマが 「美の神話」から生じる苦悩の象徴であると考えている。ウルフは次のように言う。
美の神話が物語る。「美」と呼ばれる性質が客観的、普遍的に存在するのだ。女は美を体現したがらなくてはならないし、男は美を体現する女を所有したがらな くてはならない。美の体現は、男にではなく女に強制され、それが生物学的、性的、進化論的なものであるために、このような状況が不可避の自然なものとなっ ている。つまり、強い男は戦って美しい女を手に入れ、美しい女はさらに、強い男と美しい女を産み・・・このシステムが性的選択に基づいているために、それ は避けがたく、変化しない(p.12)。
この物語が、ある女の子や女性にとって深刻な精神病理に変わるには、特別な要因が関係しているが、北アメリカ、ヨーロッパ社会に住む多くの女性は、日常生活のなかで美が演じる避けがたい役割のいくつかの側面によって苦しめられている.
実際、美は普遍的なものでもなければ変化しないものでもなく(それは見る者の目のなかにあるという意味で)、人類学者たちは、しばしば美しい女性よりも 攻撃的な女性の方が生殖の方略では成功するということを示してきた。そのような事実と関わりなく、私たちの社会にいる女たちはみな、美は力なりという等式 に従っている。このことは、私たちの生活に関する否定できない心理学的側面である。私がどこにいようが、誰といようが、私たちは評価の枠組みに入れられ、 女性の容貌についてのコメントに漬からされている。女も男も、顔、脚、お尻、胸の形とサイズによって女を評価するのである。他の女たちのように、私もしば しば、容貌と力の結びつきを壊すことに絶望する。私自身、自分の体が変化し年老いることで自分の容貌がどのように変わろうと「自然な流れに身を任せる」の ではなく、「外見を保とう」と努力している自分に気づく。
ナオミ・ウルフ(1991)が言っているように、私たち女がこの20年間に築き上げてきた新しい自由と自己評価を毒する秘密の地下生命がある。彼女の言 葉で言えば、それは「自己嫌悪、肉体的な囚われ、老いることへの恐怖、支配力を失うことへの恐れといった暗い鉱脈」(p.10)である。摂食障害は美の神 話の苦痛と抑圧について私たちに語りかける。個々の女性が美は力なりの等式に関してダブル・バインドにあることを示しているのである。ある女性が自分を美 しい(ゆえに力がある)と見なしているとしても、年を取れば、どんなにすばらしい化粧と外科医の助けを得ても、それは結果的に失うことになる。その等式に 反対して、女の容貌に対する文化の基準に適応しないという意味で「なりゆきに任せる」ならば、文化の主流には、もしかしたらサブ・カルチャーにおいてさえ も自分の居場所を見つけだせないことになるだろう(いくつかの例外はあるが)。
女は美しく、同時に自由であることはできないので(老いていく過程で美の基準が自由を制限していく)、または女は(文化の基準に合わないという意味で) 「醜く」、同時に自由であることはできないので、美は力なりという等式の結果おこってくる精神病理から逃れる道はないのである。それは古典的なダブル・バ インドなのだ。
【ジェンダーと差異】
ジェンダー、そしてその無意識的な投影の構成要素を理解することなしに、摂食障害の症状と象徴を 理解することはできない。すべてではないが、あるフェミニスト理論家たちのように、私もセックスとジェンダーをはっきりと区別する。「性的差異」を意味す るセックスと言うとき、私は男と女の体の変えられない解剖学的、生物学的違いについて言っている。生涯を通じて、これらの違いはさまざまな形を取り、両性 間に強い憧れを生じさせる。いつでも、セックスは私たちの生殖生活、ホルモン/科学的機能の諸側面の絶対的な制限枠となる。でも、ここで私が興味を持って いるのはジェンダーの方なので、セックスの違いについてはこれ以上立ち入らないつもりである。ジェンダーと言うときは、私たちが誕生(あるいは時にはそれ 以前)からそれぞれに割り当てられ、生涯逃れられない役割と意味のカテゴリーのことを指している。「これは女か男か」を知りたいというどこにでもある欲望 が、実質的に私たちの相互関係のすべてを形づくる。つまり、すべての個人的な属性にこのレンズのフィルターがかけられる。文化、社会、家族が異なるとジェ ンダーについての意味と前提も異なるにもかかわらず、現代社会のほとんどはジェンダーが生物学に基づくものだと教えるのである。慈しみ育てることは女性的 な特性か男性的な特性か、あるいは男と女ではどちらが攻撃的に見えるかなどといったこれらの違いについての説明は、現代では生物学で語られる傾向にある。 以前は、これらの違いについて宗教的、あるいは神学的説明を受けてきたかもしれないのである(そして今もそうであることもある)。
あらゆるところで人間社会は、「対立物」と呼ばれ、敵対させられるふたつのグループに分けられる。成長しつつある子どものなかで「ジェンダー」カテゴ リーが明確にされるには長い時間がかかる。2才の子は絵のなかの人々のセックスを言うことができるし、3才の子はふつう自分が男の子か女の子かを言うこと ができる。でも、6才か7才にならなければ、子どもたちはジェンダーが排他的で永続するものであることを理解できないのである。学童期くらいになるまで は、子どもたちは、自分たちの人生が言わば「平等につくられている」という印象をもっている。髪、服、名前が変化するだけで違う性になれると考えるような のだ。学童期になると、子どもたちはついに「悟る」、つまり自分が永久にひとつの集団にとどまることを知るのである。この認識は、心理学者ローレンス・ コールバーグとその同僚(たとえばRuble, 1983をみよ)の研究に続く調査で「ジェンダーの恒常性」とうまく呼ばれている。
私たちはみな決して他の人にはなれないのだという結論に達すると、他者に不安をもったり他者を羨望や理想化し始める。ふつう、それは同性の友人やメディ アから得るステレオタイプと空想に基づいている。6才か7才の頃から子どもたちは、自分と同性のピア・グループに強烈な興味をもつようになる。子どもたち は自分について、他者について知りたいのである。心理学者エレアノア・マコービ(1990)は、ここ25年間の両性間の違いに関する調査を概観して報告し た。それによると、実際の能力、様式、態度には性の違いはほとんどないのに、私たちは、そこに重要な違いがあると信じる傾向がある。新しい世代の子どもた ちはそれぞれ、女の子と男の子で違いがあるという信念に反応して、互いを(そして、どんなにそれに抵抗する「解放された」両親をも)社会化するのである。 違いがあるという信念は、家で、遊び場で、学校で、メディアでと四六時中私たちのまわりにある。思春期はジェンダーの社会化にとって決定的な時期であり、 生涯のうちでもっともジェンダー役割が固定される唯一の時期である。
ジェンダーという線に沿って自己と他者が分割させられることは、いつでもはっきりと、あるいは曖昧な仕方で私たちに影響を及ぼす。ある属性が自己から排 除され、他者へと投影されるのである。女も男も学校で、遊び場で互いに出会うとき、これらの違いに効力を「強制し」、同性から学んできた恐れと空想を遊び で表現しようとする。私たちの社会では、女は判断を下すための権威を男と男性優位の制度(ほとんどがそうであるが)に投影する傾向がある。私たちの多く が、特定の力ある男性は知識も知性も、文化的、経済的資源をも備え、それらを私たちにいいように与えてくれるのだという前提で大きくなる。女たちはしばし ば、容貌や振る舞いの基準は周囲の男性によってもたらされるものだと想像する。つまり、彼が望むから私はこう見えなくちゃならないんだとか、こうしなけれ ば彼がやっていけないから私はこれらの仕事をしなくちゃいけないんだと考えるのである。図らずも、基準を決める権威が女性自身から排除されているのであ る。
【有能な女性アンジェラの事例】
すでに述べたように、美の神話はダブル・バインドであるから、自分の容貌の基準を男が決めてくれ ると女が想像するのに何の不思議もない。容貌の問題を処理したり、「うまくやる」ことはできないので、女性は心休まることがない。基本的にダブル・バイン ドは心が休まらないことを意味している。生物学者であり哲学者であるグレゴリー・ベイトソンとその同僚の研究から、ダブル・バインドが人々を狂わせるとい うことがわかっている。私が『女の権威-心理療法で女の力を強くする』(1987)を書いたとき、何百という女性たちの夢や臨床上の素材に見られるもうひ とつのダブル・バインドを発見した。私はそれを「女の権威のダブル・バインド」と名づけた。女性が自分の権威をいかに処理しようが、つまり、率直にそれを 要求し主張しようが、あるいはそれを放棄して他者の手に委ねようが、決まって、その扱い方は根本的に間違っている、たぶん病的なのだとまで言われることに なる。社会学者ブローバーマン、フォーゲルマンらによってなされて今では有名な研究(1972)によれば、このダブル・バインドは一般大衆や心理学者の幅 広い経験的研究に見られると報告されている。ベイトソンと彼の研究を引き続き行っている人々の言うことから、ダブル・バインドを扱うにはたったひとつの方 法しかないことがわかっている。それは、そのダブル・バインドの外へと完全に踏み出さなければならないということである。これをするためには、まずそれに 気づかなければならない。そのダブル・バインド性質を明らかにしなければならないのである。女たちは一生懸命頑張りさえすれば力を手にすることができると 信じるよう励まされるために、美の神話のダブル・バインドと女の権威のダブル・バインドは今もってうまく秘密にされたままである。
私は、私たちを陥れるダブル・バインドを暴露し、「うまくやる」ことなんてできないのだと主張したい。男性優位の社会に住む女たちは、満足と自尊心に 真っ直ぐ辿り着くことはできない。このことを認めれば、自分が行ってきた選択に自信と成功を感じやすくなる。
アンジェラは42才のクライエントで、摂食障害者のための住居施設に住んでいる。彼女は「うまくやる」ために非常に一生懸命やってきた。エクササイズ、 食事制限、嘔吐、魅力的な外見を保とうとすること。アンジェラも私たちの多くと同様、容貌を通じて個人的な力の感覚を維持しようとしている。彼女はまた暖 かく、配慮が行き届き、才能に満ちており、新しい夫とのコミュニケーションを改善したいと思っている。彼女は摂食障害の女性たちの無料のセルフ・ヘルプ・ グループを運営している。これまで、過食の治療を受けるために専門のセンターにも通ってきた。最近彼女は、娘をカウンセリングに連れて行き、その後自分も 心理療法を続けている。過去には別の治療も受けていた。彼女は才能に満ちた女性である。
これらのことに加えて、アンジェラは、キャッシャー、配膳の付添人としてフルタイムで働いていて、多くの義務と責任を持っている。病気やその他の理由で 仕事を休むことはほとんどない。彼女には家にいる20才の娘、21才の娘、17才の息子、脳性麻痺の養子、新しい義理の息子がいる。アンジェラは多くの役 割をこなすよう一生懸命やってきた。
フェミニズムの観点に立って、力の文脈で彼女の困難を理解するために、まず「コンピテンス・モデル」を通じてアンジェラを見てみよう。精神病理、精神力 動、症状に関する多くの伝統的見解は、何かが間違っており何かが足りないかでクライエントを見ていくことで、私たちのクライエントの「欠陥」を強化する。 欠陥を探すやり方でいくと、アンジェラの事例史、とくに小さい頃の家族歴の外傷体験を読んで、「彼女の人生は混乱しており、いつもそうだった。いったい救 いようがあるだろうか」ということになるだろう。
欠陥を探す方向づけでは、女の権威のダブル・バインドが強化される。女性クライエントは、もしこれやあれが間違っていたら、うまくやれていたのにと結論 するだろう。欠陥を探すようなやりかたで事例を調べていくと、女性たちは、両親、しばしばとくに母親が悪いのだという結論に至る。両親がそんなにも「無 能」でなければ、物事はもっとうまくいっていたのにと考える。心理学者キャロル・タブリス(1992)が新しい本『女についての間違った基準』のなかで非 常に力強く描いているように、欠陥を探すやり方では、女は男に基づく基準で自分の人生や体を測る。これらのモデルは暗に、いつだって誰もがうまくやること ができるということを前提にしているのである。
「コンピテンス・モデル」はクライエントの弱さやストレスを見過ごすことはしないが、同時に力を重視する。『女の権威』で示したモデルでは、コンピテン スは自分で認知している力だと定義した。コンピテンスとは力を主張し、自分や環境のなかにある資源としてそれを見なす能力である。アンジェラは責任感や内 省力(たとえば彼女は繰り返し、生まれてからこのかた感情を「いっぱい詰め込んできた」と言ってきた)など、たくさんの力を持っているにもかかわらず、た ぶん治療の初期にはほとんどコンピテンスを持たなかった。住み込みのセンターでの個人セラピー、グループ・セラピーを行った治療の終わり頃には、アンジェ ラは次のことをはっきりと自分のなかに認めたのである。それは、自分についての知識、人のことを配慮する能力、計画をたてたり組織化する技能、責任をとる ことである。これらのコンピテンスは、いつか自分が依存症のカウンセラーになるという目標に到達できるという信念を強めた。コンピテンス、つまり自分の力 を認めることは、しばしば中年女性の個性化へと通じる。
アンジェラの弱さについてはどうだろう? 弱さとは、コンピテンスを妨げる長期にわたる状況である。自己評価の低さ、主導権を握ることへの恐れ、無力感 との同一化、自分の女性性についての否定的レッテル貼り(たとえば操作的だとか依存的だとか、不安が強いなど)が、アンジェラの弱さの例であるが、これら は多くの女性に共通するものである。加えて、アンジェラは自分自身や自分の体を嫌悪し、自分には何の価値もないから自分には楽しむ権利がないと考える傾向 があるという点が、もっと深刻な問題だった。彼女が自分の人となりを受け入れ、ダブル・バインドが自分に及ぼしている影響と、自分が自分の人生にもたらし ているコンピテンスを受け入れられるよう、十分内面に取り組まなければ、自己嫌悪をコントロールするために彼女は食物、エクササイズ、嘔吐を利用し続ける だろう。
コンピテンスを調べる三番目のカテゴリーはストレス、つまりさしあたって特別な順応を要求する決定要因である。(外見上は)最後の1年に、アンジェラは 家を失い、ようやく信頼し始めた男に捨てられた(その1年前には二番目の夫にも捨てられていた)。そして三番目の男と結婚し、子どもたちを養子に出し、彼 とその息子の元へ引っ越した。彼女の母親は肉体的に弱って腎臓が機能しなくなり死が予想された。このようにたくさんのストレスがあると、誰でも、物事に対 処する能力が弱まり、徹底的な危機が訪れる。当然のように、アンジェラは月経周期に関係ない出血があったりした。これはしばしば閉経期の女性ではストレス のサインである。
アンジェラの場合、注目すべきことは、彼女が治療によく反応し、過剰なエクササイズと嘔吐をやめたことである。彼女は希望をつなぎながら困難に満ちた人 生に戻ったのだった。彼女の妹アイリスは34才だったが、生き続けることができず、ピストル自殺をした。この観点からアンジェラを見ると、彼女の精神病理 が仄めかされると同時に、個性化の可能性を見ることができる。アンジェラが自分のことを他者から愛されたり賞賛されるに値する統合された有能な女性である と見ることができるとき、ストレスが強く援助が受けにくい状態であっても、女であることと結びつく弱さの多くを補うことができるだろう。そうでなければ、 彼女は、自己嫌悪をコントロールするために、食物、エクササイズ、自己飢餓を再び利用するようになる。
アンジェラは子ども時代のトラウマ(心の傷)と貧困から精神病になる危険性があった。貧困で家族の人数が多い状態で大きくなった子どもの多くは、物質 的、教育的資源を欠くことと即結びつく性的虐待、身体的虐待に曝されている。私たちが(症状のみでなく)、逆境で育つ人々のパーソナリティにできてくる 「ストレスをはねかえす要因」や「防御要因」に注意を向ければ、コンピテンスがいかにストレスと弱さの埋め合わせをしているかがわかる。アンジェラの成育 史と治療から、私は、ひどい逆境にもかかわらずしっかりと生きている強い人々の話を思い出した。アンジェラはいつでも有能に直面してきたわけではなかった が、しばしばそうしてきたのである。
【食物、性、攻撃性】
ナオミ・ウルフが「ウェイト・コントロール崇拝」と呼ぶものは、女性の食べる量や体重を命じる権 威主義的構造への恐ろしいほど広範に見られる献身である。これが私たちの社会の女性のジェンダー・アイデンティティの一側面になっていることは、誰も無視 することができない。とくに思春期(どんどん年齢は下がっているが)、女の子たちはメディアや他の文化的影響によって、男の子たちに「受け入れられる」よ う自らを社会化する。この「受け入れられる」ということは、文化的な基準や、男の子が望んでいると女の子が想像するものを投影したものに基づいている。人 生半ばまで、女たちは、どのくらいの体重がふさわしいか、どのくらい食べたらいいかに気をとらわれるあまり、基本的な本能である食物に楽しみを見いだすこ とがほとんどできない。
容貌の基準に従うことは、しばしば、自分たちの権威を他者、とくに男に投影することで保たれる。心理学的に言えば、これは自分自身の身体イメージに責任 を持つことに対する防衛である。でも、女たちは実際身体イメージや健康や美を自由にコントロールできるだろうか。否、ダブル・バインドゆえに、文化の基準 に「従え」ば貶され、従わなくても貶されることになる。
加えて、私たちはみな男による女のイメージの洪水に襲われている。歴史的には美術や文学で、今はあらゆる種類の大衆メディアで。現代の新聞、雑誌の広 告、テレビ、その他のメディアに溢れる女性の体のイメージの渦を考えるがいい。かつては、女たちも、商品を売り空想を引き起こすために利用される女の体の 写真にいつもいつも曝されていたわけではなかった。写真革命以前、ほとんどの女性は女の体のイメージを見せつけられることは滅多になかったのである。とこ ろが今、私たちはみな、いつもイメージに溺れかけている状態である。
8百万のアメリカ女性が、ウェイト・ウォッチャーズ(体重監視)に登録している。アメリカでは毎週毎週1万2千ものクラスが開かれ、痩身というジェン ダーの意味を広め、強化している(ウルフからの引用、1991、p.125)。女も男も入り混じった家族、学校、職場にいたるまでどこでも、女の外見はし ばしば達成と責任に先立っているので、私たちの多くは痩せたいという欲求から逃れることができないと感じている。女子校とか女性グループのような同性同士 の場ですら、痩せていることは能力や支配感と結びつけられることが非常に多い。
アンジェラが食物を取ることができないのは、女性が食べる楽しみを自分に禁じているという広く見られる傾向を誇張したものである。食物を取ることは、楽 しい経験から喜びを引き出す能力と、嫌なことにも効果的に直面できるという能力を含んでいる。強い自己批判能力がありながら無力感を感じることが摂食障害 の女性に見られる(Brink & Allan, 1992, p.289)。これらの感情は次のような夢に表れている。これは摂食障害の若い女性の夢である。
私には赤ちゃんがいて、いつもそのことを忘れてしまう。赤ちゃんを外に置いてけぼりにして風邪をひかせてしまう。また赤ちゃんのことを忘れてしまったの で、ある時もうだめだと罪悪感を感じる。ママとパパに会ったら、彼らが赤ちゃんの世話をするのを手伝いたがっていたことを思い出す。とっても罪深く、赤 ちゃんのために悲しい気持ちになる。私はとても赤ちゃんを愛したい気持ちになるが、どうしてもうまくいかない。(Brink & Allan, p.290)
赤ん坊を忘れてしまうという夢を見た摂食障害の女性は彼女以外にいないが、夢のなかで赤ん坊の世話をしたり、忘れたことを償う方法を見つける夢はよくあ る。どの人も、自分に安全や不安を与え、自分を養うことを回避することを感じさせる傾向にある世話人との早期の関係パターンを内在化してしまっている。と 言っても、女性たちは、自由に食べたり、食欲と感情に基づいて食べ物を楽しむということに関して、尋常でない困難な環境に直面している。
痩身にたいする文化の規準がもっとも先鋭に感じられるのは、硬直した性的ステレオタイプが男性集団、女性集団を支配する思春期である。私たちの多くは思春 期の基準を永久に持ち続けるので、この発達期間は摂食障害の女性を治療するさいに徹底的に理解される必要がある。思春期はまた、食物と性のもつれが、セク シーでありたいという感情と痩身を混同し始める時期でもある。
異性愛の女性の最近の経験では一般に、性的歓びの女性本来の能力(たとえば複数のオーガズムやクリトリス・オーガズムの得やすさなど)が反映されていな い。専門家によるものでも、大衆的なものでもほとんどの調査で、異性愛の女性は性的欲望の低さ、しばしば喜びの低さが報告されている(Young- Eisendrath, 1993, pp.374-75)。
思春期の女の子たちは自分自身の欲望や歓びからでなく、自分たちがいかに「欲望の対象」にならなければいけないかという点から、性に導き入れられる。それ 以前になされていなければこの時点で、痩身が定式の主な構成要素となる。コントロールの感覚が男の欲望の対象になることに組み込まれる。つまり、食事をコ ントロールすれば、私は力を持ち、性的であることができるのだ。ここで「性的である」という定式は、自分の歓びを選び、感じ、遂行する、自分自身の欲望の 主体であることとは関係がない。ウルフ(1991)は、とくに広告、テレビ、映画が女性のセクシュアリティに及ぼす影響について強調する。彼女によれば、
女の子たちは男の子といっしょになって、自分の性を見張ることを学ぶ。そのため、本来ならば、自分が欲するものを探したり、それについて読んだり書いたり したり、求めて得ることに費やすべき空間がなくなってしまう。性は美の人質となり、女の子たちの心の奥に早くから身代金という言葉が刻み込まれる。 (p.157)
自分自身の性的歓びを学んでいないから、私たちは、パートナーに教えることができない。女性のセクシュアリティについて男性の視点から(女性の視点から はほとんどまったくと言っていいほどない)あまりにもたくさんのイメージを受け取りすぎて、たいていの女性はいかにしたら性的な歓びを得られるかではな く、いかにしたらセクシーに「見えるか」だけを知っている。社会化の結果、私たちのほとんどがスマートな外見と性的な感情を混同している。
アンジェラの個人史は女性のセクシュアリティと摂食障害との結びつきの他の部分を補ってくれる。それは、女の子、女性に対するセクシュアル・アビューズ と暴力の問題である。暴力や虐待は、男が女にするものであり、しばしば圧倒的と思われるほどひどいものである。現在、3人に1人の成人女性が子ども時代に 性的な虐待を受けたと報告されているのに対し、男性は9人に1人である。男女ともにこれらの虐待を加えているのはほとんど大部分(どこでも85%~98% と報告されている)が男性によるものである。身近な家族が女性を虐待する傾向が強いのに対して、見知らぬ者が男性を虐待することが多いようである (Young-Eisendrath, 1993, pp.375-76)。
アメリカ女性の25~45%がレイプ、もしくはレイプ未遂の状況を生きのびてきた(Beneke, 1982)。大衆的な異性愛のイメージではセックスと攻撃性が混ぜ合わされ、今やMTVからニューヨーク・タイムズの広告にいたるまで、女性に対する暴力 が「セクシー」だとか、女性を支配しようと思えば、セックスと暴力をミックスしなければならないのだと若い人々を説得している。
多くの摂食障害の女性たちは、アンジェラのように、暴力や虐待に体を支配された経験を持っている。しかも、しばしば保護してくれるはずの世話人の男によってなのである。ここにあるのは、アノレクシアの女性が過食の時期に見た夢である。
父が私を抱き倒す・・・私たちは実際にセックスをしている・・・私は目隠しされているが、目隠しがずり落ちる・・・確かに父である・・・私は暴れ叫ぶ・・・ついに目が覚める。(Brink & Allan, p.79)。
悪魔のような強姦魔、殺人として現れる性的に支配する男のイメージは、摂食障害の女性にも治療で出会う他の女性にもすべてにあまりにありふれている。夢 は性的歓びに関して多くの女性が感じている、圧倒され、目隠しされているという感情的テーマを描写している。
食物、性、攻撃性の複雑なもつれは、信頼と歓びに多くの制限を加える。ここにアノレクシアの女性の夢がある。彼女は危機的なほど体重減少し、治療を拒ん でいた。彼女の夢は、決して得られない性的歓びと無力な怒りに、美の神話が手の尽しようがないほどにもつれていることを表現している。
姉と私はショッピング・センターにいる・・・化粧品のカウンターに商品を並べている女性がいる。私たちは彼女に情報を求め、彼女はわかりにくい説明をす る。突然、大きな腫れ物が彼女の首にできる。それは息をしているように見える。彼女の首が裂け、彼女は倒れる。大きな黒い蛙が傷の中に座っている。獰猛な 爪である。その女性は今にも死にそうだが、誰も彼女を助けようがない(傍点著者)。蛙は後ろを向き、彼女ののどから胸の中へともぐり込む。(Brink & Allan, 1992, p.287)
食物と性に歓びをほとんど感じられない女性に頻繁に見られる症状は、自分に向けられた怒りの凶暴さと不吉な感じである。怒りと不吉さは早期の家庭環境の 産物であるばかりではない。女性の体を脅かす文化の状況をも物語っている。それは、女性の容貌に内在化され投影された基準の状態であり、女の子や女性に加 えられる暴力の状態であり、結果的に女たちの自己評価を下げ自己嫌悪に陥らせて、さまざまな形の精神病に陥れる危険さえあるものである。
どの発達段階でも女に対する男の暴力、攻撃性は、情け容赦なく女の攻撃性を伴う問題へと結びつく。多くの女性は、自分の欲求を勝ち取ったり、自己主張し たりすることに絶望し、混乱している。とくに、本来なら自分を愛してくれるはずの男から肉体的、情緒的に虐待を受けてきた場合はそうである。
摂食障害についてのユング派、その他の精神力動分析では、伝統的にジェンダーへの気づきを排除し、その代わりいわゆる「母子関係の失敗」に焦点を当て る。母親を責めることは、今もなお精神分析のもっとも有害な副産物のひとつである。とくに摂食障害に関して言えば、父権制における女性の体についてのより 広い理解なしに、(現実的か象徴的かを問わず、どんな形であれ)母親に焦点を当てることは、臨床家をも大衆をもひどく惑わせることになる。北米、その他の 西洋社会のあらゆる女性の人生にあるダブル・バインド、食物と性と攻撃性のもつれを認識するのでなければ、愛着パターンから自己を点検する家族システム論 や関係モデルでさえ不完全で、効果のないものになるだろう。
【おわりに】
美の神話と女の権威にまつわるダブル・バインドを認めることで私たちは解放され、北欧の女たち は、女だって健康な体のイメージ、健康な食生活、高い自己評価をまっすぐに伸ばしてよいのだと信じることができるようになる。女性が自分の食欲と歓びにつ いて学ぶことに信頼と自由を厳しく制限するような危険もトラウマもある。しかし、これらのダブル・バインドを明らかにすることで、私たちは、男のように発 達できないことで女を(そして母親を)責めるのをやめることができる。女性の発達についてのこれらの問題にははっきりした健康の基準がないため、治療者 は、アンジェラのような女性を取り巻くダブル・バインドに気づいておく必要がある。治療的な査定をする時に、特定の女性クライエントの治療の欲求を理解す るダブル・バインドとコンピテンスの両要因を含めなければならない。
自分の個人的な福祉を危険に曝すような食習慣を持つ女性たちの生活に介入するとき、私たちはいつも次のことに気づく。夢と症状における彼女たちの象徴的 表現は、私たちが女性の体を支配している文化的、社会的状況を変えるために行動しなければ、無力なまま不屈な運命にまもなく襲われるであろうということを 私たちすべてに語っているのだと。私たちが不自由な基準と美は力なりという間違った前提から女性の体を解放するまでは、女でも男でも、食物、性、攻撃性と の関係を癒すことはできないだろう。
〔注釈〕
2頁 クライエントの考えや行動の文脈を彼女のピア・グループでのジェンダーとその発達という観点 から捉えることは、違った集団では違った身体イメージの理想が作られるのだということを認識することである。摂食障害がもっともおこりやすいのは、産業社 会で上層部にある社会経済集団であると報告されている。私たちの社会では、ほとんどの摂食障害女性が白人である。アフリカ系アメリカ人についての研究で、 白人社会に同化していればいるほど摂食障害の問題を持ちやすくなることがわかっている。摂食障害を持つ全人口の5~10%だけが男性であるが、この問題で 治療を求めた男の50%以上が同性愛であった。これらの統計は、エリン・カシャック(1992)の『危険に曝された命-女性の経験についての新しい心理 学』(Basic Books)からとった。「食事」の章を参照のこと。
文献
Beneke, T. (1982). Men on rape. New York: St. Martin's Press. (鈴木・幾島訳『レイプ・男からの発言』筑摩書房 1988)
Brink, S.G. & Allan, J.B. (1992). Dreams of anorexic and bulimic women: A reserch study. Journal of Analytical Psychology, 37, 275-297.
Broverman, I.K., Vogel, S.R., Broverman, D.M., Clarkson, F.E. & Rozenkrantz, P.S. (1972). Sex-role stereotypes: A current appraisal. Journal of Social Issues, 28, 59-78.
Chernin, K. (1981). The obsession: Reflection on the tyranny of slenderness. New York: Harper & Row.
Chernin, K. (1985). The hungry self: Women, eating and identity. New York: Harper & Row.
Levitan, H.L. (1981). Implications of certain dreams reported by patients in the bulimic phase of anorexia nervosa. Canadian Journal of Psychiatry, 26, 228-31.
Maccoby, E.E. (1990). Gender and relationships: A developmental account. American Psychologist, 45, (4), 513-520.
Orbach, S. (1978). Fat is a feminist issue: A self-help guide for compulsive eaters. New York: Berkeley.
Orbach, S. (1986). Hunger strike: The anorectic's struggle as a metaphor for our age. London: Faber & Faber. (鈴木他訳『拒食症』新曜社 1992)
Ruble, D. (1983). Sex-role development. In M.H. Bornstein & M.E. Lamb (Eds.) Developmental Psychology: An advanced textbook. Hillsdate, N.J.: Erlbaum.
Sours, J.A. (1980). Starving to death in sea of objects: The anorexia nervosa syndrome. New York: Jason Aronson.
Tavris, C. (1992). The mismeasure of woman. New York: Simon & Schuster.
Thoma, H. (1967). Anorexia nervosa. G. Brydone, Trans. New York: International Universities Press.
Wolf, N. (1991). The beauty myth: How images of beauty are used against women. New York: William Morrow.
Wooley, O., Wooley, S. & Dyrenforth, S. (1979). Obesity and women: A neglected feminist topic. Women Studies Quarterly, 2, 81-92.
Young-Eisendrath, P. & Wiedermann, F. (1987). Female authority: Empowering women through psychotherapy. New York: Guilford Press.
Young-Eisendrath, P. (1993). You're not what I expected: Learning to love the opposite sex. New York: William Morrow.
(以上、村本邦子訳)


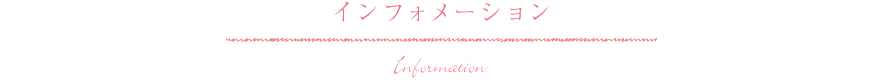
 現在、我が国でも痩せ礼賛の風潮はますます強まり、ダイエット本やダイエット食品、シェイプアップ器具は巷にあふれています。また、「今ダイエット中よ」 という会話は日常茶飯事です。拒食、過食、嘔吐、下剤を使っての浄化すら特別なことではなくなってきており、摂食障害は顕著に増加してきています。場所や 時代が変われば美の基準が変わり、その基準に振り回されてしまう女性の体って、何なのでしょうね。「何かおかしいと思うけど、やっぱり痩せたい」という一 般の女性から、専門的な関心を持つ方まで、幅広く読んでいただけるようさまざまな角度から、この問題に迫りました。執筆者の中には過去に摂食障害を経験し た人も含み、フェミニストでありユング派の分析家である、P.Y.アイゼンドラスによる寄稿論文を掲載していることでもとても貴重なものになっています。
現在、我が国でも痩せ礼賛の風潮はますます強まり、ダイエット本やダイエット食品、シェイプアップ器具は巷にあふれています。また、「今ダイエット中よ」 という会話は日常茶飯事です。拒食、過食、嘔吐、下剤を使っての浄化すら特別なことではなくなってきており、摂食障害は顕著に増加してきています。場所や 時代が変われば美の基準が変わり、その基準に振り回されてしまう女性の体って、何なのでしょうね。「何かおかしいと思うけど、やっぱり痩せたい」という一 般の女性から、専門的な関心を持つ方まで、幅広く読んでいただけるようさまざまな角度から、この問題に迫りました。執筆者の中には過去に摂食障害を経験し た人も含み、フェミニストでありユング派の分析家である、P.Y.アイゼンドラスによる寄稿論文を掲載していることでもとても貴重なものになっています。